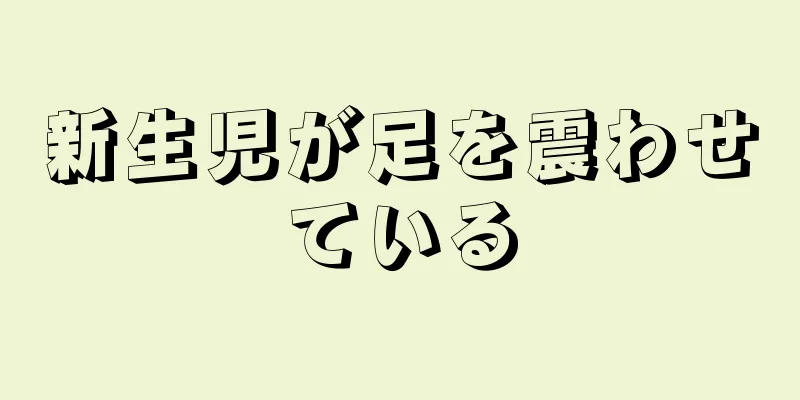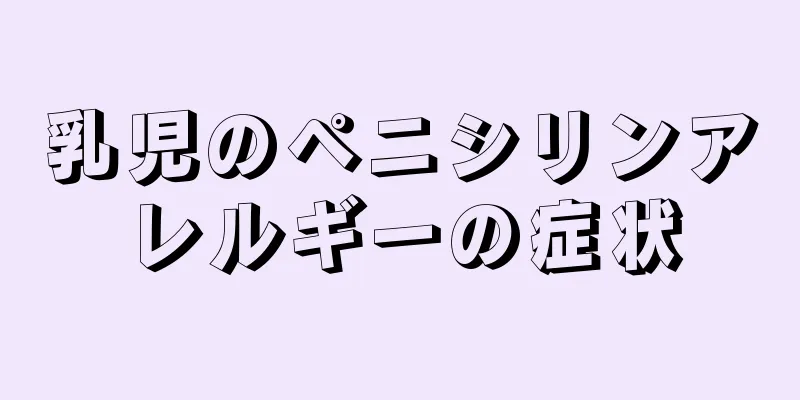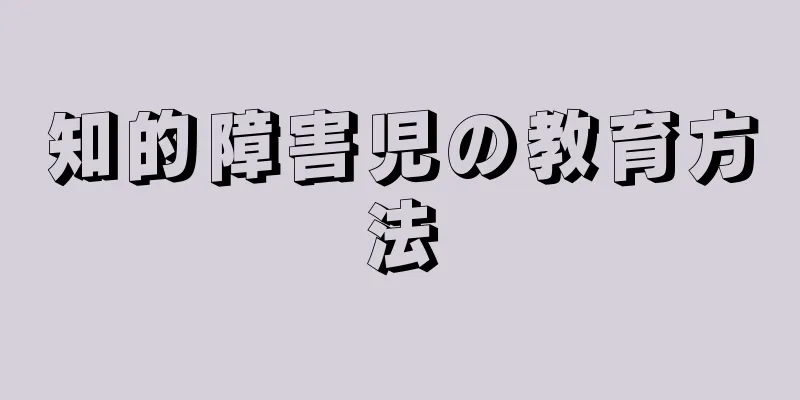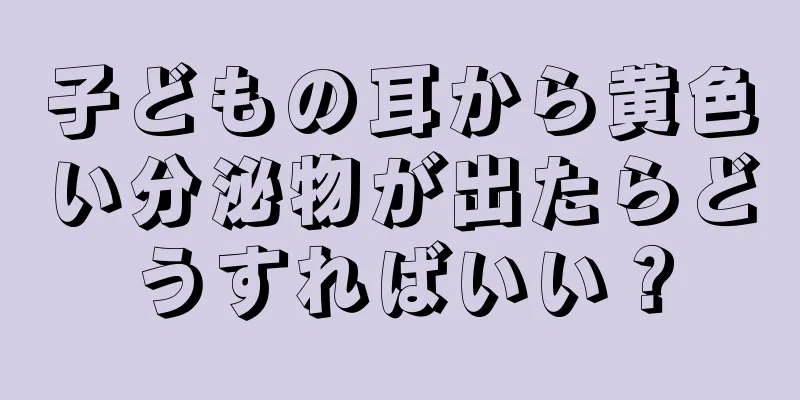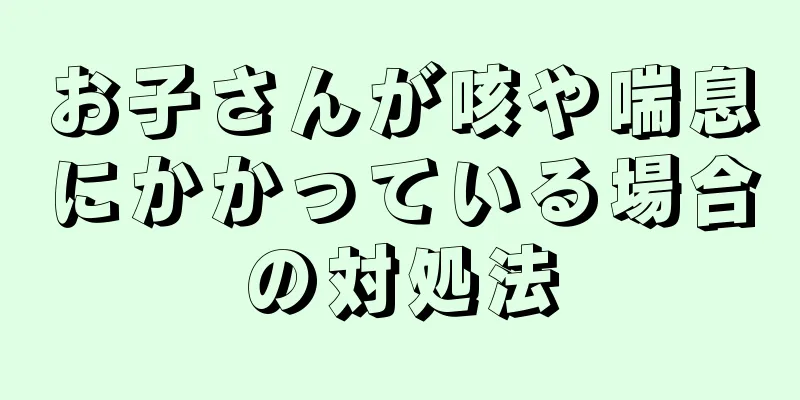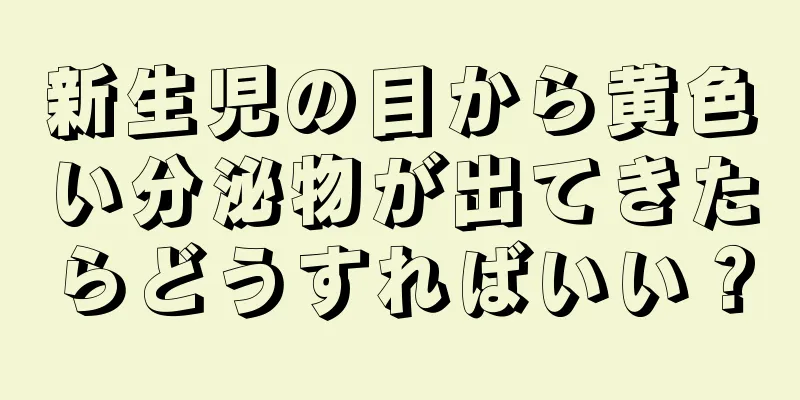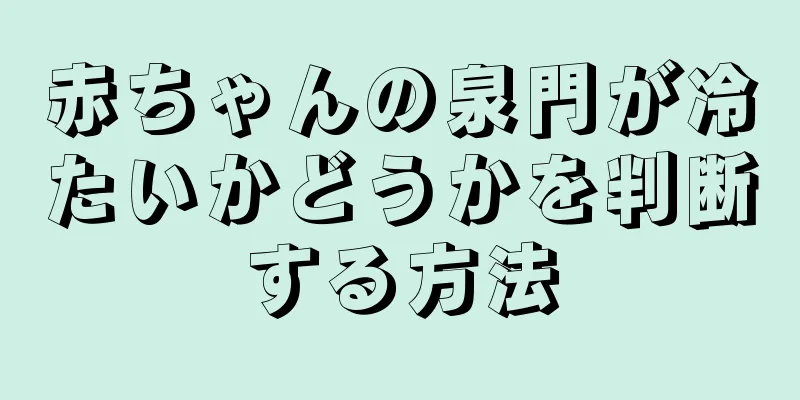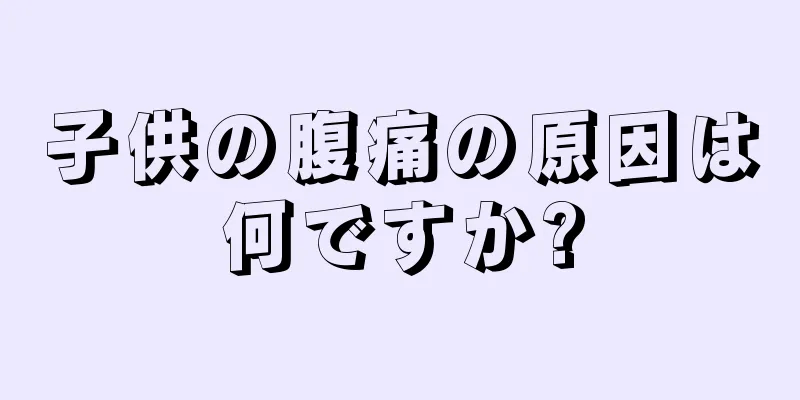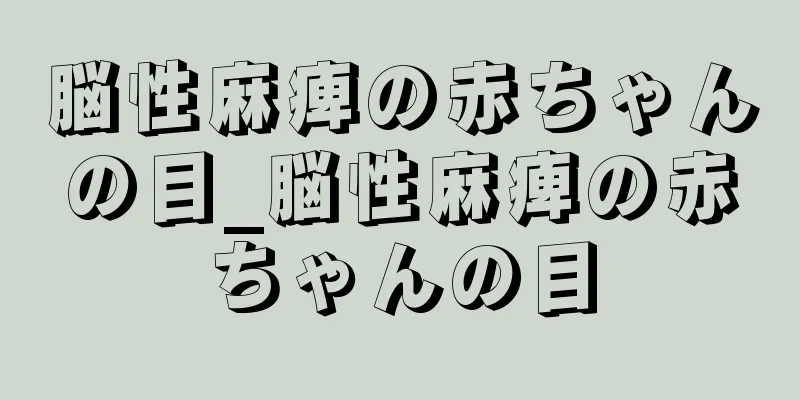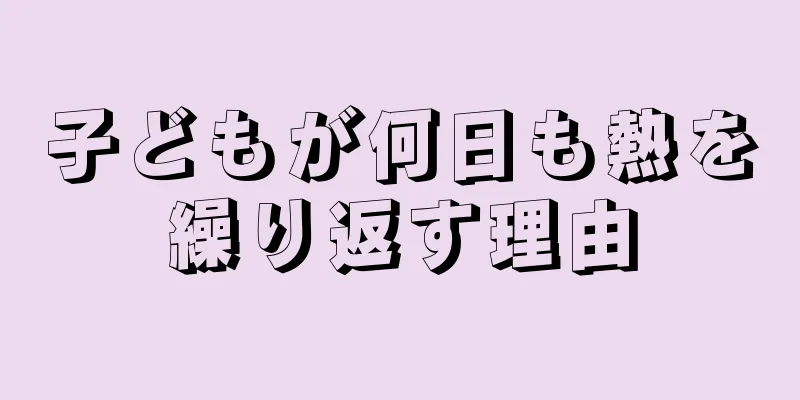子供が真菌感染症にかかったらどうするか
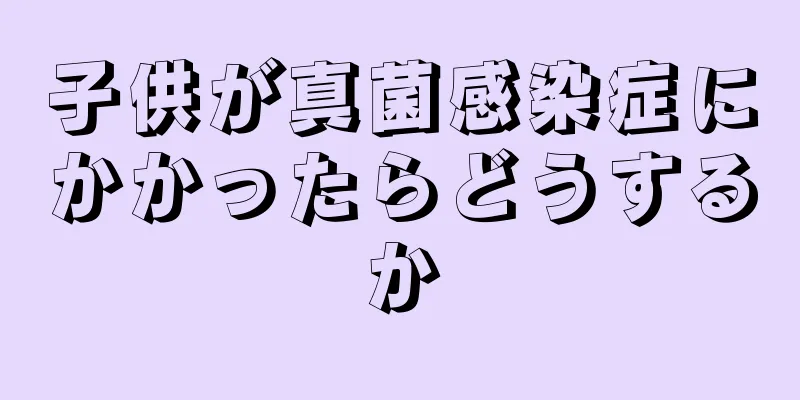
|
真菌感染症は比較的よく見られる病気であり、発症時には患者に大きな痛みを引き起こすこともあります。多くの子供たちは抵抗力が弱いため真菌感染症に苦しんでいます。幼児の真菌感染症の治療には特別な方法が必要です。幼児の体は大人の体と異なるため、体質に応じて適切な治療法を採用する必要があります。子供の真菌感染症の治療法をいくつかご紹介します。 1. 一般的な治療 カンジダ膣炎は、外陰部を重曹水で洗浄すること、ナイスタチン膣坐薬を使用すること、およびケトコナゾールまたはクロトリマゾールを経口摂取することで治療できます。下着は毎日交換し、洗って煮沸消毒してください。 1 回の治療コース後に真菌検査が陰性であり、各月経周期後の真菌検査も陰性であれば、3 回連続した強化治療コースの後に患者は治癒したとみなされます。カンジダ膣炎を引き起こす可能性のある他の疾患を積極的に治療し、感受性因子を排除します。外陰部を清潔で乾燥した状態に保ち、掻かないようにしてください。治療中は性交は禁止です。辛いものや刺激の強い食べ物を食べるのはお勧めできません。 2. 膣内投薬 膣に塗布するイミダゾール坐剤の使用は、カンジダ膣炎に良い効果があります。クロトリマゾール坐薬を毎晩 1 錠服用し、洗浄後に膣内に挿入します。10 〜 14 日間が治療コースです。または、ダクタリン坐薬を毎晩 1 錠服用し、洗浄後に膣内に挿入します。7 日間が治療コースです。 3. 膣のpH値を変える カンジダ菌の増殖に最も適した pH 値は 5.5 です。したがって、アルカリ溶液を使用して外陰部と膣を洗浄し、膣の酸性度とアルカリ度を変えると、真菌の増殖と繁殖が抑制されます。 2%~4%の重曹水を使用して、1日1~2回膣を洗浄します。1回の治療期間は2週間です。洗浄後は外陰部を拭いて乾かし、カンジダの増殖を抑えます。 4. 経口薬 真菌感染症は性交を通じてカップル間で伝染する可能性があるため、両者とも腸内カンジダを抑制する経口薬で治療することができます。フルコナゾールの経口投与量:1回150 mgを一度に服用します。または、スポラノックスを経口摂取します。カンジダ膣炎の初感染の場合は、1 回 200 mg を朝食と夕食後に服用し、1 日だけ服用します。再発性カンジダ膣炎の場合は、スポラノックスの投与量を増やす必要があり、1 回 200 mg を 1 日 1 回、3 日間連続で服用するか、1 回 100 mg を 1 日 2 回、3 日間連続で服用することができます。食後に薬を飲んでください。 5. 外用軟膏 クロトリマゾール軟膏またはダクリリン軟膏を外用すると、真菌感染による外陰炎を治療し、外陰部のかゆみや痛みの症状を緩和することができます。 2週間にわたり、毎日数回外用してください。易福清軟膏はエコナゾールを主薬とし、少量の局所ステロイド治療薬を加えて作られており、優れた止痒効果があり、外陰部の耐え難い痒みや痛みがあるカンジダ性外陰炎や膣炎の人に適しています。朝と夕方に1回ずつ、外陰部に塗布してください。 |
推薦する
子供の白血球数は16万
私たちは皆、人体の中に白血球があること、そして白血球が私たちにとって特に重要であることを知っています...
子供が嘔吐する原因は何ですか?最もリアルな状況をお知らせします
子どもの胃腸機能はまだ完璧ではないため、嘔吐の症状がよく見られます。最も一般的な原因は、悪い食べ物を...
新生児の皮膚が剥がれる原因は何ですか?
新生児の皮膚剥離は新生児に非常によく見られる病気であることは誰もが知っています。出産前、新生児は母親...
私の子供はなぜ瞬きし続けるのでしょうか?
目は世界と直接接触する最初の窓です。目を通して私たちは物事を学び、見ることができます。目に問題があれ...
子供の睾丸が肥大する理由は何ですか?
お子様の睾丸が腫れていることに気づいたら、親は細心の注意を払う必要があります。これは非常に有害で、症...
赤ちゃんは薬と粉ミルクを一緒に飲んでも大丈夫ですか?
多くの人が疑問を抱いています。「薬と粉ミルクを一緒に飲んでも大丈夫なのか?」薬は体を治すために使われ...
赤ちゃんに乳汁が溜まってしまったらどうすればいい?
母乳と粉ミルクを半分ずつ混ぜて育てた赤ちゃんもいます。生後2か月になると、粉ミルクを食べたり母乳を飲...
子供の目の端が赤くなる原因は何ですか?
子どもの目はまだ完全には発達しておらず、成熟の過程でさまざまな問題が発生しやすく、目に回復不可能な損...
新生児はどのくらいの頻度で排便するのでしょうか?
誰もが自分の赤ちゃんが健康に育つことを願っています。赤ちゃんの消化管での食物の吸収は新生児の便を見れ...
子どもの食欲を増進する方法
親が最も心配するのは子供たちです。子供たちの食欲が落ちていると、親は非常に心配し、子供たちにもっと食...
乳児湿疹は治るのにどれくらい時間がかかりますか?
最近では、多くの人が自分の体の変化、特に赤ちゃんの変化を非常に心配しています。子供は幼い頃に何度も湿...
子どもの視力発達基準と視力検査を始める時期
現在、近視の人は多く、特に子供が多く、子供の近視の症例数は増加しています。子供の近視の原因は多く、一...
子供の首の痛みの原因
子供の体のあらゆる症状は、多くの母親が心配する問題です。多くの母親は、子供が朝に首が痛んだり、体の痛...
赤ちゃんがベッドから落ちてしまったら何に注意すればいいでしょうか?
赤ちゃんが動けるようになったら、母親は赤ちゃんの世話にもっと気を配り、特に赤ちゃんがベッドから落ちな...
赤ちゃんがなかなか眠れない理由は何でしょうか?
赤ちゃんの睡眠は多くの母親が毎日心配している問題であり、特に赤ちゃんが寝つきにくいという問題です。そ...