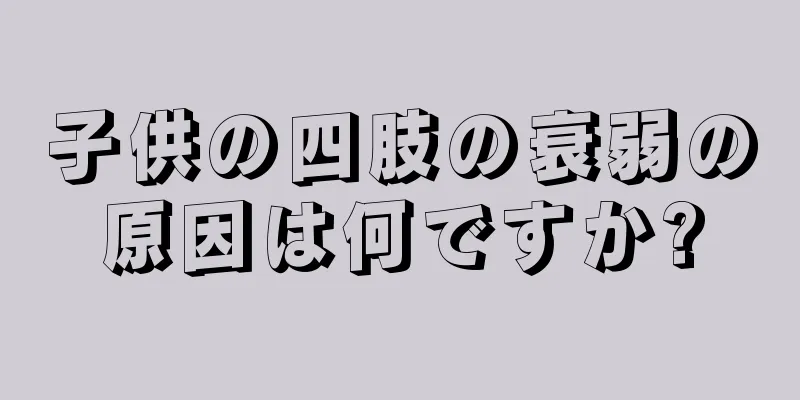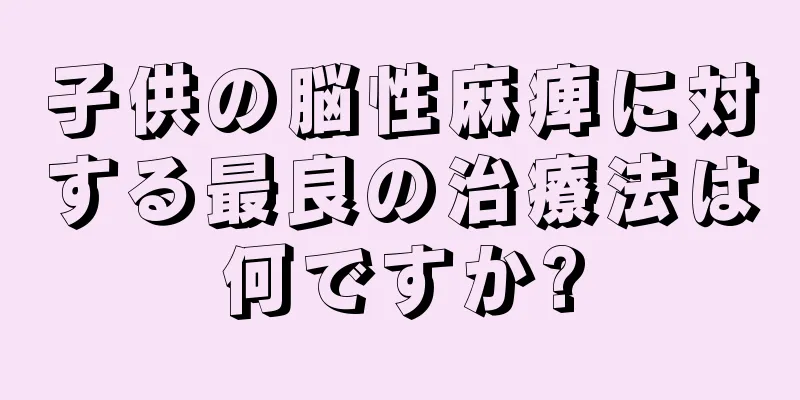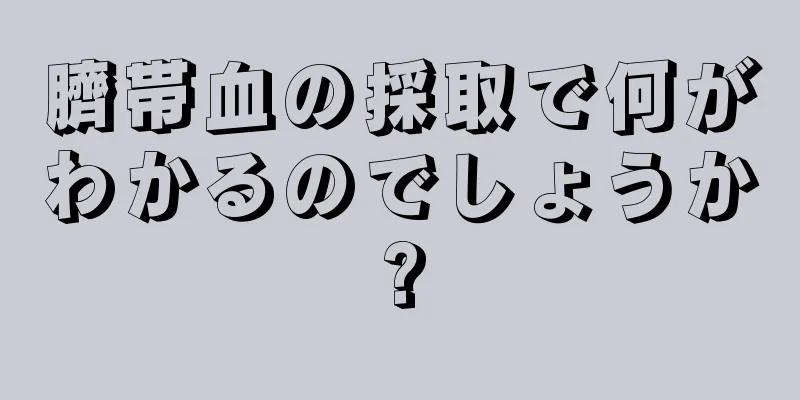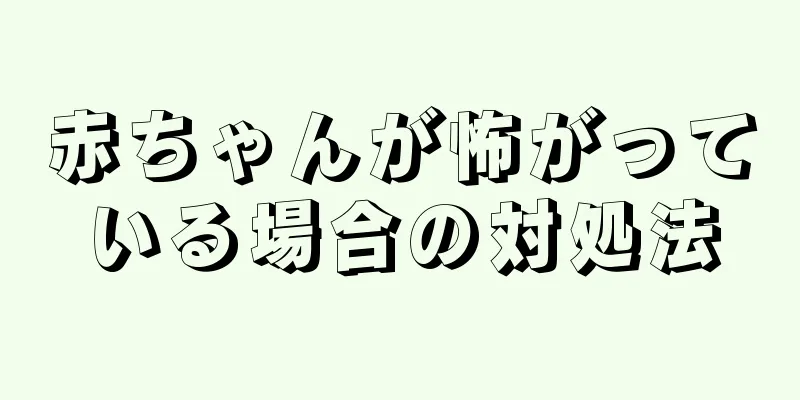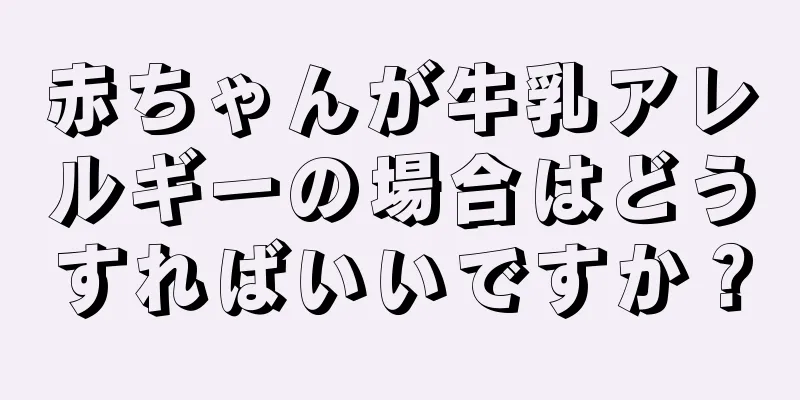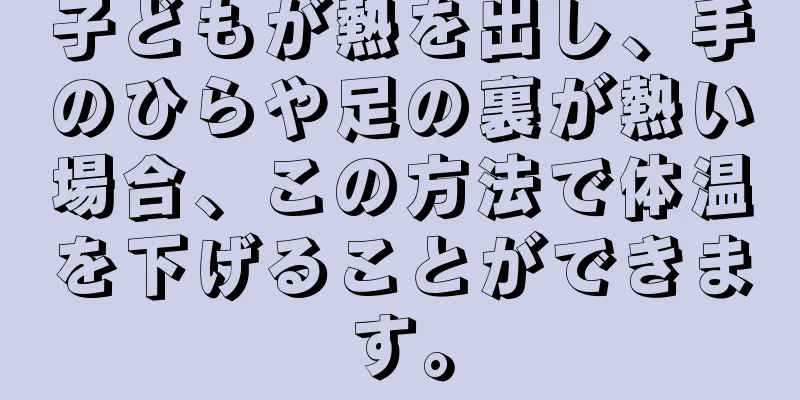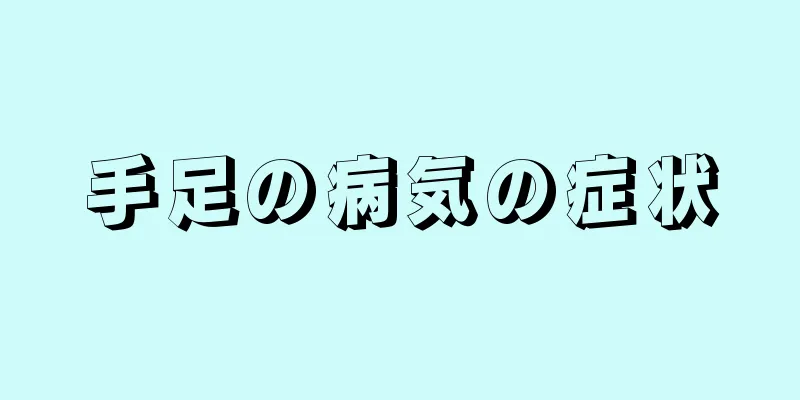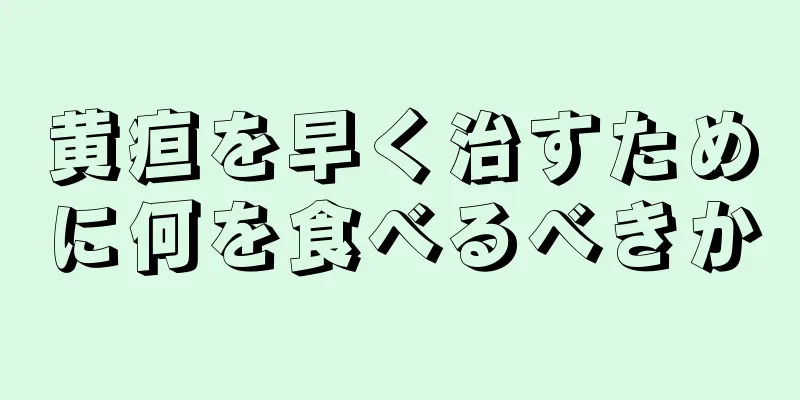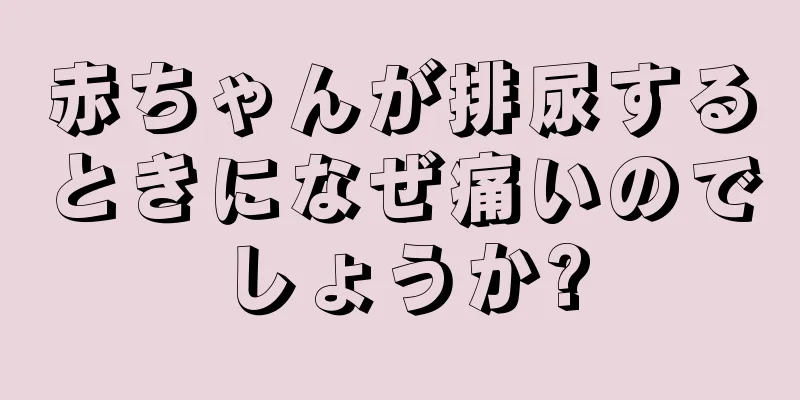子供の体温が374度になるのは普通ですか?
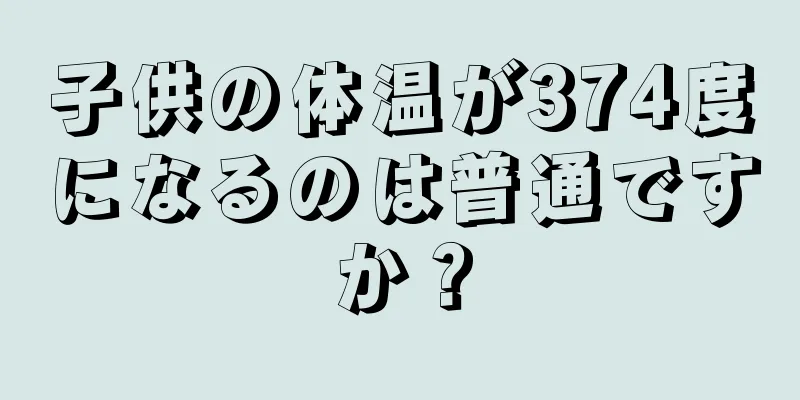
|
どの子供も家族全員の「宝物」であり、特に子供をとても愛する高齢者にとっては、子供が口の中で溶けてしまうのではないかと心配するほどです。そのため、子供に何か異常があると、親は真剣に受け止めます。子供の体温が37.4度に達していることに気づいた親の中には、この体温が熱ではないかと心配した人もいました。では、子供の体温が374度というのは正常なのでしょうか? まず、子供の体温が37.4℃というのは正常なのでしょうか?子供の基礎体温は36.9℃~37.5℃です。一般的に、体温が基礎体温より1℃以上高くなると発熱とみなされます。このうち、微熱は体温が38℃前後で変動するもの、高熱は体温が39℃以上となるものを指します。 2週間以上発熱が続く場合を遷延性発熱といいます。 上記基礎体温は肛門から測る直腸温のことであり、一般的に口腔温は直腸温より0.3℃~0.5℃低く、腋窩温は口腔温より0.3℃~0.5℃低くなります。子どもの正常な基礎体温は36.9℃~37.5℃です。一般的に、体温が基礎体温より1℃以上高くなると発熱とみなされます。このうち、微熱は体温が38℃前後で変動するもの、高熱は体温が39℃以上となるものを指します。 2週間以上発熱が続く場合を遷延性発熱といいます。上記基礎体温は肛門から測る直腸温のことであり、一般的に口腔温は直腸温より0.3℃~0.5℃低く、腋窩温は口腔温より0.3℃~0.5℃低くなります。 第二に、一般的に体温が 36 度を下回ると低体温症とみなされます。幼児は中枢体温調節システムがまだ完全には発達しておらず、皮下脂肪が薄く熱を放散しやすいため、低体温症に非常にかかりやすいです。低体温症の乳児は、一般的に特定の症状を示し、泣き声を上げたり、授乳を拒否したり、皮膚が冷たくなったり、血糖値が低下したり、皮下脂肪に塊ができたりします。低体温症の乳児は、適切な処置を受けなければ衰弱し抵抗力が低下し、重症の場合は命が脅かされることもあります。したがって、親は赤ちゃんの体温が低すぎることに気づいたら、体温を上げる対策を講じるか、医師の診察を受ける必要があります。一般的に体温を上げるには2つの方法があり、それらを組み合わせて使う必要があります。 子供の体温が 374 度になるのは正常ですか? 暖かく保ちましょう: 室温は 20 度を下回らないようにしてください。赤ちゃんが厚くて暖かい服を着て、綿の帽子をかぶっていることを確認してください。綿の帽子の外側に 1 つまたは複数の湯たんぽを置いて暖めるのが最適です。赤ちゃんの服を着替えるときは特に注意してください。栄養強化に注意してください:適切なブドウ糖補給は、赤ちゃんの寒さに対する抵抗力をある程度高め、体温が正常に戻るのを助けます。上記の方法が効かず、赤ちゃんの体温がまだ低すぎる場合は、すぐに病院に行って医師の診察を受け、低体温の原因を突き止め、さらに治療とケアを行う必要があります。 |
>>: なぜ8歳の子供はいつもジャンプするのが好きなのでしょうか?
推薦する
子供の頭頂部に白い斑点がある
子供は幼く、ウイルスや細菌の感染を受けやすいため、身体的な問題を抱えることが多いのは普通のことです。...
子供の発熱によるけいれんの原因
親は子供の体の健康をもっと心配しています。子供が病気にかかったとき、親はとても心配します。実際、発熱...
赤ちゃんのおへそを元に戻すにはどうすればいいですか?
赤ちゃんのへそは、実は一般の人たちの間では一般的な名前です。医学では、臍ヘルニアと呼ばれています。へ...
子供の首のリンパ節の腫れの症状
「アンダー・ザ・ドーム」を見て以来、母親として柴静の責任感に深く感動しています。子供のリンパ節の腫れ...
赤ちゃんは転んだ後に眠くなるのでしょうか?
子どもに関して言えば、誰もが子どもがいたずらすぎると感じているはずです。子どもは動き回るのが好きで、...
子供の右目の視界がぼやける原因は何ですか?
現代の科学技術は比較的発達しているため、多くの家庭にはコンピューターやテレビが備わっています。子供時...
子どもが鼻水を出したときはどうすればいいですか?
子供は鼻水が出やすいグループであり、これは彼らの比較的低い体の抵抗力に直接関係しています。特に、多く...
乳児にマイコプラズマ感染症が発生した場合の対処法
赤ちゃんの中には体に問題を抱えている人もいますので、赤ちゃんの健康を確保するために、適切な措置を適時...
5歳の女の子の身長と体重はどれくらいですか?
時代の進歩とともに、人々は子供、特に子供にとって発達の黄金期である幼少期に、ますます注目するようにな...
小児における亜鉛欠乏症の予防と治療
人生において誰もが知っているように、成長・発育期にある子供は十分な量の亜鉛を補給する必要があります。...
お子さんが口内炎になった場合の対処法
口内炎は私たちの生活の中でよくある問題であり、日常生活に非常に不便をきたし、多くの食べ物が食べられな...
赤ちゃんの体中に赤い斑点がある場合はどうすればいいですか?
今では、どの家庭にも子どもは一人しかおらず、多くの子どもの親は高齢化しているため、誰もが赤ちゃんに特...
子どもは瞬きを頻繁にします。その理由を詳しくお教えしましょう。
親が子供が頻繁に瞬きをしていることに気付いた場合、子供の目が不快である可能性があります。これは異常な...
2歳児が夜に熱を出したらどうするか
2歳児は体の抵抗力が比較的弱く、寒い天候では発熱しやすくなります。子どもの熱は、家族を間違いなく非常...
子どもの健康を守る栄養豊富な食品6選
最近は、特に学校では、多くの人が眼鏡をかけています。多くの子供たちも眼鏡をかけていることに気づくでし...