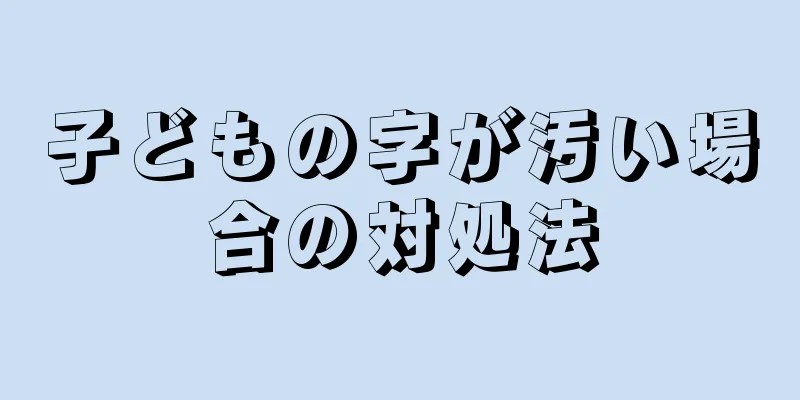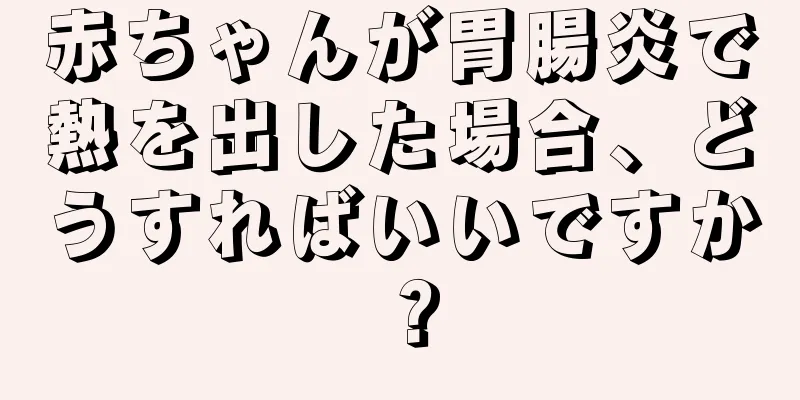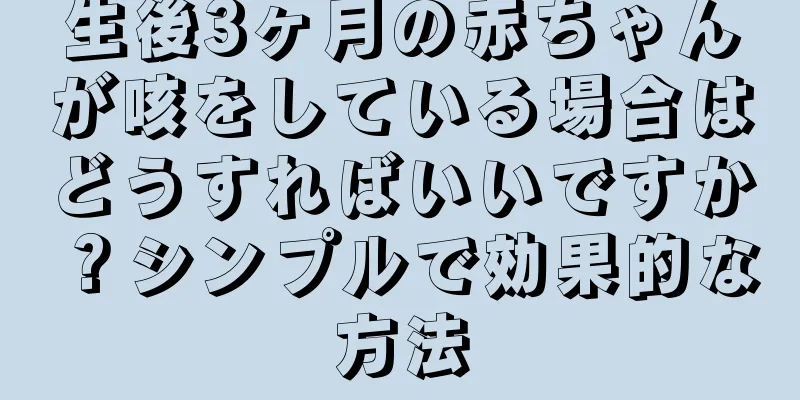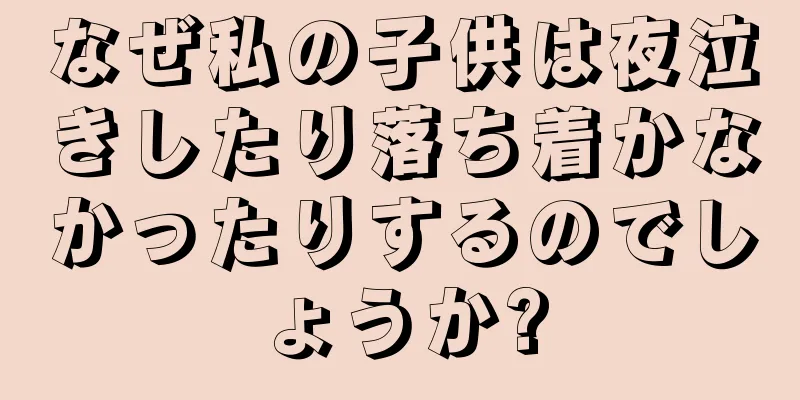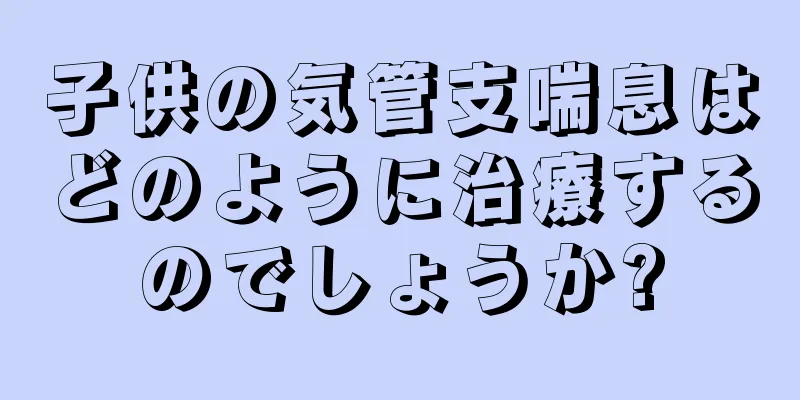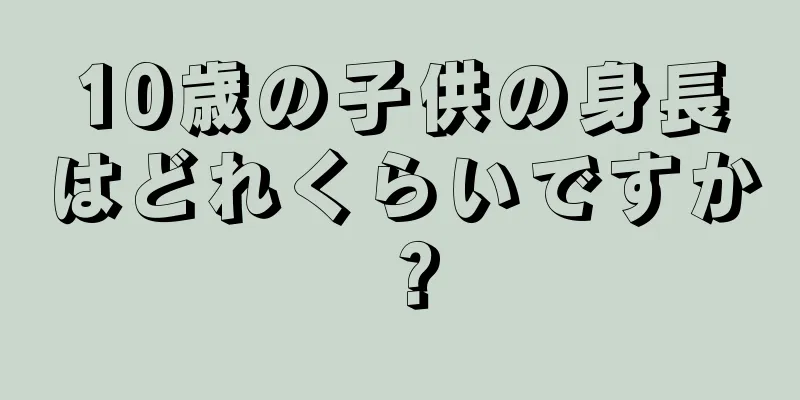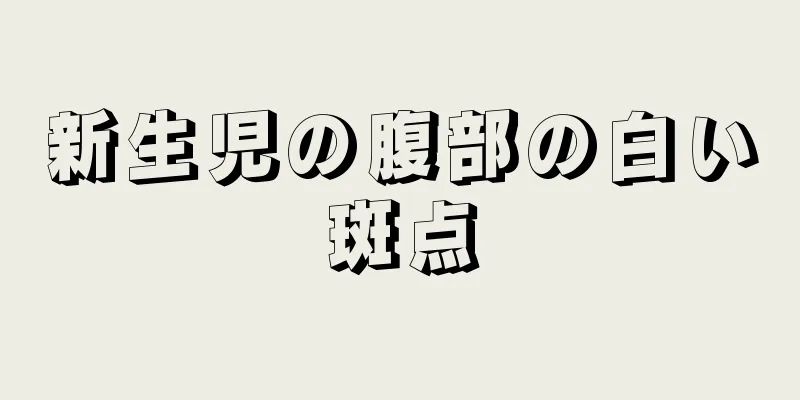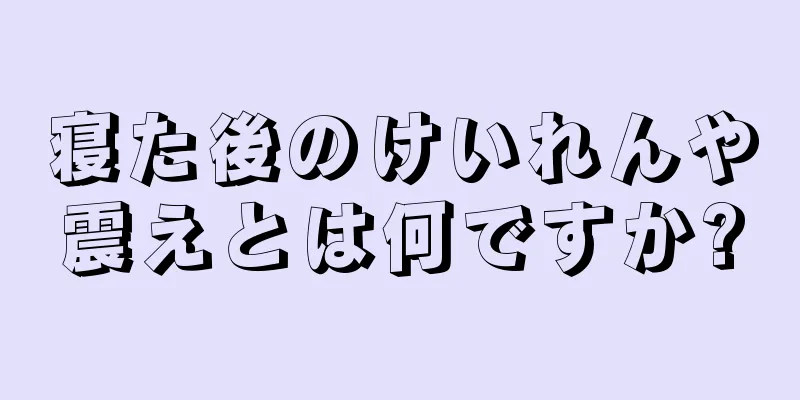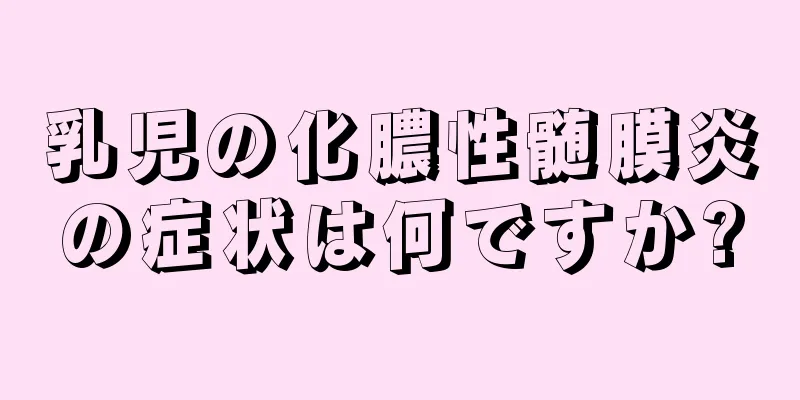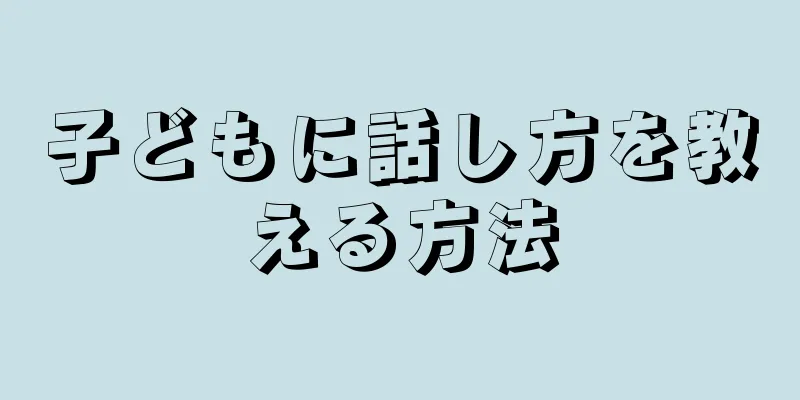新生児黄疸指数について
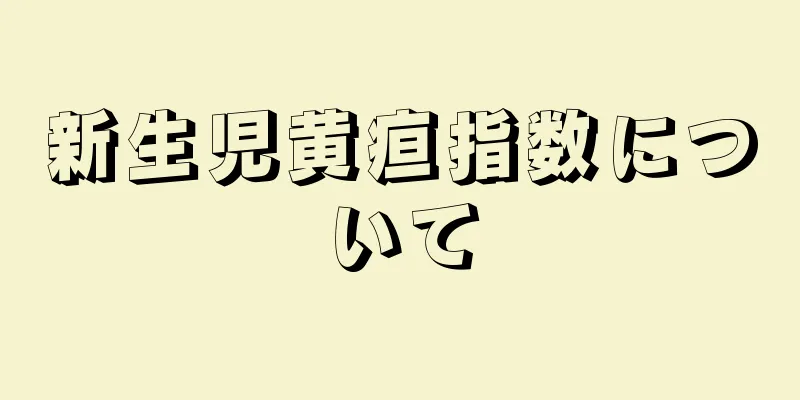
|
最近、多くの親が、自分の子供が生後間もなく新生児黄疸という病気にかかったと報告していますが、新生児黄疸が何を意味するのかを知っている人はほとんどいません。この病気は一般的にまれであるため、一般の人々はそれについて知らないのが一般的です。今日は新生児黄疸とは何かについてご紹介します。私たちは人生においてこの問題をどのように解決すべきでしょうか? 医学的には、生後1ヶ月未満(生後28日以内)の新生児に起こる黄疸を新生児黄疸といいます。新生児黄疸とは、新生児期のビリルビン代謝異常により、血液中のビリルビン濃度が上昇し、皮膚、粘膜、強膜に黄疸を呈する疾患を指します。この疾患は、生理的疾患と病理的疾患に分けられます。生理的黄疸は生後2~3日で現れ、4~6日目にピークに達し、7~10日目に消失します。未熟児ではより長く続き、軽い食欲不振を除いて他の臨床症状はありません。生後24時間以内に黄疸が出現し、毎日の血清ビリルビンが5mg/dl以上または1時間あたり0.5mg/dl以上増加し、満期産児では2週間以上、未熟児では4週間以上長期間持続し、それでも治まらない、あるいはさらに深刻化して悪化し続ける、または治まっても再び現れる場合、または生後1週間から数週間以内に黄疸が現れ始める場合は、病的黄疸です。 原因 1. ビリルビンの過剰産生 赤血球の過剰な破壊と腸肝循環の増加により、血清中の非抱合型ビリルビンが増加します。一般的な原因としては、赤血球増加症、血管外溶血、同種免疫溶血、感染症、腸肝循環の増加、赤血球酵素欠乏、赤血球形態異常、異常ヘモグロビン症などが挙げられます。 2. 肝ビリルビン代謝異常 肝細胞のビリルビンの吸収・結合機能が低下するため、血清中の非抱合型ビリルビンが増加します。一般的な原因としては、低酸素症および感染症、クリグラー・ナジャー症候群、ギルバート症候群、ルーシー・ドリスコル症候群、薬剤(スルホンアミド、サリチル酸塩、インドメタシン、スクテラリアなど)、先天性甲状腺機能低下症などが挙げられます。 扱う 1. 光療法 これは血清中の非抱合型ビリルビンを減らすためのシンプルで効果的な方法です。新生児を光線療法ボックスに入れ、網膜を傷つけないように両目を黒いアイマスクで保護し、会陰と肛門をおむつで覆い、体の残りの部分は露出したままにします。片側または両側から2~48時間(通常は4日以内)光照射を行います。ビリルビンが7mg/dL未満に低下したら治療を中止できます。 2. 血液交換療法 交換輸血はビリルビンを効果的に減らし、感作赤血球を補充し、貧血を軽減します。ただし、輸血には一定の条件が必要であり、副作用が生じる可能性もあるため、適応症を厳密に遵守する必要があります。 上記は専門家が紹介した新生児黄疸に関する一般的な知識ですので、多くの親がまだ新生児黄疸を理解していない場合は、上記の内容を読んでみてください。親として、私たちは新生児黄疸についてもっと注意を払うか、情報を読むべきです。これは赤ちゃんに対する責任感の表れでもあります。 |
推薦する
うちの2歳の赤ちゃんは話しません。何が起こっているのでしょうか?
結婚したばかりの頃、私たちは親になることを特に楽しみにしていました。それは素晴らしいことだったからで...
子供が食後に吐いてしまったらどうすればいい?
最近では、ほとんどの家庭が赤ちゃんを一人しか産まないため、赤ちゃんにもっと注意を払い、子供の健康、栄...
子供は黄耆を食べることができますか?
子どもの臓器はまだ十分に発達していないため、多くの薬を気軽に服用することはできません。多くの親は、子...
子供が機嫌が悪くなる理由
非常に気性の荒い子供もいます。家庭で甘やかされすぎている、先天的な理由があるなど、理由は様々です。こ...
知的障害の症状
子どもが成長するにつれて、親は子どものあらゆる側面を理解し、子どもに問題が生じたときには適時に改善で...
子どもの恐怖症の原因と臨床症状
小児恐怖症とは何でしょうか?多くの子供たちがこのような問題に直面しています。この病気の状況を無視する...
子供の腎不全の症状は何ですか?
腎虚は実は病気であり、子供に起こりやすいです。腎虚は患者の寿命に深刻な影響を与え、多くの病気を引き起...
早産児がミルクをあまり飲まない場合はどうすればいいですか?
早産は人生においてよくある現象です。現代人の生活のプレッシャーが増すにつれ、多くの人が妊娠後により大...
小児の心肺蘇生法はどのように行うのでしょうか?
心臓が止まったり、呼吸が止まったりした場合には、CPR が必要です。 CPR は、胸骨圧迫と人工呼吸...
赤ちゃんが鼻からミルクを吐き出すときの治療法
最近、赤ちゃんがミルクを鼻から吐き出す頻度がますます高くなっています。この病気は最近、大きな被害をも...
赤ちゃんが蕁麻疹になったらどうするか
赤ちゃんの皮膚は発育期には非常に敏感です。赤ちゃんの皮膚が外界から刺激を受けたり、不適切な食事を摂っ...
子供が夜中に咳をし続ける場合はどうすればいいですか?
子どもが成長するにつれて、多かれ少なかれ何らかの病気を発症することが多く、病気の発生はしばしば子ども...
赤ちゃんの脾臓と胃の虚弱を治療するには?
時々、赤ちゃんがいつも便秘、消化不良、腹痛、膨満感に悩まされていることに気づきます。母親として、私た...
「リトル・ファッティ」の腫瘍は無視できない
がん病院の最新の統計によると、がんを患う子供の数は日々増加しており、親は警戒する必要がある。 200...
子供の筋炎は回復するのにどれくらい時間がかかりますか?
筋炎は、子供が幼いときに罹患する可能性が高い病気です。この病気は、子供にふくらはぎの筋肉に痛みを感じ...