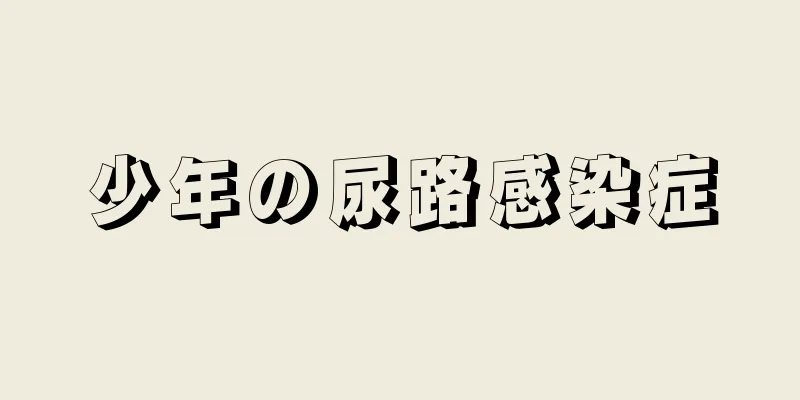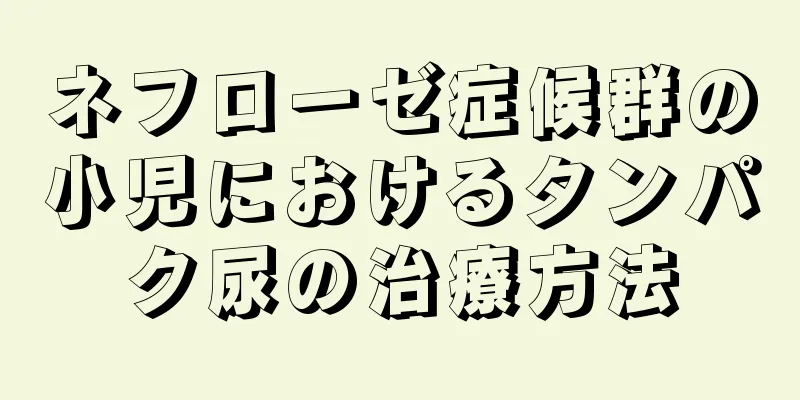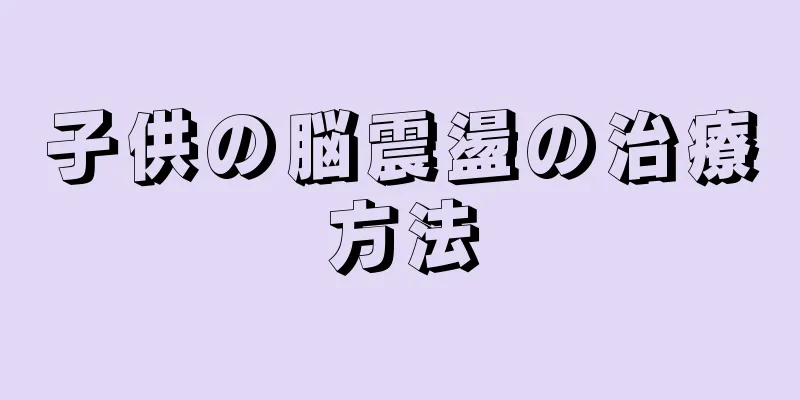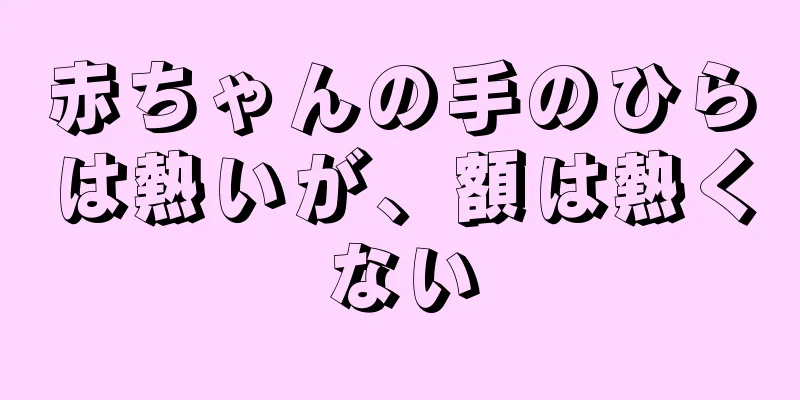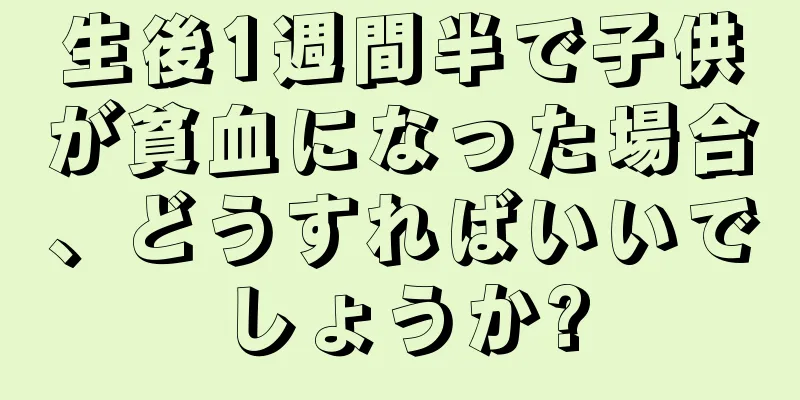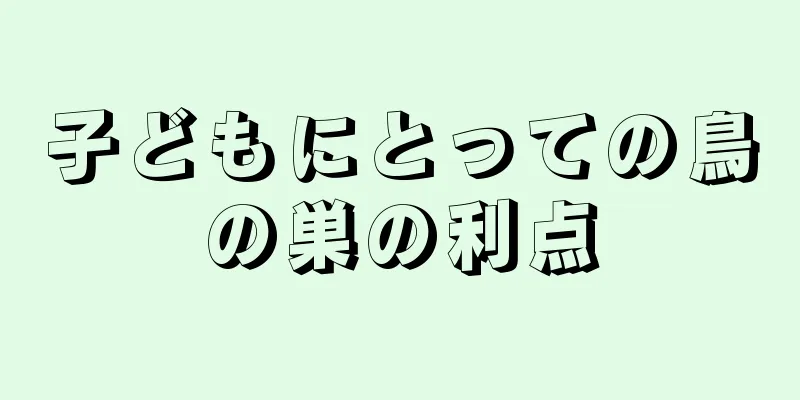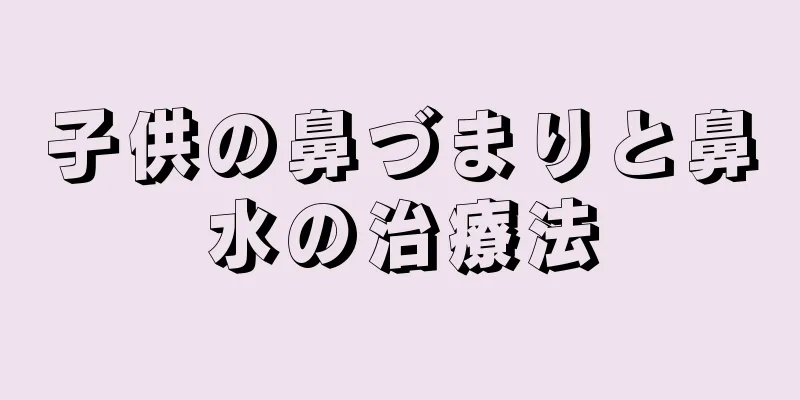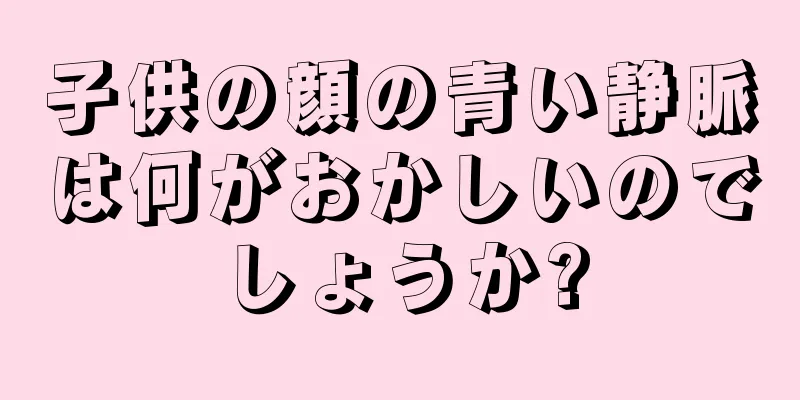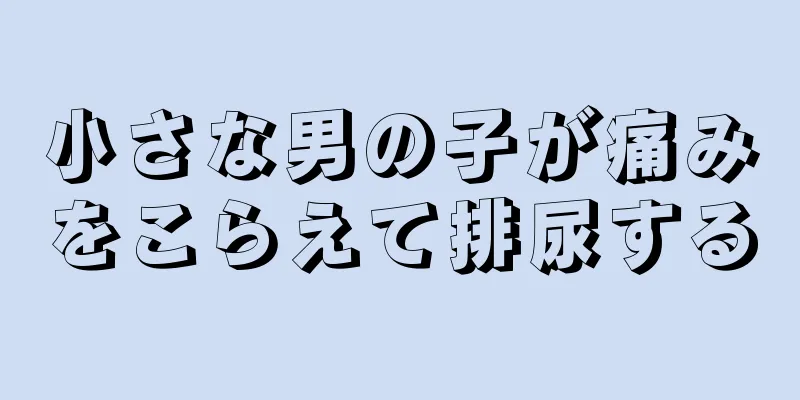反抗的な子供への言葉
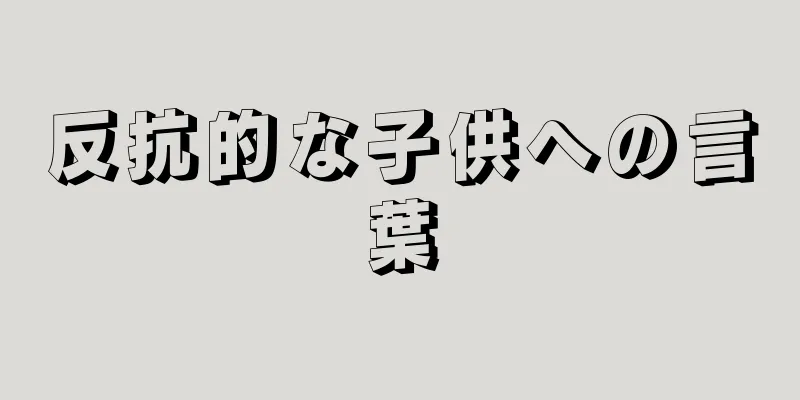
|
子どもは思春期を迎えると反抗的な行動をとるようになります。親からの適切な指導がなければ、多くの違法行為や規律違反が起こる可能性があります。さらに、この時期の子どもは親に口答えしたり、衝突を起こしたりする傾向があります。親は子どもに辛抱強く接し、厳しい手段をとらず、子どもと話し合う必要があります。では、反抗期の子どもは親とどのようにコミュニケーションをとればよいのでしょうか。どうすれば仲良くやっていけるのでしょうか。 1. 子どものことをもっとよく知る 親は生計を立てるのに忙しい一方で、子どもについてもっと知り、子どもや教師ともっとコミュニケーションを取り、学校や家庭での子どもの成績を総合的に把握するよう努める時間も取らなければなりません。理解が深まるほど、誤解は少なくなります。こうすることで、子どもが本当に言うことを聞かなくなったときに、どのように子どもを導けばよいかがよくわかるようになります。 2. 教育知識を吸収する 社会が変化するにつれ、子どもたちが育つ環境も常に変化しており、当然、教育の方法も改善され続ける必要があります。親として、新しい教育知識を積極的に吸収するのはあなたの義務です。伝統的な親子教育法では、親が権威をもって子どもを教育することがほとんどであり、教育を受ける権利に対する罰は教育権威の重要な手段である。新しい知識を吸収することで、親は自分の成長経験から抜け出し、教育の概念をタイムリーに調整できるようになります。 3. 子どもの話を辛抱強く聞く 親が激怒している場合、規律に従わない子供と対面した時の最も直接的な反応は通常、罵倒することです。こういう時は、まず親が落ち着いて、もっと我慢強くなり、子どもになぜそんなことをしたのかを尋ねることが推奨されます。親が子供の考えを理解し、問題解決に役立つ方法を見つけることに集中すると、子供の行動が実際には理解できることに気づき、多くの否定的な感情も解放されるかもしれません。 4. プライドを捨てる 親の中には、子供の前では常に威厳を保ちたいと考え、子供に対して上から目線の態度で接することに慣れている人もいます。親が本当に謙虚になり、心の底から子供を尊敬し、命令口調で子供に話すのをやめ、子供を大人として尊敬してくれることを願っています。子どもにいつも「ダメ」と言わないでください。その代わりに、選択肢を与えて、自分で決めさせてあげましょう。子どもが十分に成長していて、自分の考えを表現することに問題がない場合は、子ども自身に解決策や代替案を考えさせることもできます。 5. 子どもたちに真実を話す 通常の訓戒に加えて、親は現実の状況における特定の原則を子供たちに教えるべきです。子どもに共感力を持たせ、他の人の視点から物事を経験させ、自分の行動が他の人にどのような影響を与えるかを真に理解させましょう。真実を説明する方法は、子どもの年齢に応じて説明の深さを選択できます。非常に小さな子どもには、物語を使うことができます。 |
推薦する
赤ちゃんがとても暑い場合はどうすればいいですか?
喉が痛くなるのはよくあることです。大人だけでなく、赤ちゃんも喉が痛くなることがあります。例えば、季節...
子どもが脳卒中を起こしたらどうすればいいでしょうか?
脳卒中は非常に一般的な現象です。高齢者に多いですが、子供にも起こることがあります。発症する可能性は比...
子供はなぜ寝ているときに汗をかくのでしょうか?
日常生活では、幼い子供が寝ているときに頭に汗をかくことがあります。このとき、親は過度の発汗によって子...
子供の外陰部の炎症を治療するには?
外陰炎は一般的な婦人科疾患です。外陰炎は成人女性に限ったものだと多くの人が信じていますが、実は赤ちゃ...
赤ちゃんの便が濃い緑色なのはなぜですか?
今日では、すべての子どもは家族の宝であり、子どもの健康は親にとって最も懸念される問題となっています。...
生後6か月半の赤ちゃんに与えられる補助食品にはどのようなものがありますか?
多くの母親にとって、赤ちゃんの健康は非常に心配なことです。赤ちゃんは生まれてからゆっくりと成長するた...
2歳の赤ちゃんにとって水泳にはどのようなメリットがありますか?
最近では、赤ちゃんが一人しかいない家庭も多く、親が子供を重視する傾向は前例のないほどです。子供が幼い...
赤ちゃんの手の皮が剥ける原因は何ですか?
赤ちゃんの中には体に問題を抱えている子もいます。そのため、健康を確保し、これらの問題によって引き起こ...
子どもの歯が生え変わるときに注意すべきことは何ですか?
子どもの歯は、通常6歳か7歳で生え変わります。この時期は乳歯が退化し始めるので、母親は子どもの歯磨き...
新生児用の哺乳瓶の選び方は?
新生児用品は特別な注意が必要で、品質と衛生が保証されなければなりません。新生児の体格はまだ比較的弱く...
赤ちゃんが1歳になっても安定して立つことができない場合はどうすればいいですか?
赤ちゃんは、話すべき時に話せない、歩ける時に歩けないなど、何らかの問題を抱えがちです。これらの問題に...
5歳児の正常な脈拍数はどれくらいですか?
親は子供の身体の健康、特に脈拍について非常に心配しています。子どもに不快感の症状があれば、脈拍も変化...
なぜ子どもの成長は遅いのでしょうか?
子どもの身体的健康と成長と発達は、親が最も心配する2つの問題です。特に子どもが思春期になると、多くの...
生後4ヶ月の女の子の身長と体重はどれくらいですか?
最近の子どもは成長がとても早いです。生まれたときの体重はわずか数キロですが、重い子でも7~8キロしか...
小児の誤嚥性肺炎の治療法は何ですか?
子どもは幼いときに注意しないと肺炎になる可能性が非常に高くなります。そのため、この時期、親は子供の日...