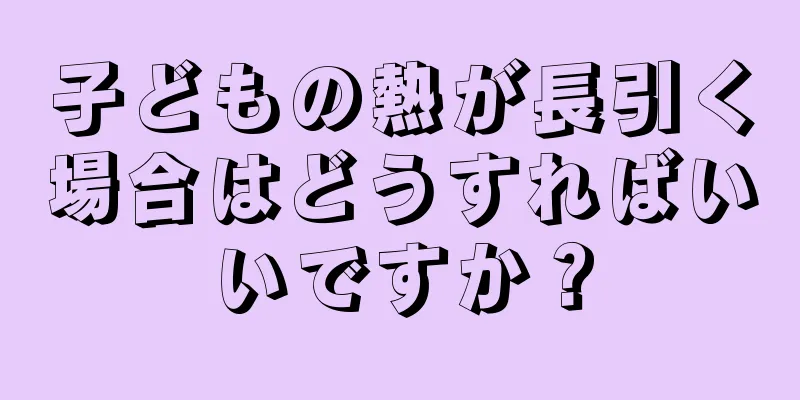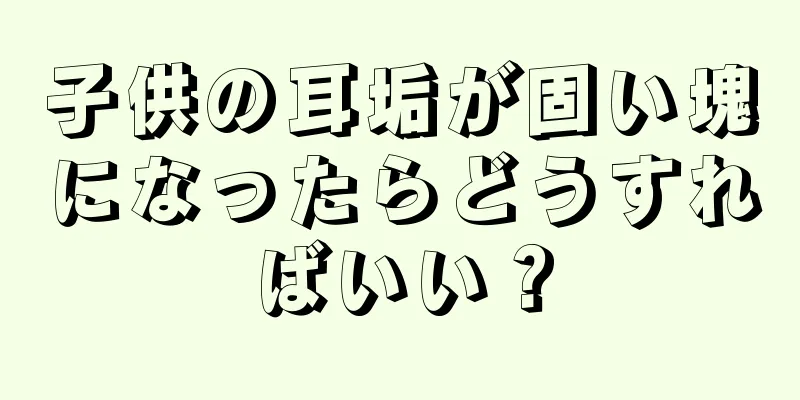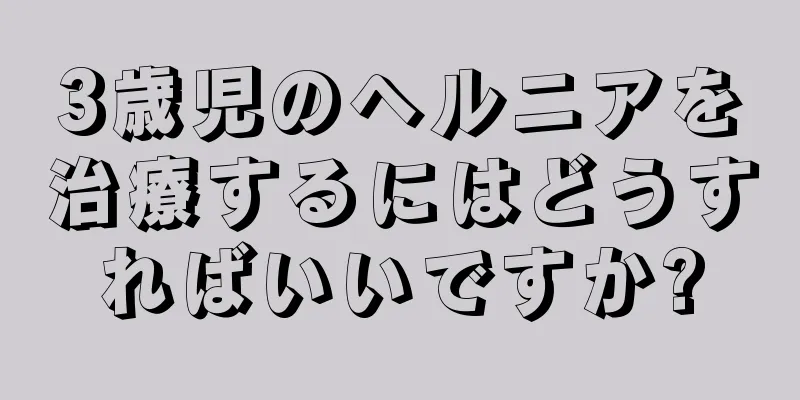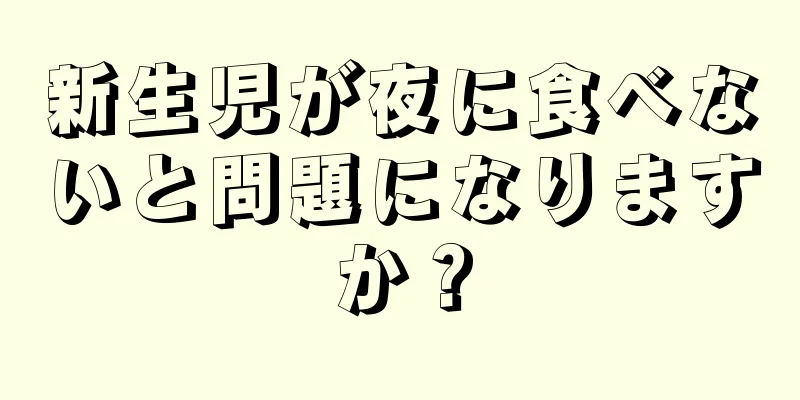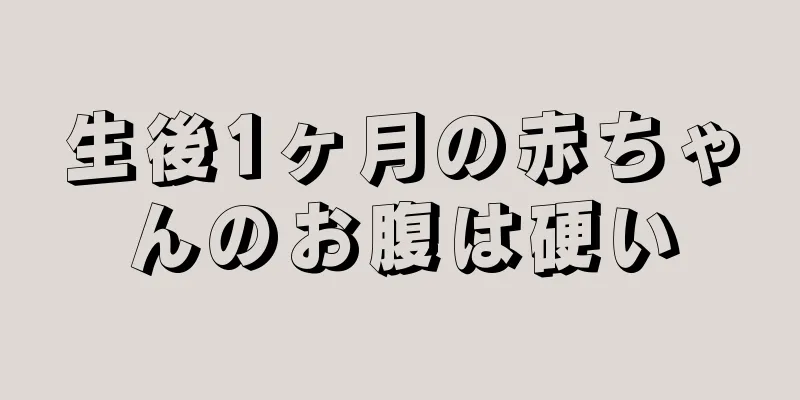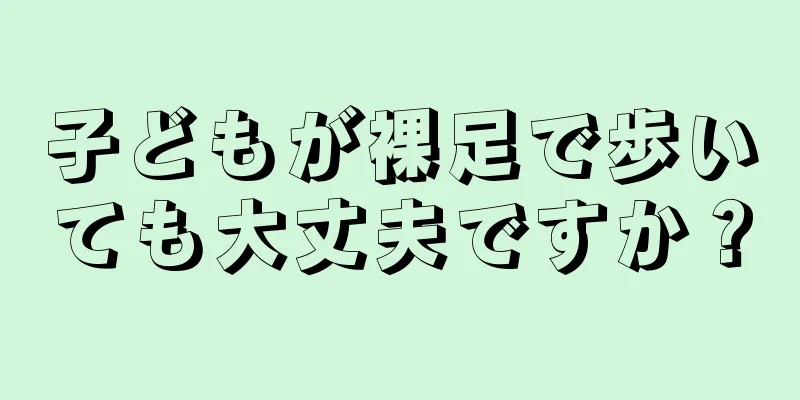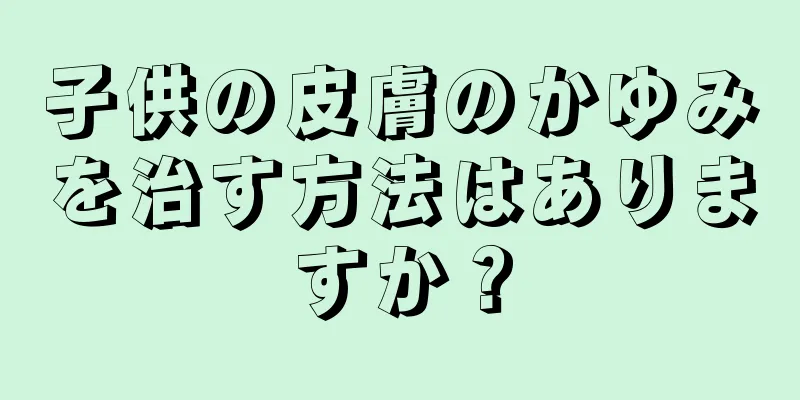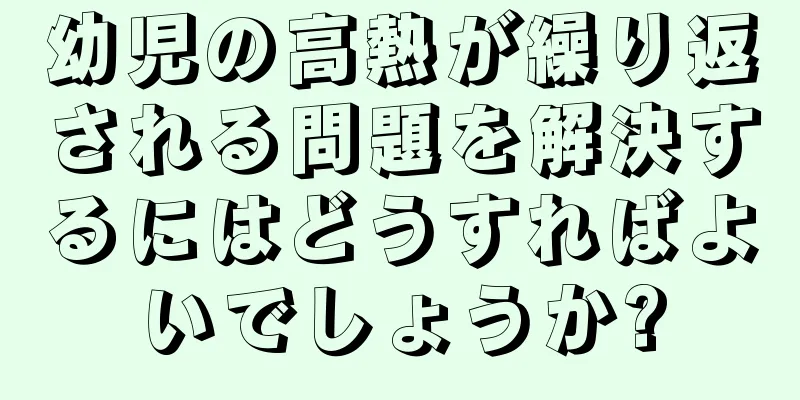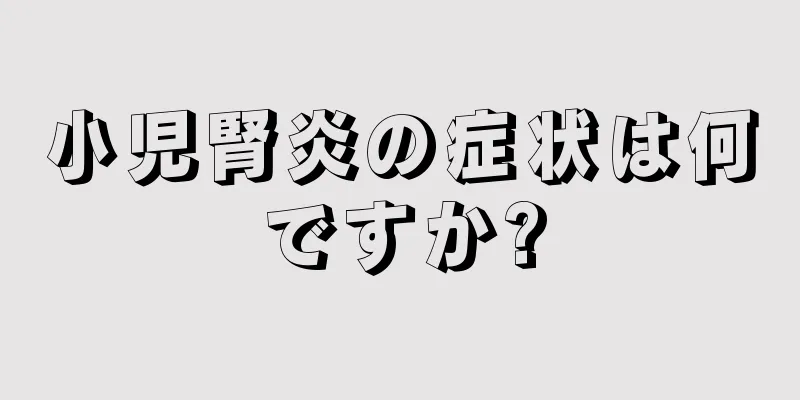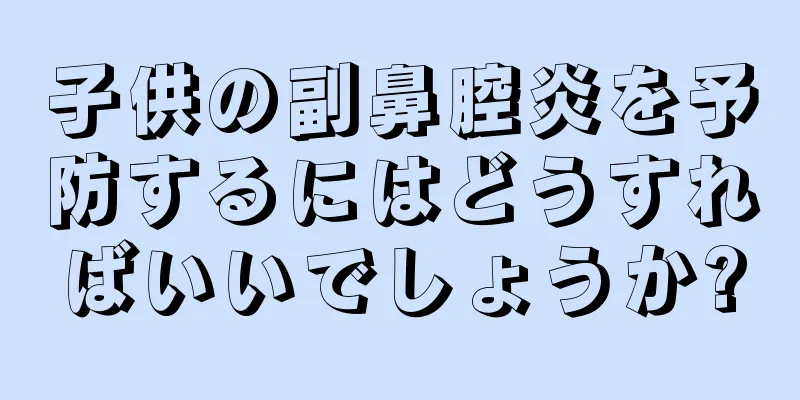子供の脳震盪の治療方法
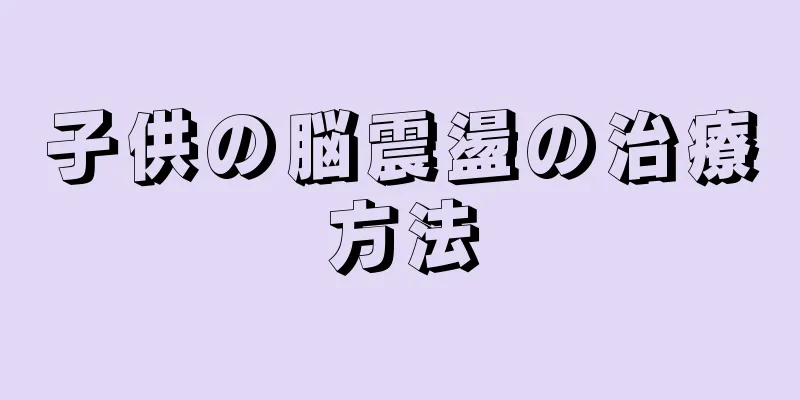
|
脳震盪は比較的よく見られる脳の病気です。脳が重傷を負うと、脳震盪が起こる可能性が高くなります。もちろん、子供の場合、脳震盪が起こった後は、タイムリーな治療を受けなければなりません。そうしないと、子供の脳と知的発達に大きな影響を与えることになります。では、子供の脳震盪はどのように治療すればよいのでしょうか?具体的な方法は以下で紹介します! 脳震盪とは何ですか? 脳震盪は頭部への外力によって引き起こされる一時的な神経機能障害で、通常は短時間の意識喪失と逆行性健忘として現れます。脳震盪患者の神経学的検査では、通常、局所的な兆候は見られず、頭部 CT や MRI などの通常の画像検査でも異常は見られません。 脳震盪の臨床的特徴は何ですか? 脳震盪の最も典型的な臨床的特徴は、軽度の意識障害であり、意識喪失や混乱として現れることがあります。意識障害は通常 30 分を超えません。 逆行性健忘は脳震盪の最も特異な症状です。つまり、負傷の前後に何が起こったのかを思い出すことはできませんが、過去の記憶は損なわれません。 脳震盪のその他の臨床症状には、頭痛、吐き気、嘔吐、めまい、かすみ目、羞明、疲労、平衡機能障害などの身体症状が含まれます。認知機能障害、情動障害、睡眠障害も起こる可能性があります。 脳震盪の診断方法 脳震盪は、頭部外傷後に一時的に意識を失い、臨床検査および画像検査が正常である場合に診断されます。脳震盪が疑われる患者を評価する最初のステップは、詳細な傷害歴を取得することです。受傷のメカニズム、意識喪失の有無、意識喪失の継続時間、嘔吐の有無など、受傷時の状況を含みます。次に、患者の症状を詳しく尋ねる必要があります。30 秒以上の意識喪失、重大な記憶喪失、または徐々に悪化する頭痛など、一部の症状は頭蓋骨のより深刻な脳損傷を示している可能性があります。これらの状態が存在する場合、画像検査が必要です。頭部外傷の急性期には、頭部 CT スキャンが第一選択であり、CT スキャンが陰性であれば MRI スキャンを選択できます。 脳震盪患者を効果的に治療する方法 脳震盪の早期治療の鍵は、症状が治まるまで十分に休息を取ることです。初期段階では、1~3週間ベッドで休んで、仕事、勉強、トレーニングをやめ、テレビを見たり、長時間読書をしたり、携帯電話で遊んだり、ゲームをしたりせず、十分な睡眠を確保し、栄養摂取を増やすことをお勧めします。外傷後に明らかな頭痛、吐き気、嘔吐がある患者には、対症療法を採用することができ、一部の神経栄養薬は脳機能の回復を促進することができます。脳震盪患者は、症状が完全に消えてから、徐々にトレーニング、仕事、勉強を再開することができます。 脳震盪患者のほとんどは、早期治療後、短期間で回復し、症状は完全に消えます。しかし、少数の患者では症状が持続し、持続性脳震盪または脳震盪後症候群と呼ばれます。 持続性脳震盪の治療は主に対症療法であり、患者の不安や緊張を取り除くために心理療法や理学療法が補助的に行われます。 |
推薦する
赤ちゃんはゴマペーストを食べても大丈夫ですか?正しい食べ方を学んでください
赤ちゃんが数か月になったら、補助食品を与え始めることができます。赤ちゃんが食べるべき補助食品には、非...
子供がオレンジを食べても大丈夫ですか?
オレンジは酸味と甘みがあり、新鮮でジューシーで、人々にとても人気があります。オレンジは水分含有量が非...
赤ちゃんの歯が生える時期が遅い理由は何ですか?
日常生活の中で、多くの母親が赤ちゃんの歯が生えるのを心配しています。では、赤ちゃんの歯はいつ生えてく...
子供の骨折は治るのにどれくらい時間がかかりますか?
人間の骨は、臨床的には亀裂骨折と呼ばれるより深刻な骨折を含め、さまざまな病気を発症する可能性がありま...
子供のマイコプラズマ肺炎はどのように治療するのですか?
一般的に、マイコプラズマ肺炎に感染すると、子供は大変なことになります。マイコプラズマ感染症は風邪より...
不均衡な食生活がもたらす5つの副作用
赤ちゃんは好き嫌いが激しく、食欲不振になることがよくあります。また、ほとんどの赤ちゃんは肉だけを好ん...
赤ちゃんの便が少なくなる理由
実際、日常生活では、赤ちゃんの抵抗力は比較的弱いので、衛生に注意する必要があります。そうしないと、細...
子供の鳩胸の場合、どの科に行くべきですか?
鳩胸は医学的な病気であり、鳩胸を持つ子供の多くは生まれつき鳩胸を持っています。この病気は、子供の体型...
子供の鼻肥大の症状は何ですか?
鼻甲介肥大は一般的な慢性鼻疾患であり、発症率の増加に伴い、この疾患は年少児にますます多く見られるよう...
子供のADHDの治療法は何ですか?
子どもの注意欠陥多動性障害(ADHD)は、重大な行動障害となっています。この症状が発生すると、子ども...
赤ちゃんは何ヶ月で座ることを覚えますか?
赤ちゃんの成長と発達の過程で、親は最初の1か月から細心の注意を払います。一般的に、赤ちゃんは生後6か...
お子さんが皮膚炎や湿疹にかかっている場合はどうすればいいでしょうか?
親にとって、子供の世話をするのはとても難しい仕事です。子供はとても繊細で、客観的な世界を正しく理解し...
お子様の口内炎が治らない場合の対処法
口腔内潰瘍はよくある古い問題ですが、大きな問題ではありません。口腔内潰瘍は自然に治ることもありますが...
子供のくる病の症状は何ですか?
子どもの成長は祖国の未来であり、家族の希望です。そのため、親は子どもが成長と発達の過程で遭遇する病気...
赤ちゃんが血を吐く理由は何でしょうか?
赤ちゃんがミルクを吐き出すことはよくあることですが、吐き出したミルクに血が混じっている場合は異常な現...