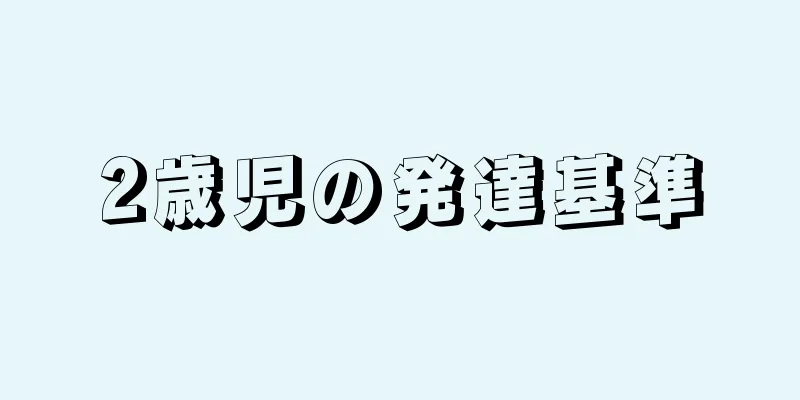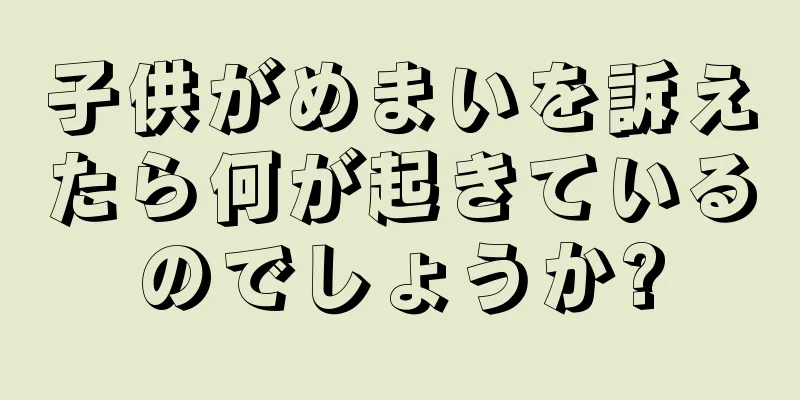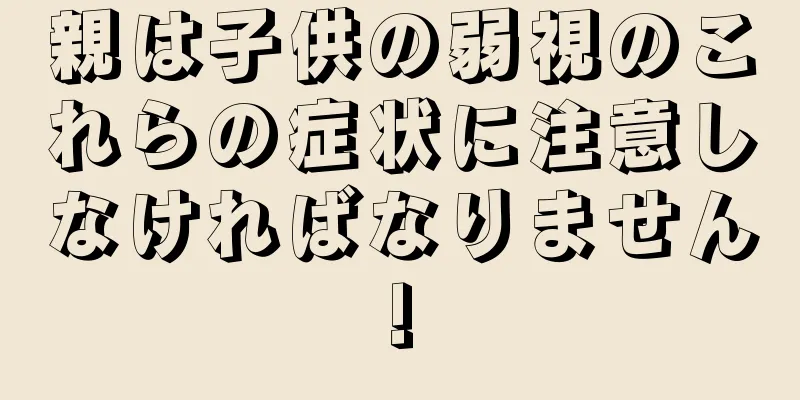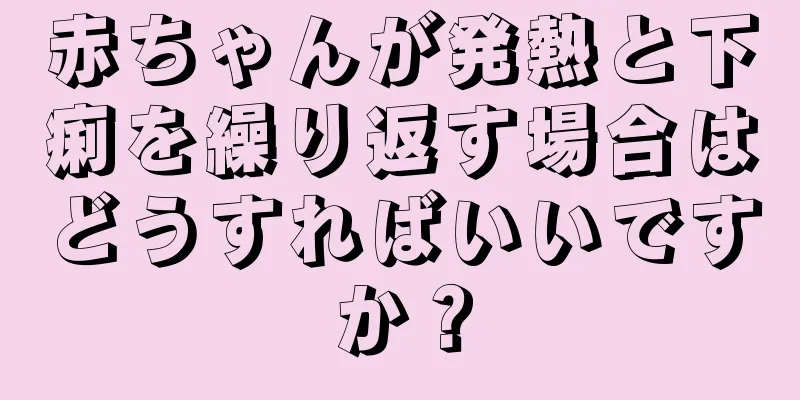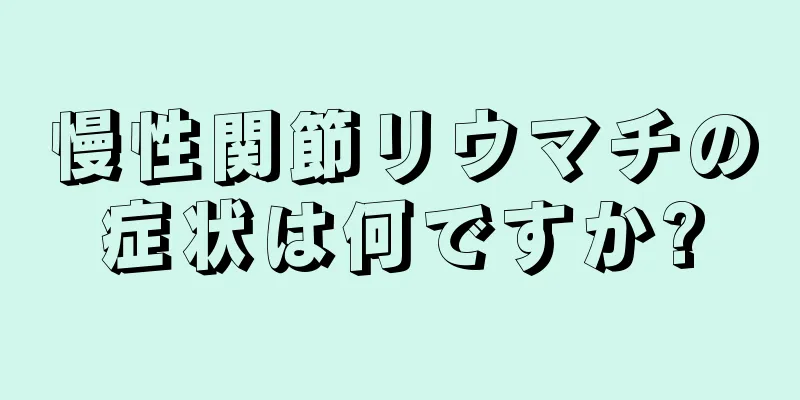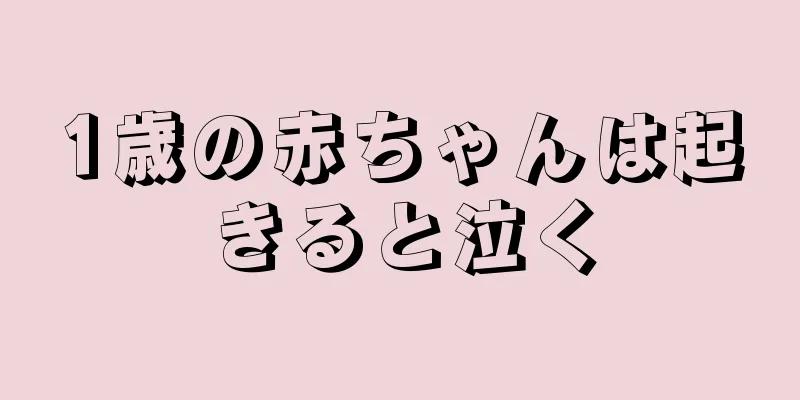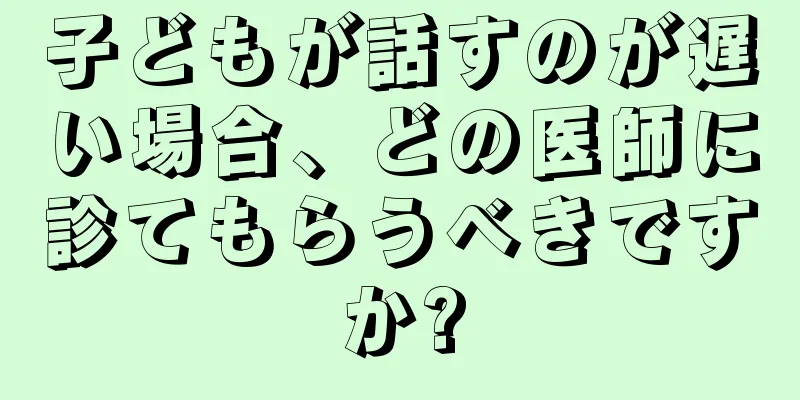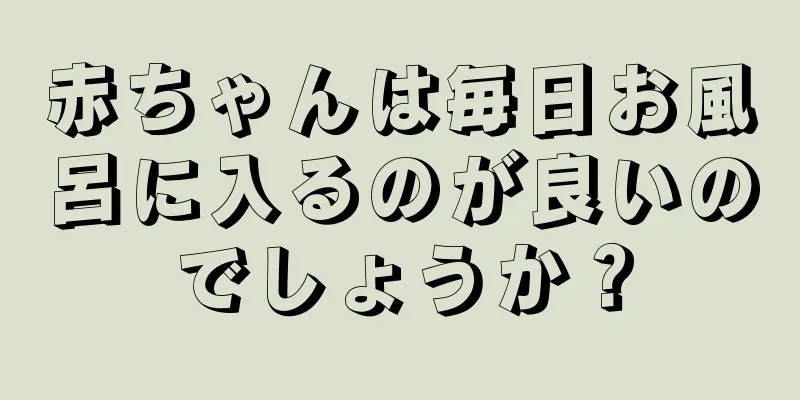子供の視力矯正の正しい方法は何ですか?
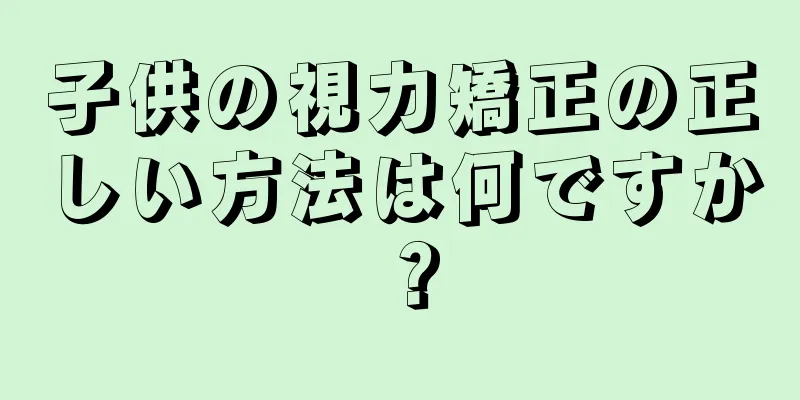
|
多くの人は、子供の視力は幼い頃は良好で、成人後に再び発達するので、幼い頃に電子製品を使用しても問題ないと考えています。しかし、現在、視力の問題を抱える子供が増えており、その多くは電子製品の長期にわたる誤用や目の過度の使用によるものです。子供の視力の問題は、時間内に修正する必要があります。そうしないと、発達の過程で、思春期に達すると、一生眼鏡や補助製品を着用しなければならなくなり、子供の外見に影響を与えます。専門的な視力矯正器具を使用するだけでなく、矯正眼鏡をかけ、カルシウムを豊富に含む食品を多く食べ、ビタミンや微量元素を補給することで、視力の回復を早め、予後を良好にすることができます。 子供の視力を矯正する方法 現在、屈折異常を矯正する方法は、フレーム眼鏡の着用、コンタクトレンズ、レーザー手術の 3 つが主に存在します。子供の場合、視力を矯正するためにフレーム付きの眼鏡をかけるのが最も安全です。 物理的な矯正方法に加えて、食事から目に有益な微量元素を補給することもできます。 1. カルシウムを含む食品:カルシウムが不足した食事は、幼児の神経筋の興奮性を高め、眼筋が極度に緊張した状態になり、時間が経つにつれて視力障害を引き起こしやすくなります。したがって、お子様にはカルシウムを含む食品をもっと与えてください。赤身の肉、牛乳、卵、豆、魚、エビ、昆布、野菜、オレンジなどは、比較的カルシウムが豊富です。 2. ビタミンAを含む食品:ビタミンAを含む食品は、結膜や角膜の乾燥や変性を防ぎ、「ドライアイ」を予防・治療することができます。ビタミン A は、暗い環境に適応する目の能力を高めることもできます。ビタミンAが豊富な食品には、豚レバー、鶏レバー、卵黄、牛乳、ニンジン、ほうれん草、ネギ、ピーマン、サツマイモ、オレンジ、アプリコット、柿などがあります。 3. ビタミンCを含む食品:ビタミンCは目の水晶体の成分の一つです。ビタミンCが不足すると水晶体が曇りやすくなり、白内障の原因になります。さまざまな野菜や果物など、ビタミン C を含む食品を子供にもっと与えましょう。ピーマン、キュウリ、カリフラワー、白菜、新鮮なナツメ、生の梨にはビタミン C が最も多く含まれています。 4. クロムを含む食品:人体内のクロム含有量が減少すると、インスリンの効果が著しく低下し、血漿の浸透圧が上昇し、水晶体と眼房の浸透圧が変化し、弱視や近視を引き起こします。人体に必要なクロムは、含有量が多い玄米、トウモロコシ、黒砂糖などの天然食品から摂取する必要があります。また、赤ちゃんが甘いものをたくさん食べると、水晶体と房水の浸透圧が変化することに注意してください。 5. アルカリ性食品:身体の疲労は、体内の酸性代謝産物のほとんどが人体の内部環境を酸性にすることで引き起こされますが、目の疲労も例外ではありません。アルカリ性の食品を多く摂取すると、体内の酸性環境が中和され、目の疲れが軽減されます。アルカリ性食品には、全粒米、リンゴ、柑橘類、昆布、豆やピーマンなどの生鮮食品が含まれます。 |
<<: 子どもはどうやって痰を減らすのでしょうか?この食事療法は薬よりも良い
推薦する
子供の咳や下痢の解決策は何ですか?
子供は咳の症状がよく見られます。これは抵抗力が非常に弱く、体の多くの医学的機能がまだ健全ではないため...
子供の虫垂炎を治療するには?
多くの子供は幼い時にいつも何らかの問題を抱えており、家族はいつも子供のことを特に心配しています。特に...
蚊に刺されたらどんな薬を使えばいいですか?
夏になると、蚊の数が急に増えます。蚊が人の血を吸うと、皮膚に赤いぶつぶつができ、ひどく痒くなります。...
1歳の赤ちゃんにはどんなミルクが適していますか?
赤ちゃんは生まれた後、母乳を飲む必要がありますが、母乳の出が悪いために赤ちゃんに粉ミルクを与える母親...
赤ちゃんの気管支炎の治療方法
気管支炎は誰もがよく知っている呼吸器疾患ですが、最近では環境問題により頻繁に発生しています。多くの子...
赤ちゃんの牛乳アレルギーのアレルゲンを確認する方法
出産後、赤ちゃんの体はまだ発育段階にあります。この期間中、赤ちゃんの体の抵抗力は比較的低いです。赤ち...
赤ちゃんが夜に咳をしたり嘔吐したりしたらどうすればいい?
現在、多くの親が、赤ちゃんの微熱や咳が一向に良くならず、症状が繰り返し再発し、非常に困惑していると報...
子どもが高熱を出しているときにエアコンをつけても大丈夫ですか?
子どもが熱を出しているときにエアコンをつけても問題ありませんが、エアコンをつけた後は部屋の空気が非常...
赤ちゃんは羊の脳を食べることができますか?保護者の皆様、ぜひご覧ください。
ご存知のとおり、羊の脳は栄養価の高い食品です。多くの人が好んで食べ、味もとても美味しいです。しかし、...
子どもはいつも便秘なので、親はこうするべきです
便秘は、胃腸の運動が遅い、水分の吸収が低い、脂肪分が多い、胃腸管が脂っこい、定期的な腸洗浄が行われな...
赤ちゃんが咳をしているときにビワの葉水を飲ませるにはどうすればいいですか?
赤ちゃんの健康は、親にとって非常に心配なことです。赤ちゃんは人生で多くの病気に遭遇し、体の健康に大き...
生後2ヶ月の赤ちゃんの疝痛の症状
疝痛の問題は大人だけが抱えていると考える人が多いですが、実は生後2か月の赤ちゃんも疝痛を経験すること...
赤ちゃんはなぜいつもおならをするのでしょうか?
おならは、主に胃や腸に関係する、ごく普通の行動であることは誰もが知っています。しかし、頻繁にオナラを...
子どもが熱を出したらどうするか
子どもは抵抗力が弱いため、外部環境にまだ適応しておらず、身体が十分なストレスに耐えることができません...
生後8ヶ月の赤ちゃんの口臭の原因は何ですか?
口臭は大人になってからしか発生しないものだと誰もが思っているかもしれません。実はそうではありません。...