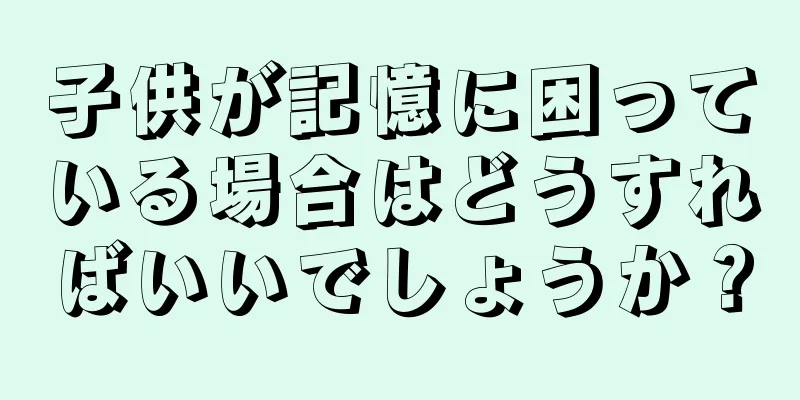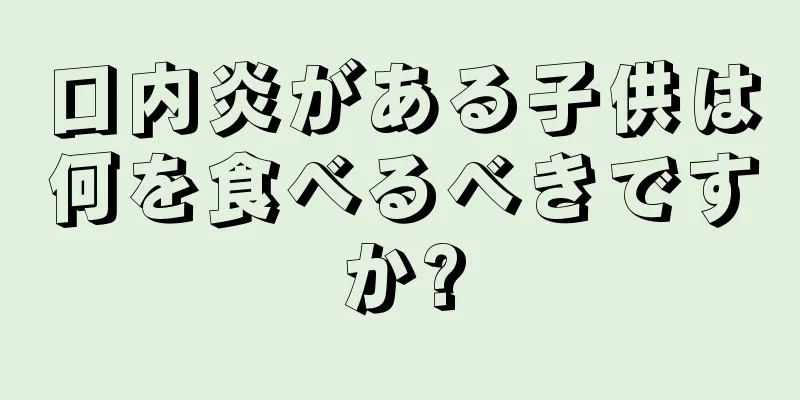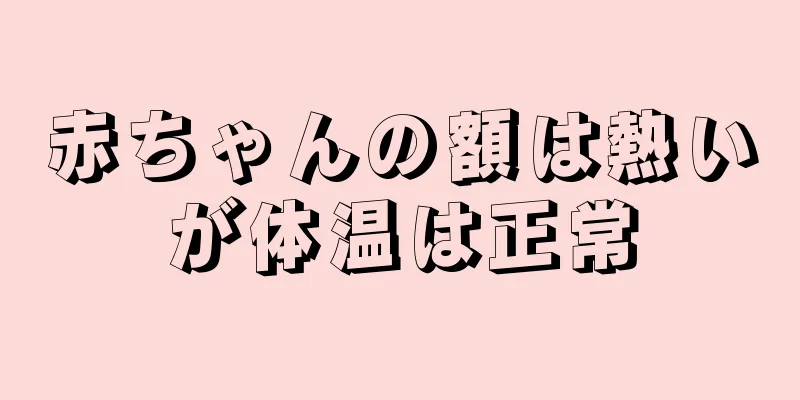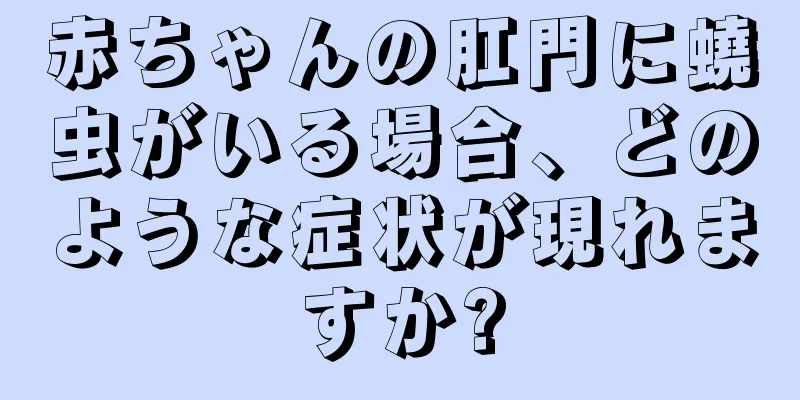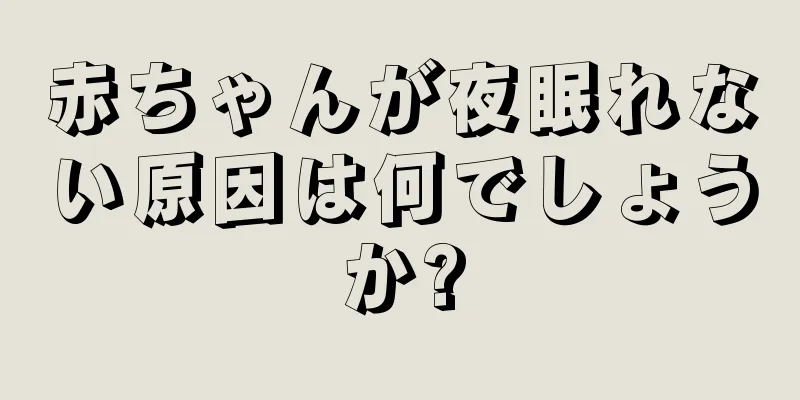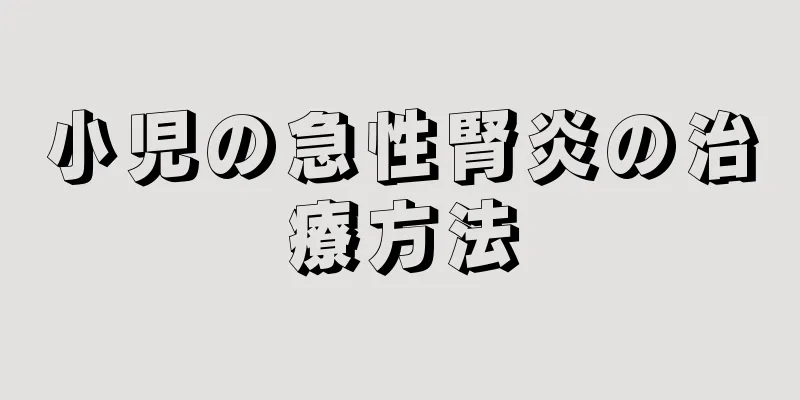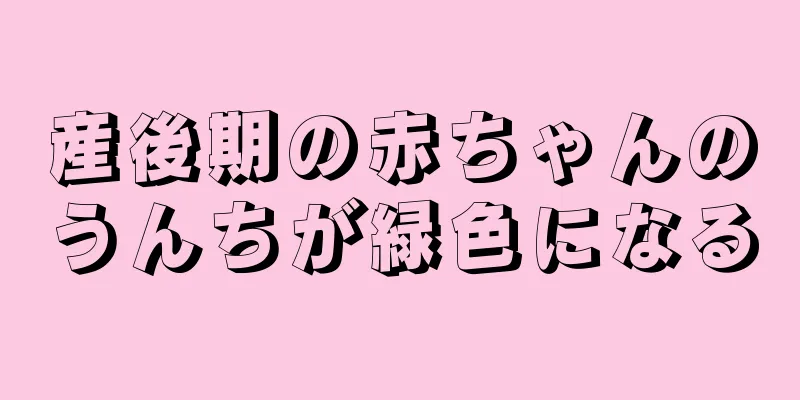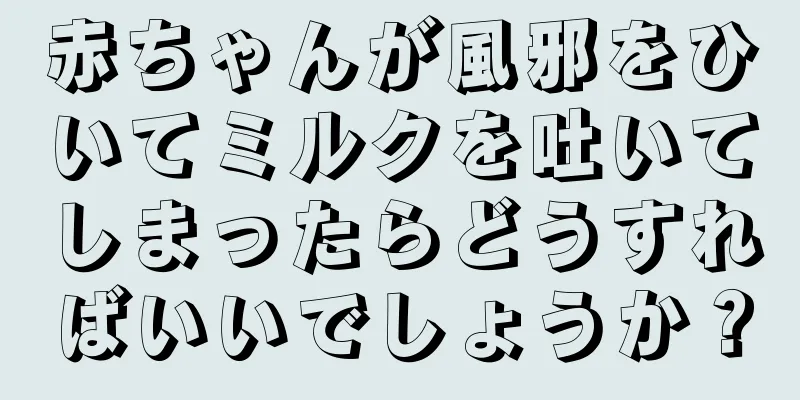新生児が消化不良を起こした場合はどうすればいいですか?
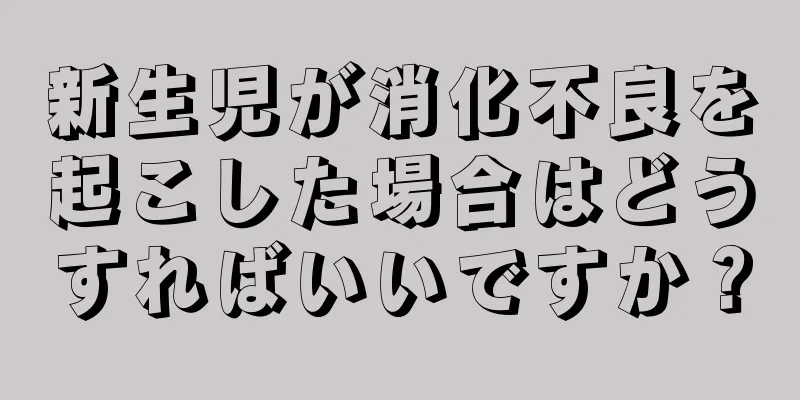
|
新生児の消化不良は、赤ちゃんの身体の発育に大きな支障をきたし、多くの母親を特に心配させます。そのため、赤ちゃんの消化不良の治療法について、誰もがある程度理解しておくことをお勧めします。赤ちゃんの消化不良に遭遇したときは、砂糖と塩の入った水を使用するか、母親が低脂肪食品を食べて赤ちゃんの消化を促進することをお勧めします。 自家製の砂糖と塩水を使用して水分補給します。つまり、5000 ml の温かい沸騰水に 1.75 グラムの精製塩と 10 グラムの白砂糖を加えます。1.75 グラムの精製塩はビール瓶のキャップの半分に相当し、10 グラムの白砂糖は小さじ 2 杯に相当します。自家製の米スープと塩水を使用して水分補給します。つまり、500 ml の温かい沸騰水に 1.75 グラムの精製塩を加えます。水分補給には医師が処方した ORS (経口補水塩) を使用します。ORS 補水塩は調製された乾燥粉末で、使用時に指示に従って液体に混ぜるだけです。 その後、最初の 4 時間は赤ちゃんの体重 1 kg あたり 20 ~ 40 ml の水分を与えます。その後はいつでも経口摂取し、飲めるだけ飲んでください。 2 歳未満の赤ちゃんには、1 ~ 2 分ごとに小さなスプーン 1 杯ずつ飲ませることができますが、それ以上の年齢の赤ちゃんは小さなコップで飲むことができます。赤ちゃんが嘔吐した場合は、10分ほど待ってから、ゆっくりと授乳を再開してください。赤ちゃんのまぶたが腫れてきたら、水分が過剰に補給されたことを示しているので、一時的に沸騰したお湯か母乳に切り替える必要があります。 ご注意:ORS 補水塩を牛乳、ライススープ、ジュース、その他の飲み物に加えないでください。また、指示に従って調理した後は砂糖を加えないでください。そうしないと、補水効果に影響します。 下痢の伝統的な治療法では、子供が一定期間断食することを推奨しています。しかし、これは身体の栄養補給を妨げ、簡単に栄養失調につながる可能性があります。現在では、下痢をしている赤ちゃんには絶食はせず、少量ずつ頻繁に食事をとるという原則に従い、1日に少なくとも6回は食事をとることが推奨されています。母乳で育てられた赤ちゃんは母乳を飲み続けますが、母親の食事は脂肪分を控えるべきです。そうでないと下痢が悪化します。6 か月以内に哺乳瓶で育てられた赤ちゃんは、通常の量のミルクを飲むことができます。離乳食を始めている 6 か月以上の赤ちゃんは、下痢が止まってから 2 週間まで、お粥、ソフト麺、魚のミンチ、少量の野菜ピューレ、新鮮なフルーツジュース、バナナピューレなど、消化しやすい食品を食べることができます。 新生児の生活における消化不良の治療法を皆様によりよく理解していただくために、この記事で紹介した内容を正しく活用していただくよう提案いたします。ブランド母乳育児法を通じて赤ちゃんの消化不良を治療し、母乳の成分を改善して赤ちゃんの消化能力を高めることができます。 |
>>: 1歳の赤ちゃんが細菌感染により発熱を繰り返した場合の対処法
推薦する
子供の尿に泡が出る原因は何ですか?
子どもの中には尿に問題を抱えている子もいるので、身体の健康と安全を確保し、子どもの健康に影響を与える...
小児におけるクラミジア感染症の症状
小児のクラミジア感染症の主な症状はクラミジア肺炎です。小児がこの病気を発症した場合、母親から直接感染...
食べるのを嫌がる13ヶ月の赤ちゃんへの治療法
家族全員が赤ちゃんをとても愛しています。赤ちゃんが生まれると、家中が賑やかになり、いたるところに子供...
赤ちゃんが普通に話せるようになるには何ヶ月かかりますか?
赤ちゃんが話せるようになるのは何ヶ月が普通でしょうか? 親は皆、赤ちゃんがもっと早く話せるようになっ...
子供の腰椎椎間板ヘルニアと脚の痛み
腰椎椎間板ヘルニアは非常に一般的な病気で、主に20歳から50歳の人に発生します。発生率は女性よりも男...
生後6ヶ月の赤ちゃんの発熱の治療
人生には多くの緊急事態が起こりますが、赤ちゃんは家族の重要な一員です。生後6か月の赤ちゃんが熱を出す...
新生児が食後にうんちをするのは普通ですか?
新生児の身体の発達は比較的速く、子供の代謝も比較的速いため、子供は1日に何度も食事し、何度も排便しま...
転んだ子どもへの対処法
子どもの皮膚は非常にデリケートなので、転んだときに膝を怪我してしまうことがあります。膝の周りにはたく...
子供が吃音になったらどうするか
吃音は、一部の子供が成長段階で経験する症状であり、多くの親が非常に心配する問題でもあります。これは、...
子供は炭酸飲料を飲んでも大丈夫ですか?
子どもたちは色鮮やかでおいしい食べ物にとても興味があり、炭酸飲料は上記の特徴を満たしているため、多く...
新生児の顔に赤い斑点がある場合はどうすればよいですか?
新生児の顔に赤い斑点が現れる理由は何ですか? 赤ちゃんの皮膚は非常に柔らかく、赤い斑点が現れる原因は...
子供はコーヒーを飲んでもよいか?母親が知っておくべきこと
多くの子供は、大人がコーヒーを飲んでいるのを見ると、自分も飲みたくなります。このとき、多くの親も子供...
新生児の黄疸を軽減する方法
新生児が黄疸を呈することは非常に一般的ですが、必ずしも病的というわけではありません。すべての新生児は...
子供が腹筋運動をしても大丈夫でしょうか?
子どもは身体の発達段階にあります。適切な運動は身体の発達、特に骨の成長を促進するのに役立つので、子ど...
子供のIQを決めるのは誰ですか?
私たちは皆、かわいい子供を産みたいと願っています。人間の遺伝子の特性によると、男性も女性も、より賢い...