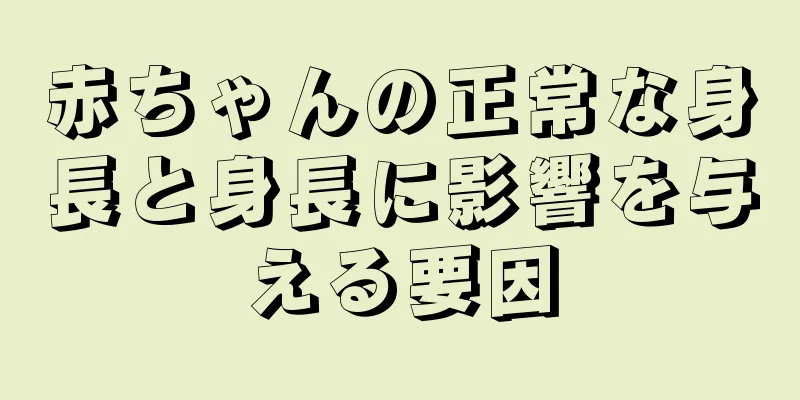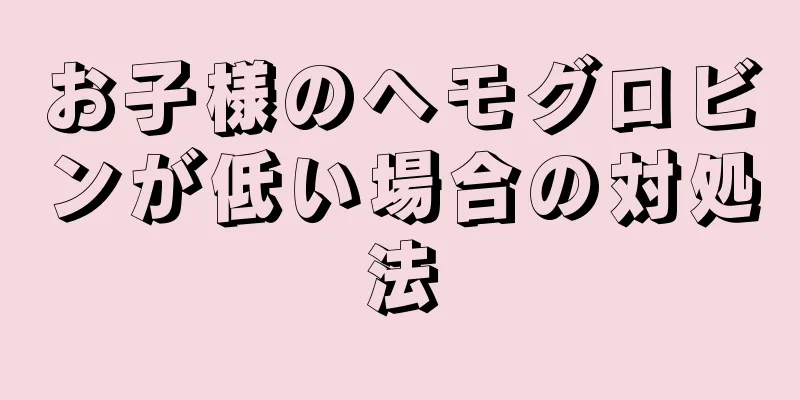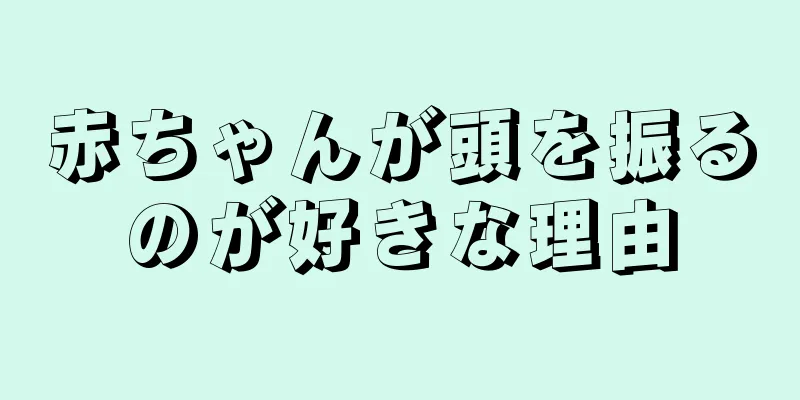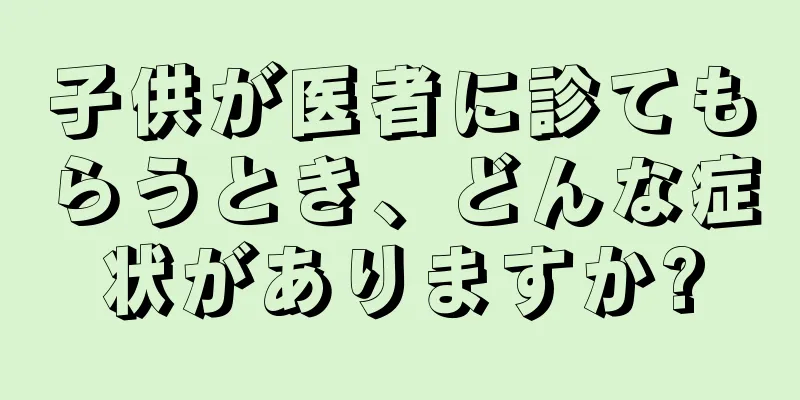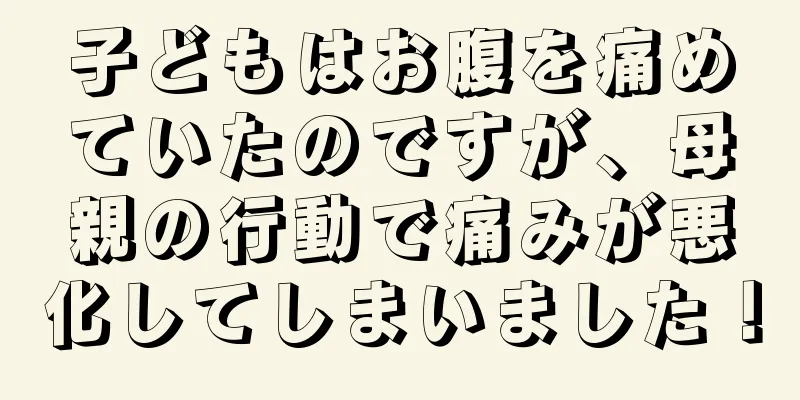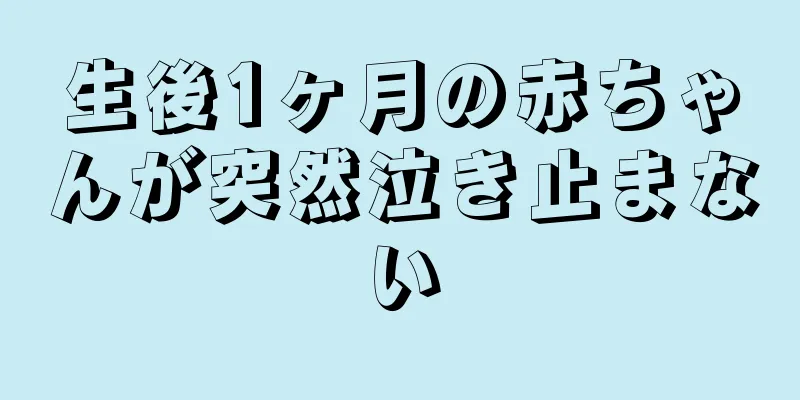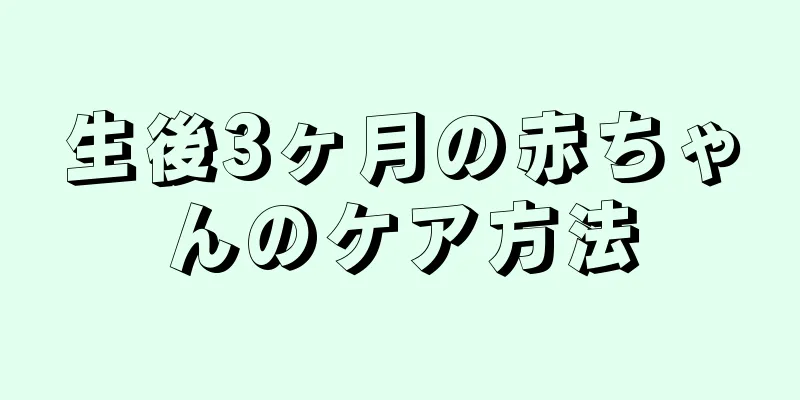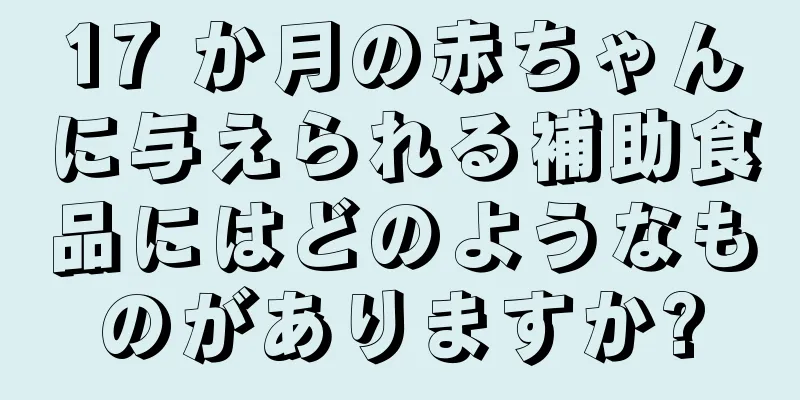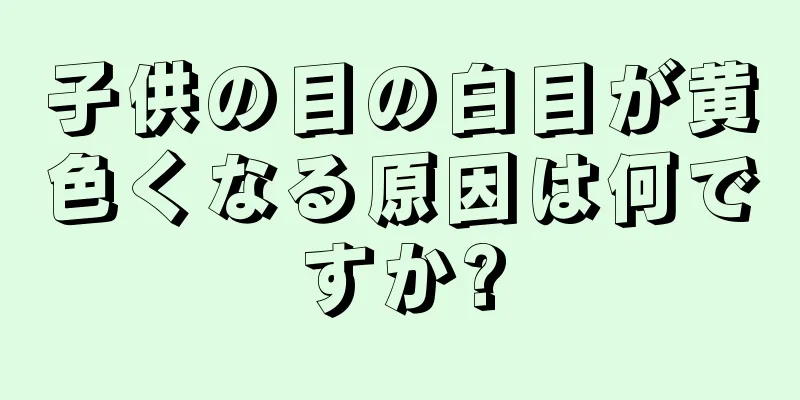赤ちゃんの亜鉛欠乏症を補うにはどうすればいいですか?
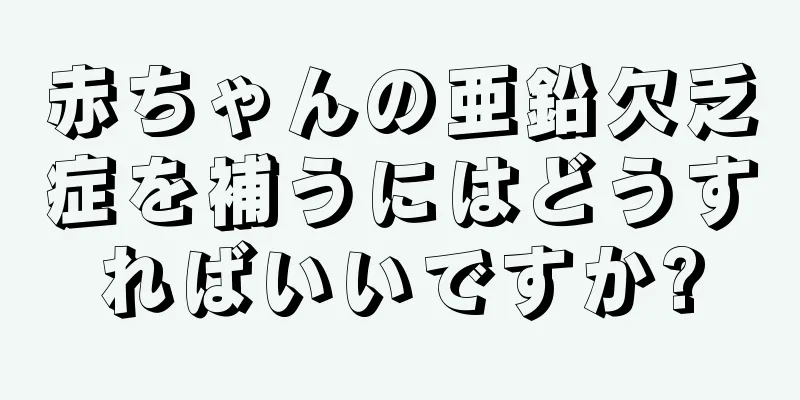
|
私の子供は3歳で、幼稚園に通っています。最近、幼稚園の先生から、子供が食事が嫌いで、椅子にじっと座っていられず、授業に集中できず、クラスメイトとよく喧嘩していると報告がありました。病院で検査を受けたところ、医師はこれが亜鉛欠乏症の兆候だと言いました。では、赤ちゃんの亜鉛欠乏症をどうやって補えばいいのでしょうか?親として、この問題には注意しなければなりません。なぜなら、子どもは成長段階にあるからです。体内に亜鉛が不足すると、子どもは活発になり、成長が遅れることが多いのです。したがって、お子様に不足している微量元素を確認した後、健やかな成長に影響を与えないように補給する必要があります。 赤ちゃんの亜鉛欠乏症を補うにはどうすればいいですか? 注意: 食品を過度に加工すると亜鉛が破壊されます。そのため、亜鉛の損失を減らすには、食品を調理する際の熱を制御する必要があります。 食品中の鉄、カルシウム、リン、銅などの含有量が多すぎると、亜鉛の吸収率と利用率が低下します。日常の食生活では食品の多様性を確保し、バランスの取れた食生活を実現するよう努めるべきです。 薬物補充:医師の指導の下で行う必要があります 亜鉛の吸収に影響を与える要因は数多くあり、特に拒食症の子供の場合、悪循環に陥り、食物から必要な亜鉛を摂取することが困難になるため、薬で補給する必要があります。現在、亜鉛製剤としては硫酸亜鉛、グルコン酸亜鉛、甘草亜鉛、酵母亜鉛などがあります。 注意: 亜鉛の有効摂取量は毒性摂取量に非常に近いので注意してください。不適切な使用は過剰摂取につながりやすく、鉄欠乏症、銅欠乏症、貧血などの一連の疾患を引き起こす可能性があります。 亜鉛を多く含む食品:赤身の牛肉、豚肉、羊肉、鶏の心臓、魚、カキ、卵黄、脱脂粉乳、小麦胚芽、ゴマ、クルミ、カキ、豆、ピーナッツ、キビ、大根 赤ちゃんが毎日摂取する必要がある亜鉛の量: 6 か月未満の子供の場合 1 日 3 mg、6 か月から 12 か月の子供の場合 1 日 5 mg、1 歳から 13 歳の子供の場合 1 日 10 mg、13 歳以上の子供の場合 1 日 15 mg 子供が通常の食事を摂り、病気でなければ、食事から摂取する毎日の亜鉛は基本的にこの基準を満たすことができます。 亜鉛は微量元素なので、補給は適度に行う必要があります。過剰に摂取すると中毒、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などの胃腸症状を引き起こす可能性があります。また、発熱、貧血、成長遅延、関節出血、骨の分解、腎不全、心血管疾患や脳血管疾患などを引き起こす可能性があります。 まとめると、これは赤ちゃんの亜鉛と鉄の欠乏を補う方法についてです。親や友人が心配していた重要な問題が解決されました。そして、お子様の具体的な状況に応じて微量元素を補給する必要があります。特に、多くのお子様が不足しやすい亜鉛を補給する必要があります。そのため、食事によるサプリメントと薬物によるサプリメントの両方が非常に重要であり、お子様に合った方法を選択できます。 |
推薦する
赤ちゃんが10日間下痢をしていて、まだ良くならない場合はどうすればいいですか?
赤ちゃんにとって、生まれてから大人になるまでの毎日はとても大変なことであり、母親は赤ちゃんが健康に育...
2歳の赤ちゃんはロバの皮のゼラチンケーキを食べても大丈夫ですか?
ロバ皮ゼラチンは血液と気を補う食品です。貧血に悩む女性の多くは、ロバ皮ゼラチンを使って体調を整えてい...
赤ちゃんの下痢豆腐カス状態
赤ちゃんがいる家庭の親は注意が必要です。赤ちゃんの便の形、色、匂いで、子供が胃腸疾患にかかっているか...
子供の皮膚のかゆみを和らげる方法
バス:水温は適度で熱すぎず、皮膚の末梢神経を麻痺させて皮膚のかゆみを和らげるようにしてください。 ...
赤ちゃんが牛乳アレルギーの場合の対処法
牛乳には動物性タンパク質が豊富に含まれています。毎朝牛乳を一杯飲むと、人体に必要なタンパク質を毎日補...
なぜ子供は夜中に泣くのでしょうか?
子どもが健康に成長するには十分な睡眠が必要です。しかし、多くの親は夜中に子どもが泣くという現象に遭遇...
痰のない乾いた咳に子供が服用すべき薬は何ですか?専門家に教えてもらいましょう!
子どもはよく咳をしますが、これは親にとっては非常に心配なことです。主な理由は、子どもの呼吸器系がまだ...
女の子の早期発達の症状は何ですか?
女の子が思春期に達すると、性的欲求が発達し始め、多くの明らかな女性的特徴が現れます。最も明らかな兆候...
なぜ子供のうんちに血が混じっているのでしょうか?
実は、親は排便時の姿勢を観察することで、子どもの健康状態を把握することができます。子どもの便に血が混...
赤ちゃんの発達遅延の7つの症状に注意し、早期発見しましょう
赤ちゃんが生まれた後、親が最も心配するのは、赤ちゃんの発育が正常かどうかです。以下は、さまざまな年齢...
子どもは寝ているときに鼻づまりや呼吸困難に悩まされる
子どもが幼いときは、母親は子どもが自分の目から離れたところで何か問題が起きるのではないかと心配し、常...
しばらくすると子供の胸の痛みは治まります。
胸部は心臓が位置する場所です。この部分に痛みが生じると、非常に深刻な結果を招く可能性があります。子供...
日焼けした子供の肌を早く白くするにはどうすればいいですか?
夏はいつも走り回っているので、強い紫外線で子供たちが日焼けしてしまうのではないかと心配する家庭は多い...
赤ちゃんにBCG膿瘍ができた場合はどうすればいいですか?
赤ちゃんの中には病気を予防するためにBCGワクチンを注射しなければならない子もいますが、BCGワクチ...
ダニ刺されの対処法
ダニは人々の生活のいたるところに存在します。ダニは肉眼では見えないほど小さな寄生虫ですが、人々が日常...