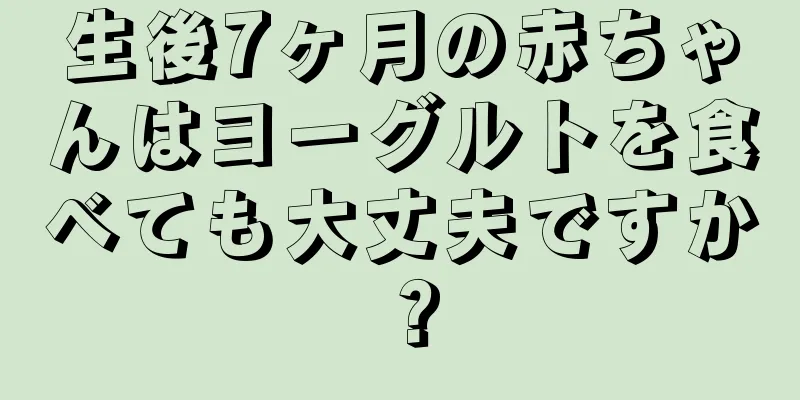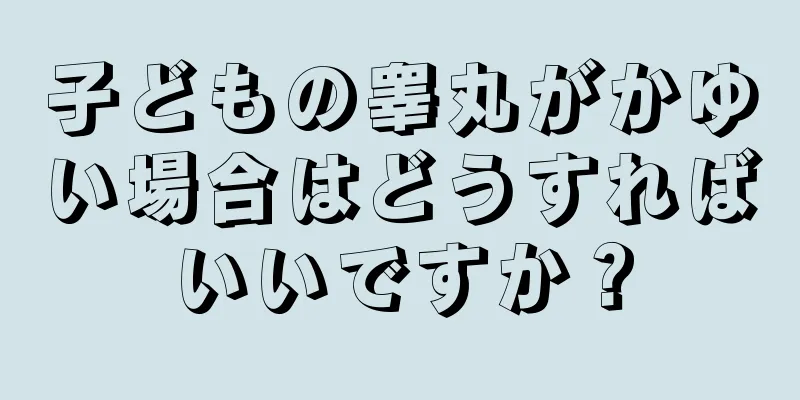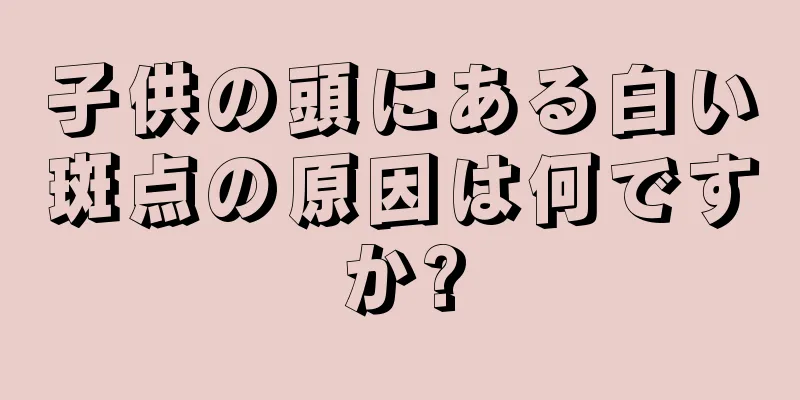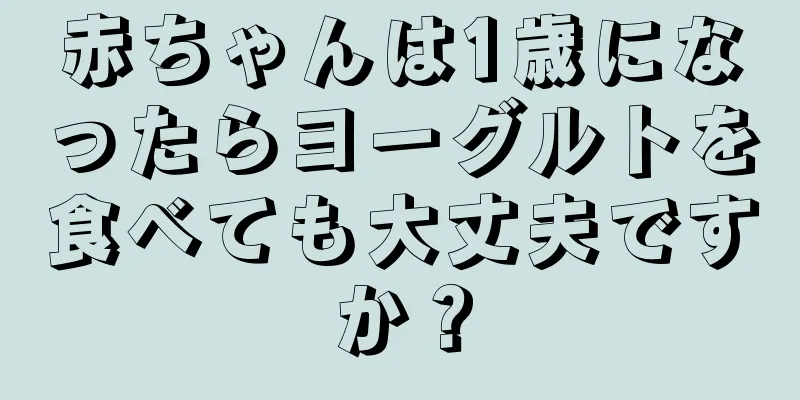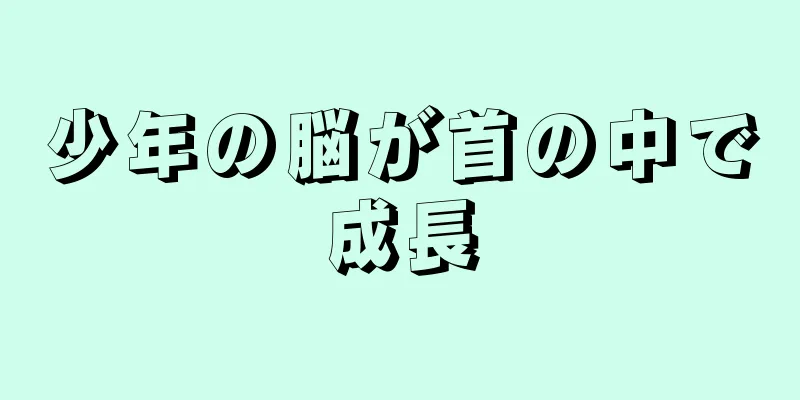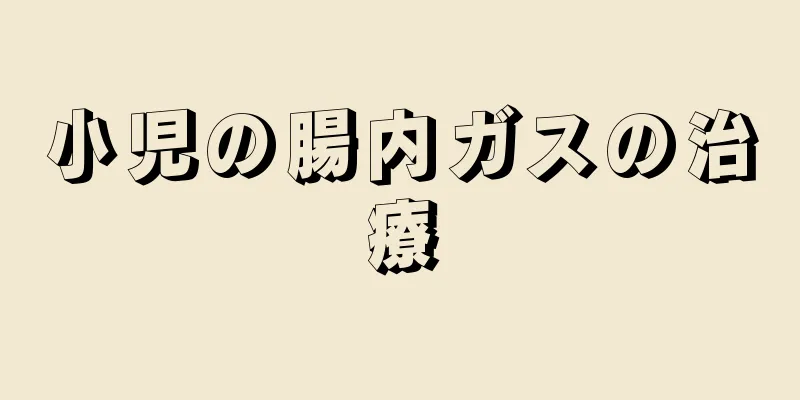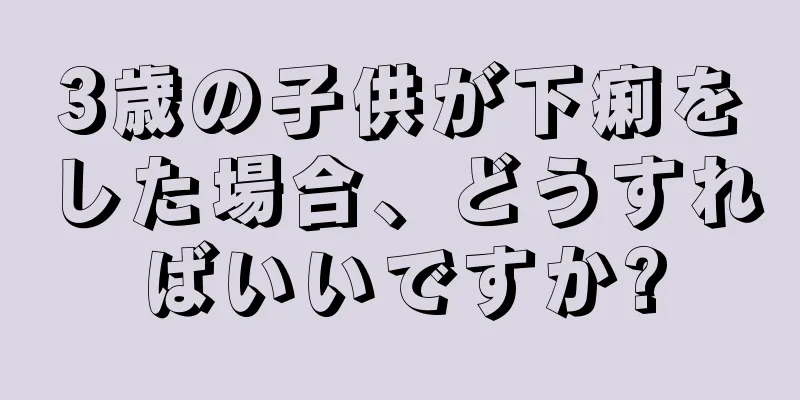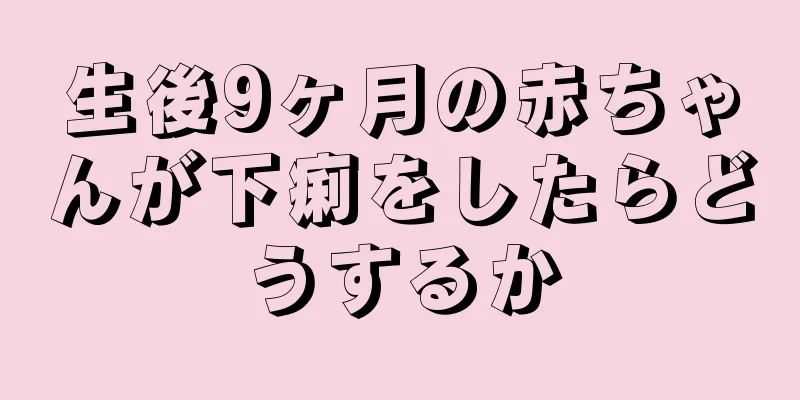新生児がいびきをかくのは普通ですか?
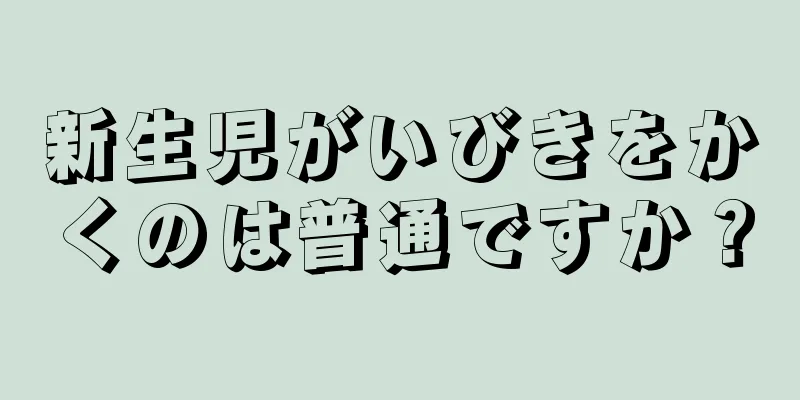
|
いびきには、いびきをかくという別名があります。普通の人は、肉体的にも精神的にも疲れて眠っているときにいびきをかきます。しかし、生まれたばかりの赤ちゃんがいびきをかくのは正常なのでしょうか?この状況を見てみましょう。 いびきは、いびきとも呼ばれます。通常、幼い子供は寝ている間に軽いいびきをかくことがよくあります。しかし、継続的に大きないびきをかいている場合は異常であり、医学的な病状とみなす必要があります。最も一般的な病状は脳梁肥大です。 アデノイドは、アデノイドとも呼ばれ、鼻腔の後ろにある鼻咽頭の後壁に位置する大きなリンパ組織です。増殖体は幼児期に急速に発達し、3歳から6歳の間に最も活発に成長し、思春期に徐々に縮小します。したがって、増殖小体の肥大は幼児期に特有の病変です。通常の大きさの増殖体は子供に影響はありませんが、増殖体が大きすぎると子供の心身の健康に影響を及ぼします。 気温の変化、栄養失調、抵抗力の低下、風邪、扁桃炎、鼻炎、副鼻腔炎などが増殖体の肥大につながることがあります。鼻顆が大きくなりすぎて後鼻孔を塞いでしまうため、鼻水が排出されにくくなるだけでなく、鼻腔への空気の出入りも妨げられます。子供が眠った後、気管から吐き出されたガスは口から吐き出されてしまいます。睡眠中は全身の筋肉が弛緩するため、舌も弛緩して咽頭に落ち込み、咽頭が狭くなり閉塞感が生じます。このとき、ガスは舌根と舌懸垂組織に時々衝撃を与え、呼吸とともに夜間の音が爆発的に発生します。幼児がいびきをかいたり、息を止めたり、口呼吸を長時間続けたりすると、身体や脳の発達に影響を及ぼし、知能が低下し、反応が鈍くなり、表情が鈍くなり、鼻唇溝が消え、上唇が厚くなって反り返り、上切歯が突き出て露出し、下顎が垂れ下がり、硬口蓋が高くアーチ状になり、特殊な「増殖顔」を形成するなど、外見が悪化します。耳管軟骨の肥大により耳管軟骨の動きが妨げられ、中耳滲出液が溜まりやすくなり、中耳炎や伝音難聴の原因となります。幼児は口を開けて呼吸することが多く、睡眠中に不快な状態になります。夜間は十分な休息が取れず、日中は機嫌が悪く、食欲がなくなり、食事から十分なカロリーを摂取できません。また、成長と発達が遅れ、身長と体重が同年齢の通常の子供よりも低く、体の抵抗力が低下する可能性があります。そのため、これらの子供は呼吸器感染症にかかりやすいだけでなく、鳩胸、漏斗胸、さらには肺性心にもかかりやすいのです。もちろん、幼い子供のいびきは、咽頭の扁桃腺が肥大して咽頭腔が部分的に閉塞することによっても引き起こされる可能性があります。 以上が新生児のいびきについての説明です。新生児のいびきには通常、何らかの理由があり、一定の科学的根拠があります。お子さんがいびきをかく場合、上気道に何らかの閉塞があり、それがいびきの原因となっているため、病的なものである可能性が高いです。まずは病院に行って検査を受け、それから合理的な解決策を探してください。 |
<<: 新生児肺炎の治療にはどれくらいの時間がかかりますか?
推薦する
肝火の子供に良い食べ物は何ですか?
子どもの肝火が過剰である場合、親は科学的な食事療法と養生法に注意を払う必要があります。例えば、蓮の実...
目の健康でない子供は何を食べるべきでしょうか?
子どもはまだ成長発達期にあり、目のあらゆる面がまだ完全には発達していません。親は子どもに目の衛生に注...
子供の消化不良と発熱の症状は何ですか?
ご存知のとおり、子供は祖国の花です。多くの親は子供の体調を非常に心配しています。子供が熱を出すのは普...
子供の扁桃炎に最適な治療法は何ですか?
扁桃炎は一般的な病気であり、子供の間で最も一般的な病気の 1 つです。子供が扁桃炎にかかっても、適切...
DPTを服用した後に腕が赤く腫れた場合の対処法
赤ちゃんが成長するにつれて、いくつかの病気の発生を防ぐためにさまざまな予防接種を受ける必要があり、そ...
新生児の心筋酵素の正常値
今日では、子どもは皆家族の宝であり、特に子どもの健康問題は親たちから大きな注目を集めています。しかし...
子供が急性胃腸炎になった場合の対処法
多くの親は、子供が急性胃腸炎にかかっている状況に遭遇したことがあります。一般的に言えば、子供が何度も...
2歳児を幼稚園に通わせることのメリットとデメリット
2歳児を幼稚園に通わせることのメリットとデメリット子供が2歳になると、両親が仕事で忙しい場合は、赤ち...
赤ちゃんのお尻に赤い斑点がある場合はどうすればよいですか?
赤ちゃんのお尻に赤い斑点ができました。このような症状を経験したことがある赤ちゃんは多いのではないでし...
生後42日の赤ちゃんの発達指標は何ですか?
赤ちゃんの発達は、すべての親が非常に心配している問題です。赤ちゃんの健康と成長にとっても非常に重要で...
1歳の赤ちゃんはリュウガンを食べても大丈夫ですか?
すでに 1 歳になっている赤ちゃんは、生涯を通じていくつかの補助食品を食べることができます。この時、...
子どもの虫歯はどうして発症するのでしょうか?
ご存知のとおり、子どもの自制心は一般的に低く、甘いものが好きな子どももいます。親がすぐに止めずに食べ...
ステンレス製のボウルは子供にとって有害ですか?
キッチンにあるさまざまな洗面器、鍋、ボウルなどは、重くてかさばる鉄製ではなく、ステンレス製になってい...
赤ちゃんが鼻水や鼻炎になった場合はどうすればいいですか?
これは人々に多くの迷惑をかける病気でもあります。治療プロセスは非常に長く、治癒が困難です。治療中に症...
小児の喘鳴と喘息の違い
喘息は非常に治りにくい病気です。臨床医学技術においても、喘息が治ることは全くありません。症状を緩和し...