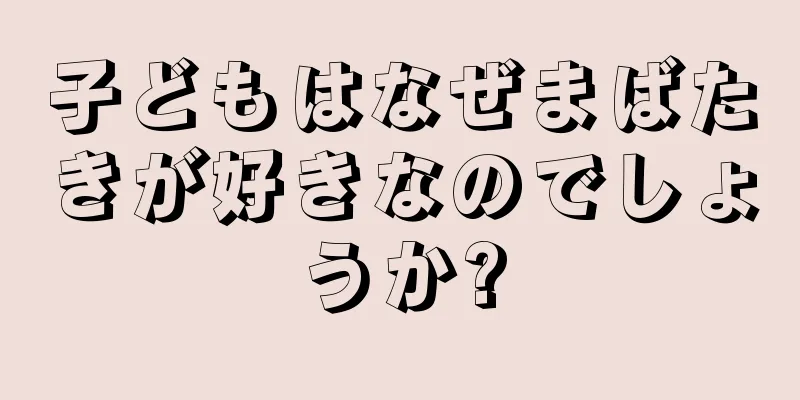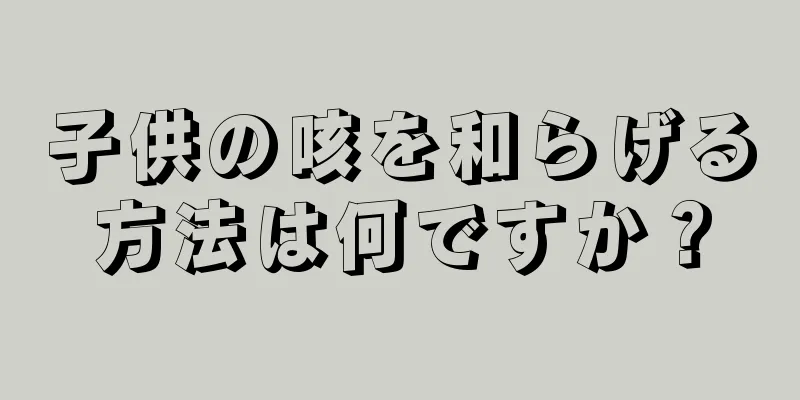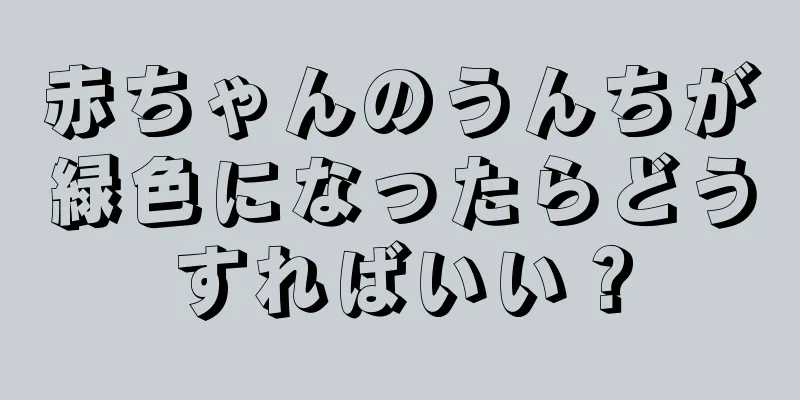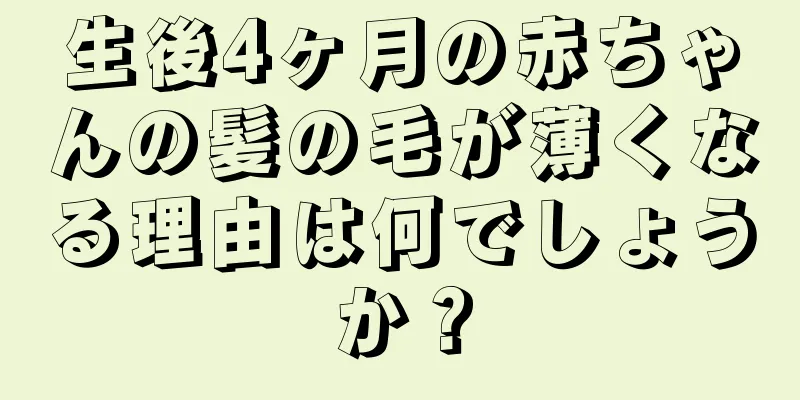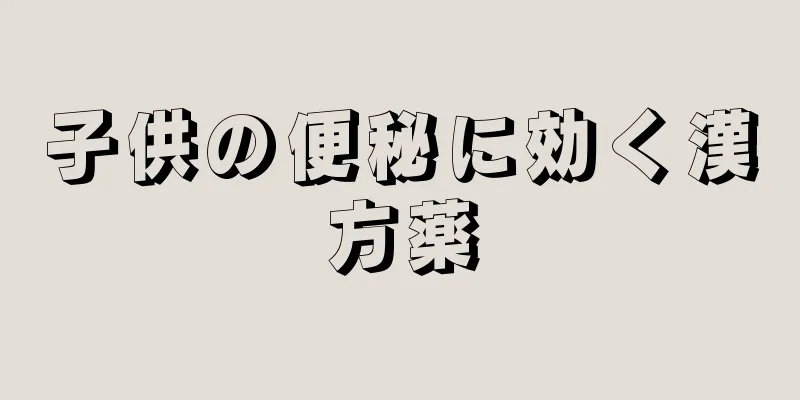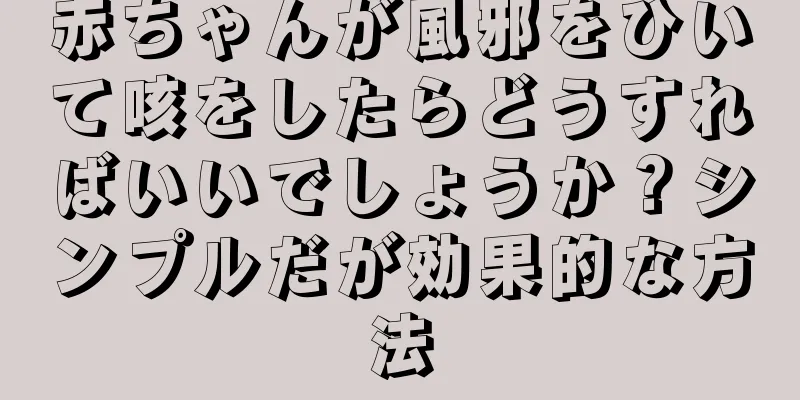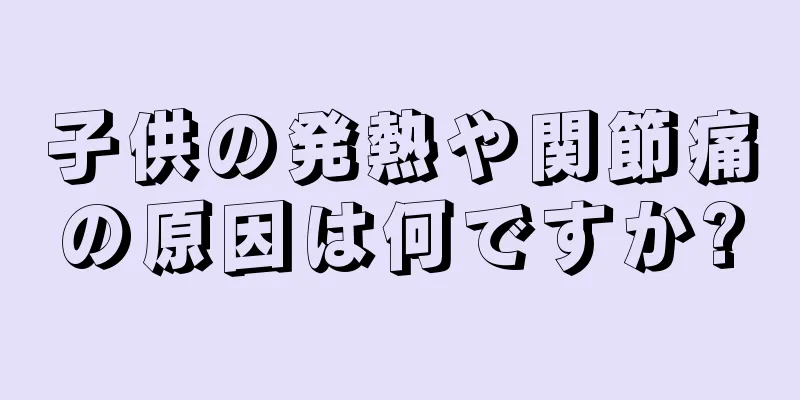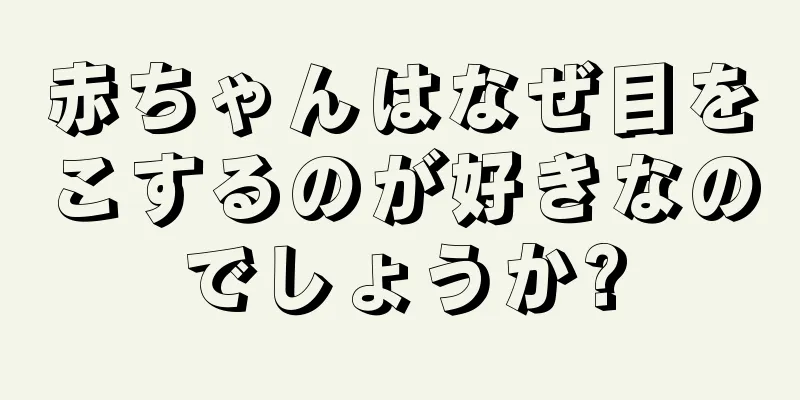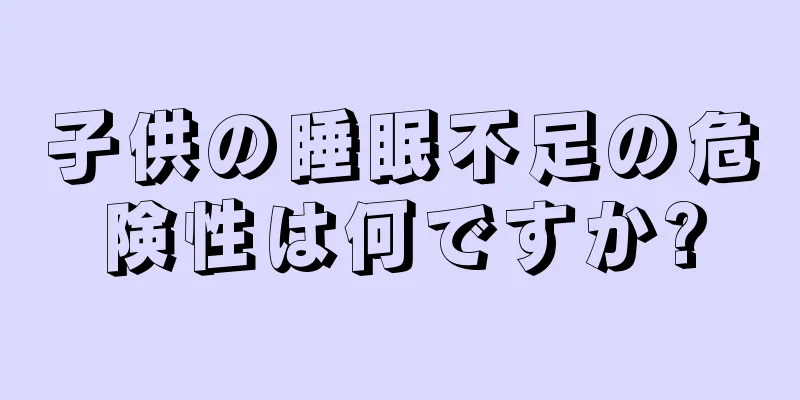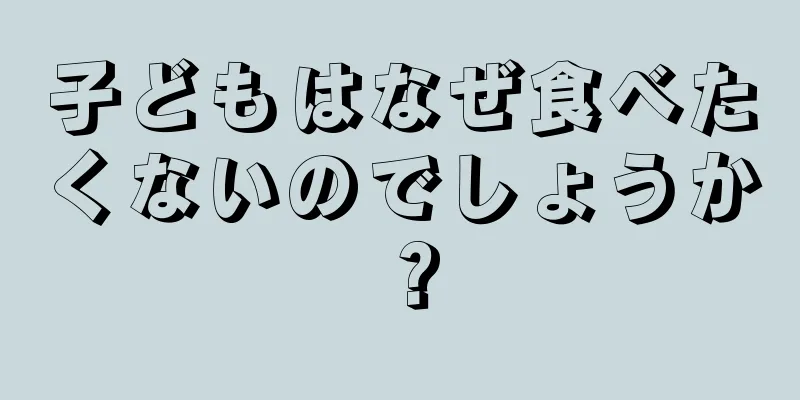子どもが食べ物に好き嫌いがある場合の対処法
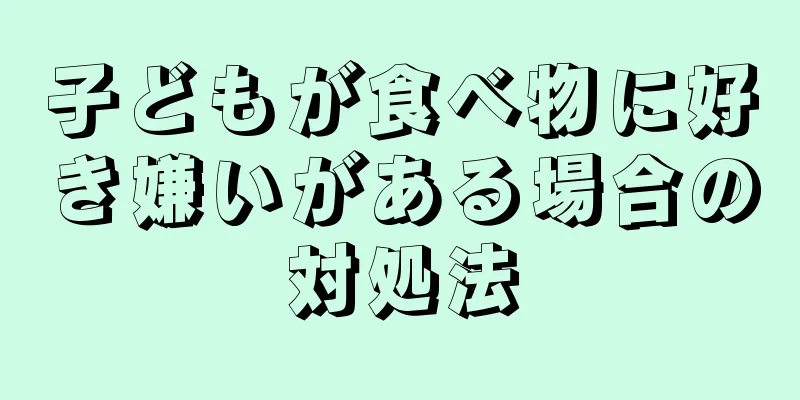
|
子育ては長いプロセスです。諺にあるように、人は鉄、食べ物は鋼です。食事を取らないと、空腹を感じます。子どもが幼い頃から好き嫌いをする習慣を身につけてしまったら、栄養バランスはどうやって確保すればいいのでしょうか。子どもの好き嫌いの問題は、習慣化して矯正が難しくなることを防ぐために、できるだけ早く解決する必要があります。私たちの周りではそのような例が数多く起こっているので、大げさに考えないでください。 子どもはなぜ好き嫌いが多いのでしょうか。それは食べ物があまり美味しくないからかもしれません。そのため、親は料理にもっと力を入れなければなりません。子どもがいつも 1 品か 2 品しか食べないのであれば、栄養バランスを保つために他の料理も試すように指導する必要があります。 好き嫌いの理由 1. 子ども自身の消化力が弱く、親が子どもに正常な食習慣を身につけさせておらず、親自身も偏食の癖がある。 2. 親は子供の成長に気を遣いすぎて、子供が好まない栄養補助食品を無理やり食べさせてしまいます。子供にさまざまな食べ物を与えることに注意を払わないため、子供の味覚が特定の食べ物に適応できなくなります。 3. 親は子供に過度のプレッシャーをかけたり、おやつを食べ過ぎさせたりしてはいけません。 好き嫌いの危険性 1. 好き嫌いや偏食は子供にとって非常に悪い習慣であり、成長と発達に非常に有害です。 2. 食べ物に好き嫌いがあると、ビタミン欠乏症になりやすくなります。ビタミンが不足すると、ビタミン欠乏症候群を引き起こし、体の健康や病気の回復に影響を及ぼします。 3. 食べ物の好き嫌いは、特定の栄養素の摂取不足や過剰につながり、体力の低下や抵抗力の低下を引き起こし、病気や過度の肥満にかかりやすくなり、子供の成長と発達に深刻な影響を与えます。 子どもの偏食の問題を解決する方法 1. 子どもに野菜を洗ったり、食卓の準備を手伝わせましょう。食事の前に激しい運動をしないでください。食事中は子どもが一人で食べられるようにしてください。食事中は子どもにネガティブな感情を抱かせないでください。 2. 子どもの好き嫌いを甘やかさない。積極的に教え、好き嫌いをする機会を与えないようにしましょう。食べるときには、その食べ物はおいしいし、子どもも好きになるだろうとほのめかしましょう。好き嫌いをしない手本を示しましょう。賢い組み合わせで料理するなどしましょう。 3. お子さんが微量元素不足に陥っていないか、定期的に小児科病院で検査を受けたり、お子さんが吸収しやすいサイズの脾臓強化・補血顆粒を与えたりすることができます。 通常の指導が効果がない場合には、薬物療法による治療が必要になります。絶対に必要な場合を除いて、薬は使用しないようにしてください。結局のところ、すべての薬は有毒です。この原則を覚えておく必要があり、子供が薬で問題を抱えることがあってはいけません。さらに、お子様にサンザシなどの前菜を選んで食べさせることもできます。これにより、食欲が増進し、好き嫌いが減ります。 |
推薦する
小児高血圧の診断基準は何ですか?
小児高血圧の診断基準は何ですか?小児高血圧の数値基準は成人と同じですか?小児高血圧は、子供は自分の症...
新生児の目の大きさはそれぞれ異なる
子供が生まれた後、両親が新生児の目の大きさが異なることに気付いた場合、これは人生では非常に一般的なこ...
赤ちゃんの足裏が熱くなる理由
赤ちゃんの身体の健康は親にとって最も重要な問題です。赤ちゃんがさまざまな症状を示すと、親は非常に心配...
2歳の赤ちゃんの足がまっすぐでない場合の対処法
多くの赤ちゃんは足が曲がっていますが、まだ小さいので矯正するのは簡単です。 2 歳児の足がまっすぐで...
子供はバッタを食べても大丈夫ですか?
バッタは蝉の蛹のことを指し、河南省では蝉の幼虫の呼び名です。蝉の蛹は栄養価が非常に高く、夏には各地で...
赤ちゃんの体に湿気や熱がある場合は、10種類の食べ物を食べることでそれを解消することができます
春は雨が多く風が強い季節です。雨が多く湿気が多いと、湿度が高くなりすぎると感じやすく、赤ちゃんも呼吸...
お子様の歯が腐食してしまったらどうすればいいですか?
子供は親にとって新しい赤ちゃんであり、子供に生じるあらゆる問題は拡大されます。私たちはたいてい身体的...
新生児の髪はどのくらいの頻度で剃るべきですか?
私の国の一部の田舎では、赤ちゃんが1ヶ月になったら、赤ちゃんの髪を剃るべきだという言い伝えがあります...
赤ちゃんは何ヶ月で寝返りが打てるようになりますか?
赤ちゃんがさまざまなスキルを習得するには時間がかかります。赤ちゃんは生まれたばかりのときは泣くことし...
赤ちゃんの膝がポキポキ鳴ると健康に影響しますか?
家族は子供の健康状態に異常があることに気付いたとき、やはりとても心配になります。では、赤ちゃんの膝が...
赤ちゃんの頭が汗をかいた場合はどうすればいいですか?
赤ちゃんが次々と生まれてくる中、親たちは多くの赤ちゃんの症状をあまりよくわかっていませんが、赤ちゃん...
脳性麻痺の子供は正常な知能を持っていますか?
赤ちゃんが妊婦さんのお腹の中にいるときは、赤ちゃんが健康かどうかは判断できるはずですが、中には特定で...
自閉症の症状、3つの側面をお伝えします!
自閉症は、臨床現場では自閉症としても知られており、比較的よく見られる精神疾患です。自閉症はさまざまな...
赤ちゃんの食欲不振の原因は何でしょうか?
どの子供も親のお気に入りです。どの子供の食事と日常生活も親の関心事です。子供があまり食べないと、親は...
2歳児の朝食
赤ちゃんは2歳になると食欲不振、食欲不振、好き嫌いが見られるようになるため、親はどうしようもない気持...