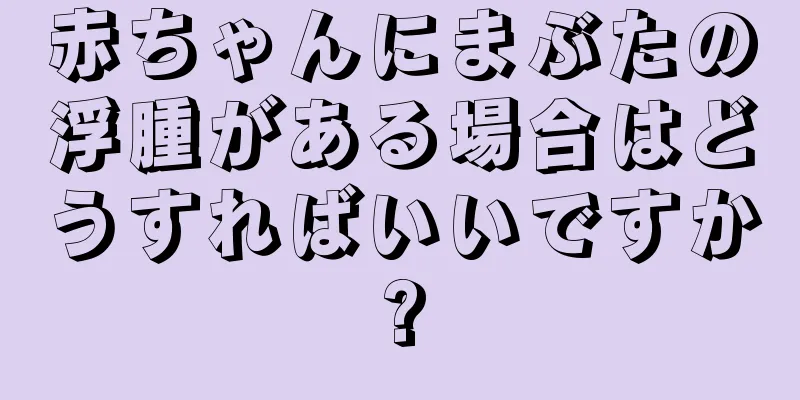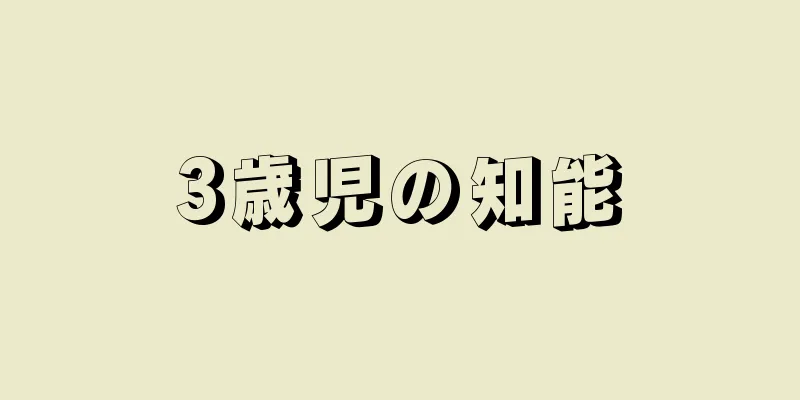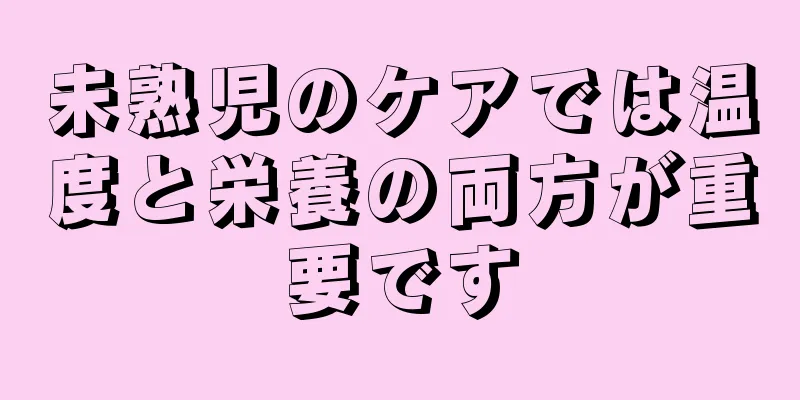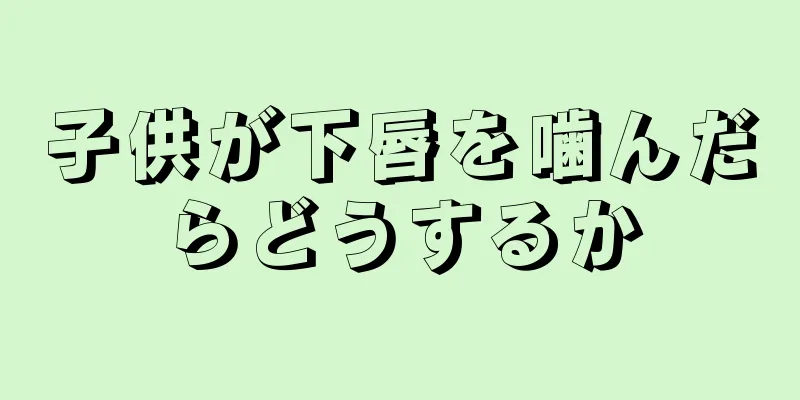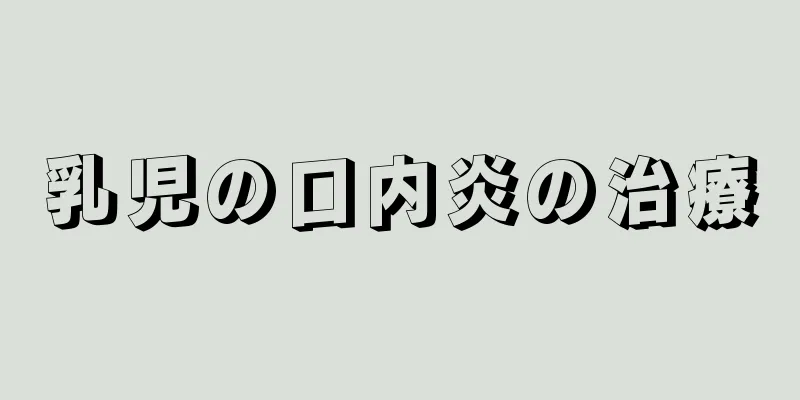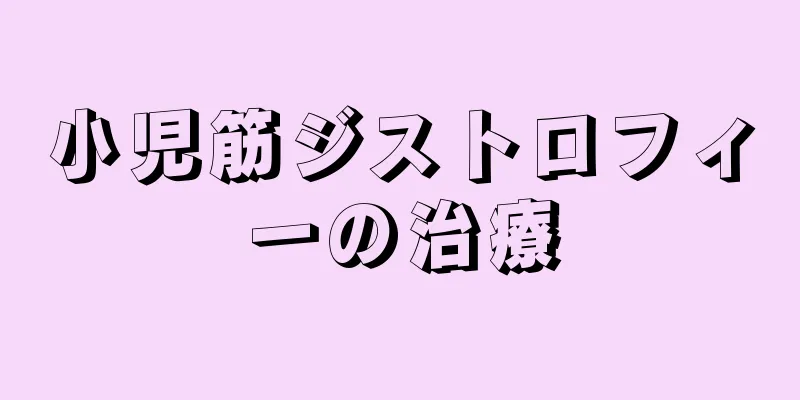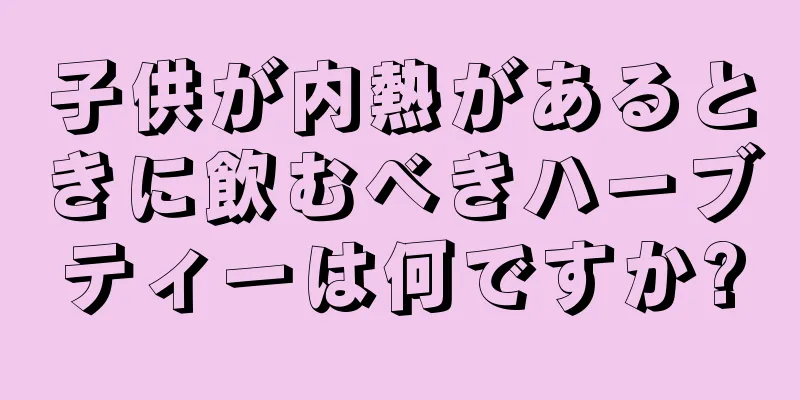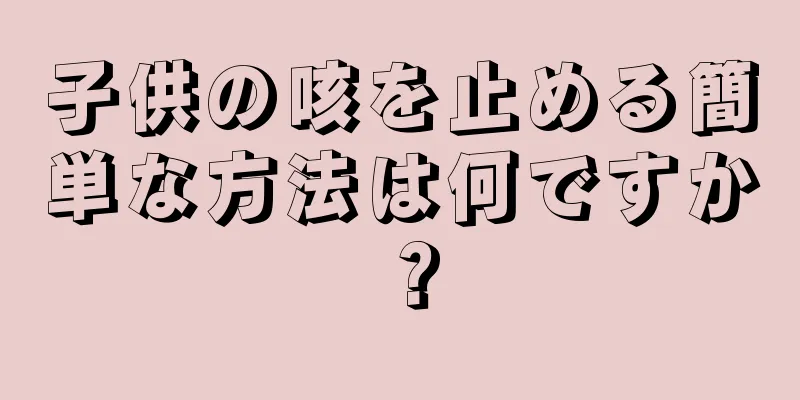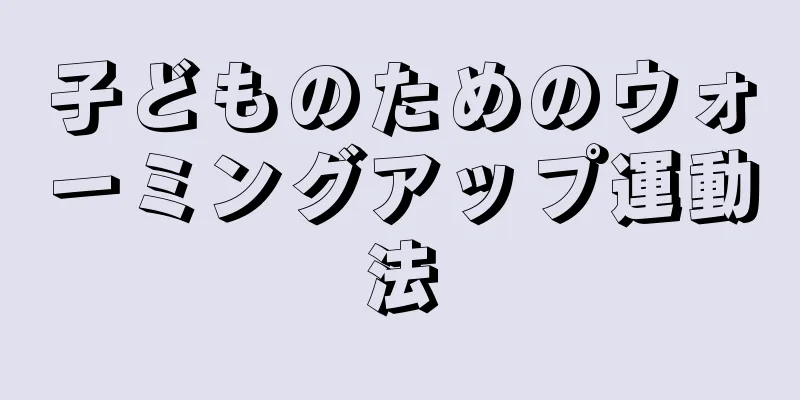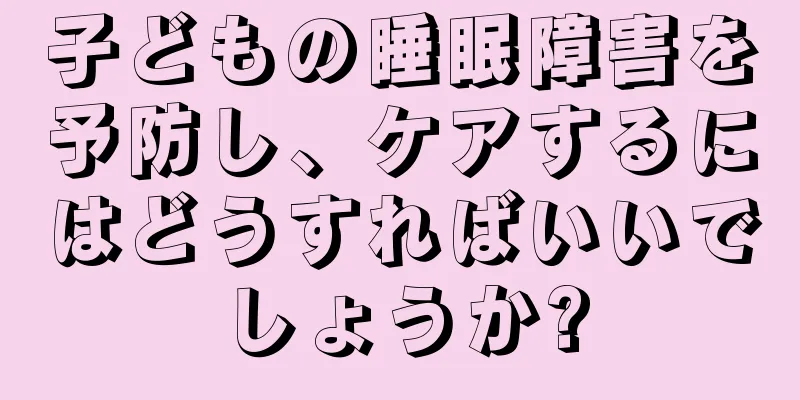生後6ヶ月の赤ちゃんが斜視になった場合の対処法
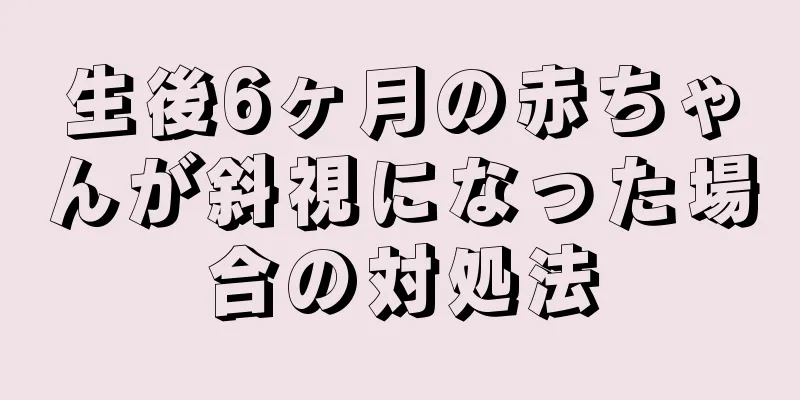
|
赤ちゃんの中には斜視の状態で生まれる子もいます。何かを見るとき、左右の目の眼球が中央に寄ってきます。この症状は生後6か月になるまで改善しません。家族は赤ちゃんが大きくなって斜視になってしまうのではないかととても心配しています。治療の必要はないと言う人もいれば、治療のために病院に行く必要があると言う人もいます。斜視は、一般的に「寄り目」と呼ばれ、医学的には「内斜視」と呼ばれます。 1. 赤ちゃんの目のトラブルのほとんどは生理的な現象です 大人と比べると、赤ちゃんの鼻梁はずっと平らに見えます。これは鼻骨がまだ完全には発達していないためです。そのため、目の間の皮膚がずっと広く見え、眼球の内側の白目のほとんどまたはすべてを覆っています。その結果、赤ちゃんは「寄り目」のように見えます。これは偽斜視とも呼ばれ、偽の寄り目の一種です。さらに、生後数か月間は、眼球運動を調節する筋肉の一部が十分に発達しておらず、両眼の動きを調整する能力が乏しい。赤ちゃんの目の柔軟性も低下しているようで、母親は赤ちゃんの目を疑うようになる。一般的に、2〜3 か月後には、赤ちゃんの両目の焦点を合わせる能力が十分に発達します。 2. 赤ちゃんの目が寄り目かどうか見分ける方法 赤ちゃんの目は成長すると良くなると言われていますよね?それで、どれくらいの大きさにすべきでしょうか?一般的に、生後 6 か月を過ぎると、赤ちゃんの両目で物体に焦点を合わせる能力が向上し、斜視は起こらなくなります。 6 か月経っても改善が見られない場合は、すぐに医師の診察を受けてください。しかし、6 か月経っても斜視が続いている場合、それが必ずしも真の斜視であるとは限りません。診断には眼科医によるさらなる検査が必要です。親は自宅で赤ちゃんの簡単な検査を行うこともできます。具体的な方法は、赤ちゃんを横に寝かせ、大人がランダムに物体を拾い、赤ちゃんの目から40cm以上離れたところで左右に動かして赤ちゃんに見せるというものです。このとき赤ちゃんの眼球の内側にまだ赤ちゃんの白目が見えていれば、赤ちゃんの目は「斜視」ではないことを意味します。 3. 赤ちゃんの斜視を矯正する方法 1. 多角度吊り下げおもちゃ おもちゃはベビーベッドの決まった場所に掛けず、頻繁に位置を変えてください。赤ちゃんの部屋の明るい色の装飾も、子供がいつも同じ場所を見つめないように頻繁に変える必要があります。 2. 寝る姿勢を頻繁に変える 赤ちゃんは常に片側を下にして寝かせ、母親は赤ちゃんが時々左に、時々右に体位を変えるのを手伝う必要があります。これにより、光の投影方向が頻繁に変わり、赤ちゃんの目が複数の側を向くようになり、斜視を防ぐことができます。 3. 赤ちゃんの目を頻繁に動かす 赤ちゃんを一日中ベビーベッドやベビーカーの中に放置しないでください。赤ちゃんを屋外に連れ出し、頻繁に歩き回って、さまざまなものを見る機会を与えるのが最善です。好奇心旺盛な赤ちゃんは目を絶えず動かすので、目の筋肉と神経の協調性が高まり、斜視を防ぐのに役立ちます。 |
推薦する
子供の爪に白い斑点がある場合は、適時に微量元素を確認してください
赤ちゃんの爪に白い斑点が見つかった場合、親は注意する必要があります。多くの場合、微量元素の不足または...
赤ちゃんは何歳から別々の部屋で寝かせた方が良いのでしょうか?
多くの大人は、赤ちゃんと一緒に寝るととても幸せを感じます。しかし、赤ちゃんは成長し続けます。物心つい...
男の子が髪の毛を失ったらどうすればいいでしょうか?
思春期の男の子は急速に成長し、発達するため、男の子の脱毛などの悪い状況が発生することは避けられません...
子供の指先の白い斑点の解決方法
最近、多くの子供たちの指先に白い斑点があります。これは、胃腸の消化器系に何らかの問題があるか、胃の中...
赤ちゃんの目が赤いのはなぜですか?
赤ちゃんの目が赤いと、特に心配する親はたくさんいます。赤ちゃんの目が赤いと、他の目や体の病気を引き起...
寝る前に子供が咳をしたらどうするか
子どもが成長していく過程で、風邪をひいたり、怒ったり、咳をしたりすることは避けられません。母乳から完...
男児の尿路感染症の症状
生後数年間に尿路感染症に罹る赤ちゃんもいますが、この病気がすぐに通常の病院で治療されない場合、非常に...
子供の首のけいれん
子供が幼いとき、泣くことによって引き起こされるけいれんの現象は非常に深刻です。多くの子供は泣いた後に...
赤ちゃんの髪が白くなったらどうすればいいですか?
赤ちゃんの健康は家族にとって最も幸せなことです。現在、ほとんどの家庭は一人っ子なので、子育ては非常に...
赤ちゃんの手に白い斑点ができる原因は何ですか?
赤ちゃんは話すことができないので、話せないことがあるのではないかと心配で、私たちは皆、赤ちゃんに特別...
1週間4ヶ月の離乳食レシピ
赤ちゃんは日々成長し、その体はますます多くの栄養を必要とします。赤ちゃんにもっと栄養を与えるために、...
赤ちゃんの食欲を刺激するために何を食べたらいいでしょうか?
暑い夏を迎えると、大人だけでなく、子どもの食欲も著しく低下します。しかし、子どもは大人のように好きな...
赤ちゃんが鼻づまりになったらどうすればいい?
赤ちゃんの鼻づまりは主に生理的または病理的です。日常生活では、風邪などが原因となる場合があります。そ...
子どもが水っぽい便をしたらどうするか
乳児の軟便は、胃腸の働きが悪く、正常に吸収できないことや、不適切な授乳、細菌感染などにより起こること...
お子様の脳波に異常があった場合、どうすればいいでしょうか?
脳波は人体のさまざまな器官を直接反映し、さまざまな生理機能が健康であるかどうかを理解するのに役立ちま...