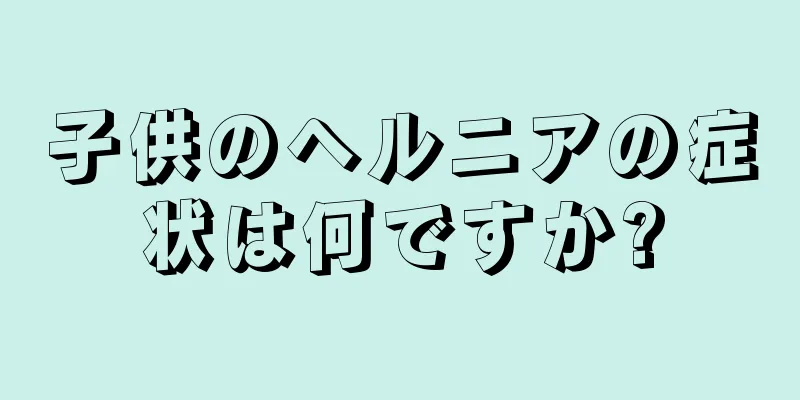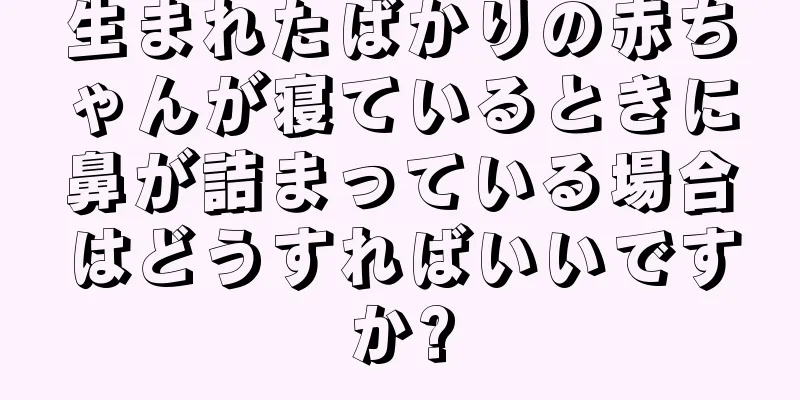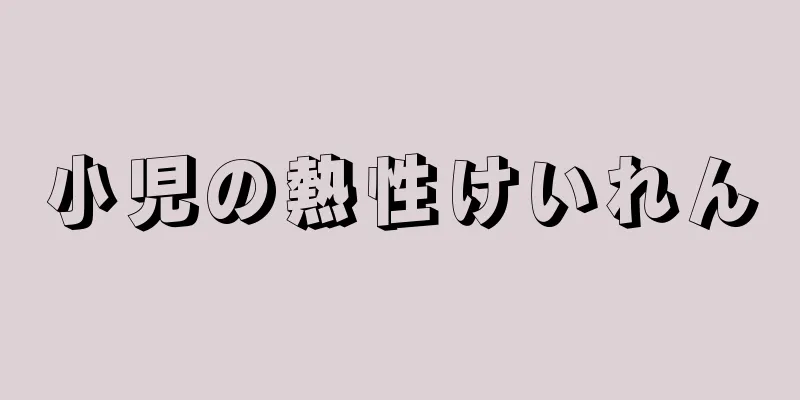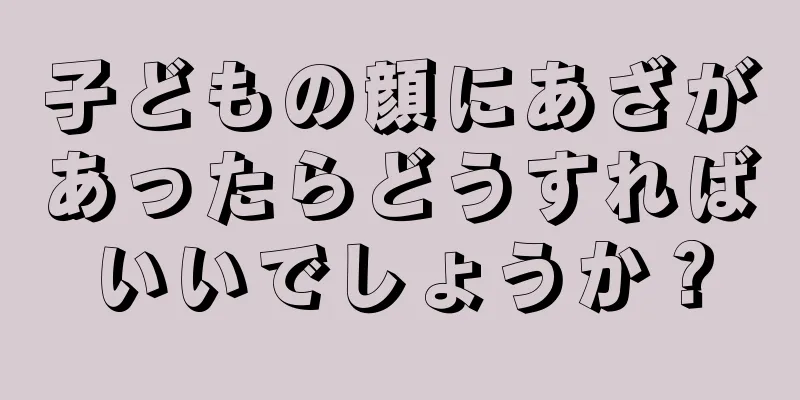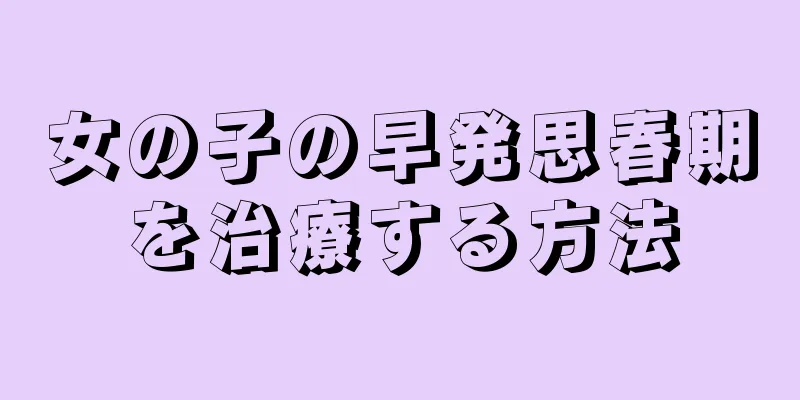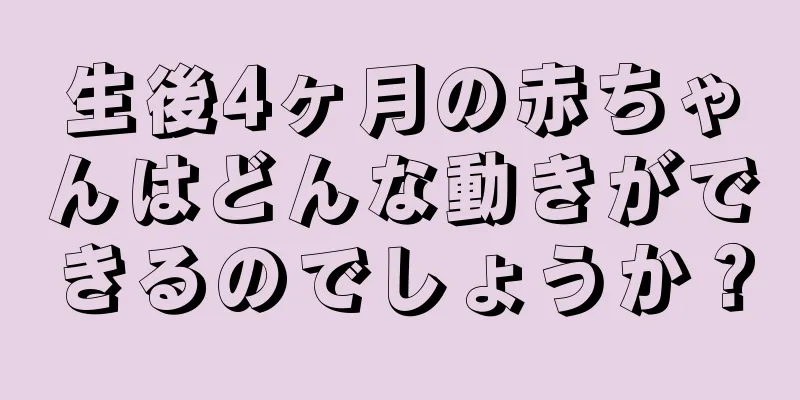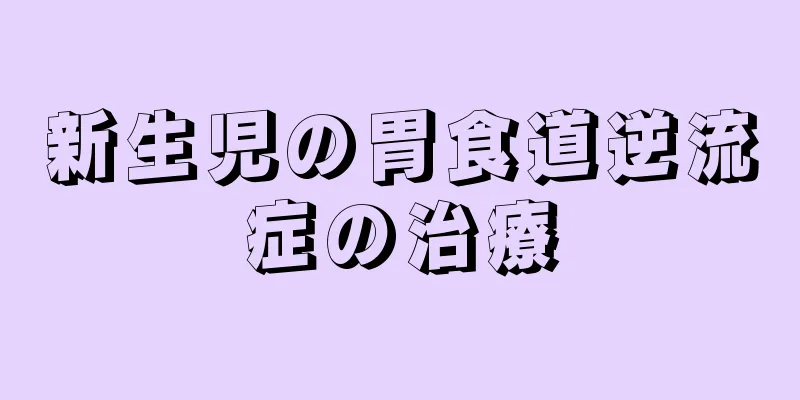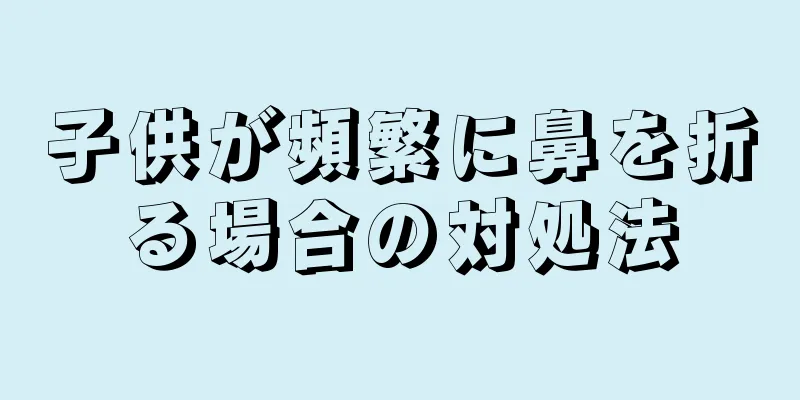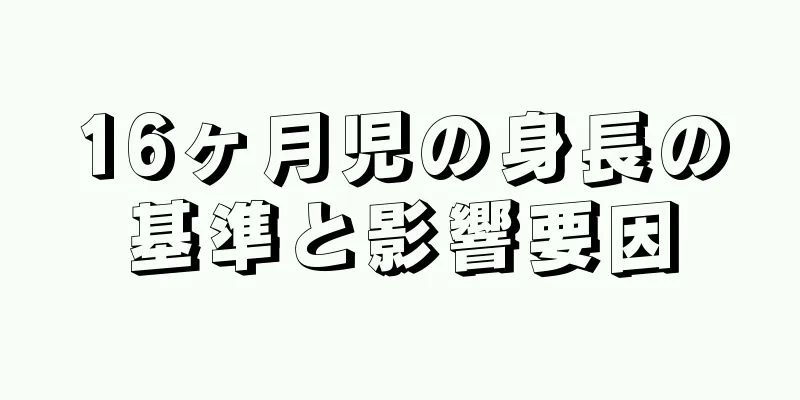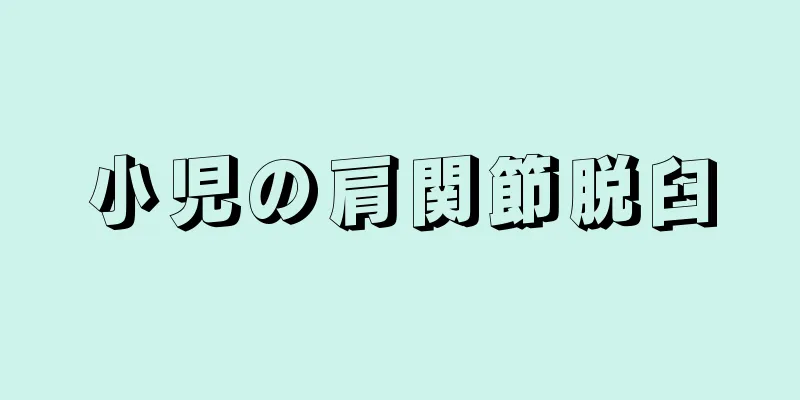幼稚園入園の不安にどう対処すればいい?
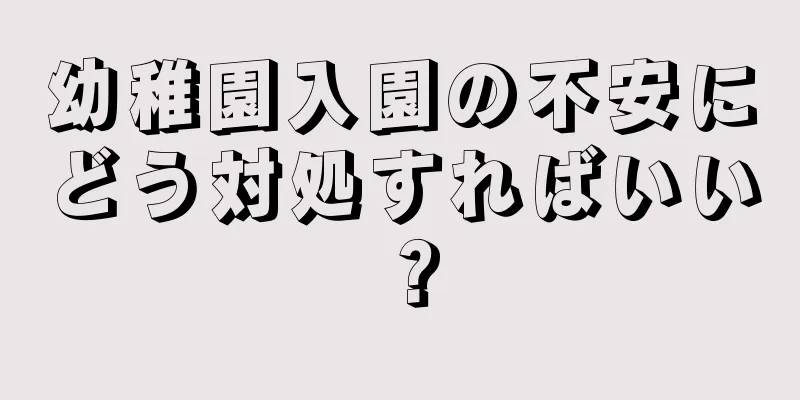
|
親が初めて子供を幼稚園に連れて行くとき、子供は慣れない環境に慣れていないため、親から離れようとしません。親が去ると子供は泣きます。ようやく落ち着いた後、子供は幼稚園でも不安になります。この問題は、幼稚園の先生と親が一緒に対処する必要があります。まず、子供の状況を考慮する必要があります。特に、次の対処のヒントを覚えておく必要があります。 幼稚園入園の不安にどう対処すればいい? まず、子供を慰めてあげましょう。まずは子どもを落ち着かせ、入院することに興奮しないようにしてください。子どもが興奮していると、理屈を聞かなくなります。 次に、なぜ幼稚園に行かなければならないのかを子どもに明確に説明する必要があります。子どもの中には、親が自分を嫌いになって捨てようとしているから幼稚園に残されていると考える子もいます。子どもを正しく導き、親がなぜ幼稚園に行かせたいのか理由を子どもに伝える必要があります。 次に、幼稚園に対する子どもの興味を育て、幼稚園にはどんな楽しいことがあるかを伝え、適切なご褒美を与えることです。例えば、子どもが1週間幼稚園で良い成績をとったら、遊びに連れて行ってあげてもいいなど、約束は守らなければなりません。 子どもが初めて病院に入院したときは、親が適切に付き添ってあげてください。いきなり子どもをそこに置き去りにしてはいけません。子どもは慣れない環境に放り込まれると特に怖がり、その後その場所に抵抗するようになります。ですから、焦らずゆっくり進め、文句を言うのではなく子どもを励ましてあげてください。 3歳児が初めて幼稚園に入園し、愛着対象(主に親戚)から離れると、すぐに不安、落ち着かない、悲しい、辛いなどの感情が表れ、コケティッシュな態度をとったり、泣いたり、騒いだりするなど、離れることを拒否する兆候が見られます。これは子供の幼稚園不安であり、実際には一種の分離不安であり、緊張して不安な感情です。通常、3歳の子供は幼稚園に入学して勉強や生活を始め、3.5歳は子供が愛着を育むピークの時期です。幼い子どもたちが初めて新しい幼稚園に入るとき、慣れない環境、慣れない先生、慣れない友達によって不安を感じ、大切な人たちへの愛着が強まり、愛する人たちと離れたくないと思うようになります。大切な人がいなくなると、幼い子どもは不安を感じ、頼れる対象がなくなり、幼稚園に行くことに不安を感じるようになります。 幼稚園に入園すると、子どもは誰でも多かれ少なかれ分離不安を経験しますが、その程度はさまざまです。一般的に、幼児が幼稚園に行くときに不安に思うことは、親類にしがみつく、先生に抱っこをせがむ、泣く、騒ぐ、転がる、物を投げる、眠い、ぼーっとする、おねしょをする、おねしょをする、食事を拒む、水を飲まない、指を噛む、指を切る、壁に頭を打ち付ける、などです。幼児はこれらの脅しを使って、親が自分から離れないようにすることがよくあります。人生で最初の分離不安は、子供が初めて幼稚園に入園したときに起こります。 |
>>: 赤ちゃんがビンロウの実を食べるのは良いことでしょうか?
推薦する
子供の口腔掻痒症
子どもの身体の健康は非常に重要ですが、大人が子どもの身体の健康に注意を払わないと、何らかの問題が見つ...
子供の風疹の症状は何ですか?
子どもの蕁麻疹の現象は、親にとって心配な問題です。結局のところ、子どもの免疫力は比較的低いので、生活...
子供の鼻炎の原因は何ですか?
子供にとって、それは成長と発達の段階です。彼らの免疫システムはまだ完璧ではなく、抵抗力は比較的弱いで...
妊娠6ヶ月での赤ちゃんの発育基準はどのくらいですか?
妊娠6ヶ月の妊婦にとって、妊娠6ヶ月間の赤ちゃんの発育基準を理解することは非常に重要です。こうするこ...
子どもが熱を出したり細菌感染したりした場合、親はどうすればよいのでしょうか?
今日の多くの3人家族では、子どもが家庭の中心であり、親は子どもを宝物のように大切にしています。いつで...
小児行動障害
どの子供も親にとってかけがえのない存在であり、あなたの子供も常にあなたの心の中にいると思います。そう...
子供の目のかゆみの原因は何ですか?
子供の目のかゆみは、通常、角膜の問題が原因です。まつ毛が長すぎると、角膜に刺さって目のかゆみを引き起...
赤ちゃんの便に茶色い粒子が混じっている
子供の正常な便は黄色です。消化不良のため、便は薄く、凝乳状になることもあります。便の質感が変化すると...
小児の尿失禁の治療
子供の尿失禁は多くの親にとって頭痛の種となっています。この状況はますます一般的になっています。生活の...
どのような運動が子供の身長を伸ばすのに役立ちますか?
身長を伸ばすには、当然ながら運動が欠かせません。運動に集中することでのみ骨がよりよく発達し、身長を伸...
子供の副鼻腔炎を予防するにはどうすればいいでしょうか?
副鼻腔炎は、多発性または単発性です。副鼻腔炎は通常、急性副鼻腔炎と慢性副鼻腔炎の2種類に分けられます...
子供がいつも下唇を噛む場合の対処法
子どもが下唇を頻繁に噛むと、歯が前に突き出る原因になりやすく、歯が生えている段階にあるため、この悪い...
携帯電話を見ることは子供の目にどれくらい有害でしょうか?
携帯電話の普及に伴い、多くの子どもたちは自分の携帯電話を見なくなり、毎日親の携帯電話を見ています。現...
早発思春期に影響を与える要因は何ですか?
子どもの早熟は現代社会ではよく見られる社会現象であり、多くの親がこの点に注目し始めています。小児にお...
2歳の赤ちゃんが下痢をしたらどうするか
2歳の赤ちゃんが下痢をするのは珍しいことではありません。親としては、赤ちゃんの成長や健康に悪影響を与...