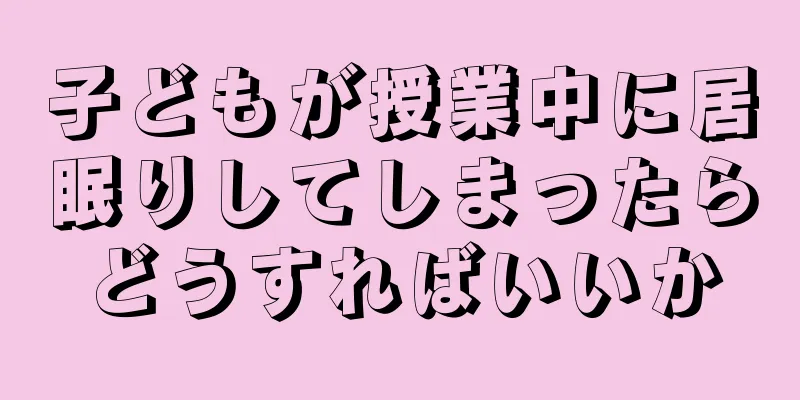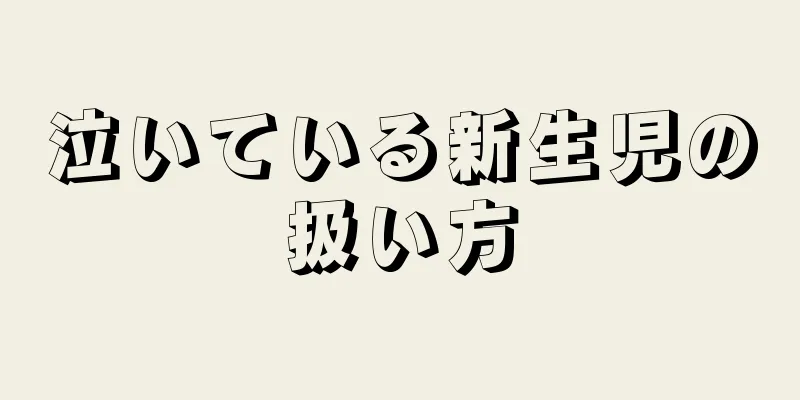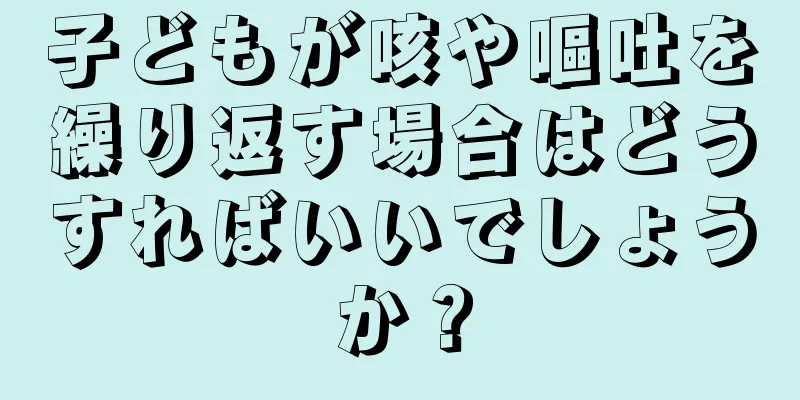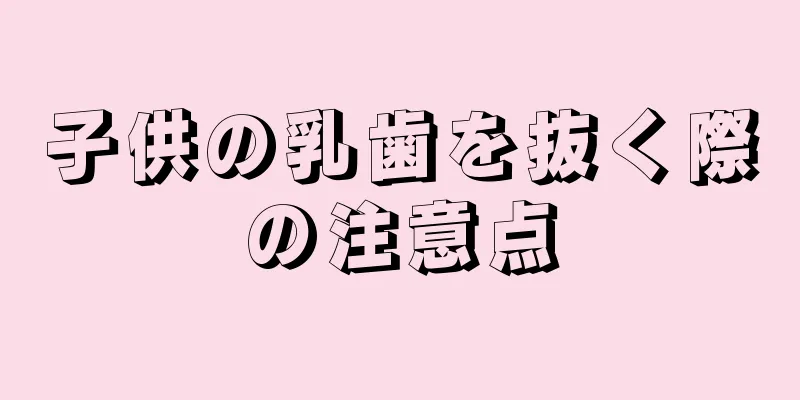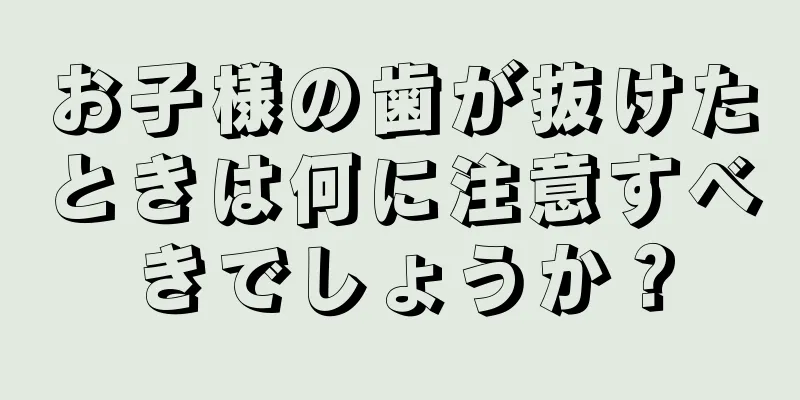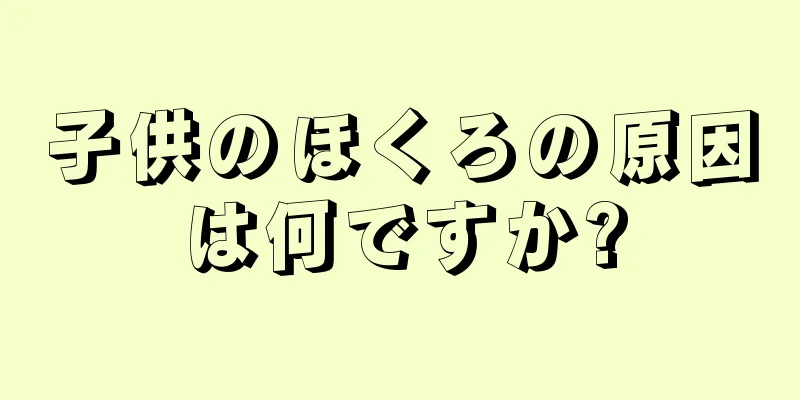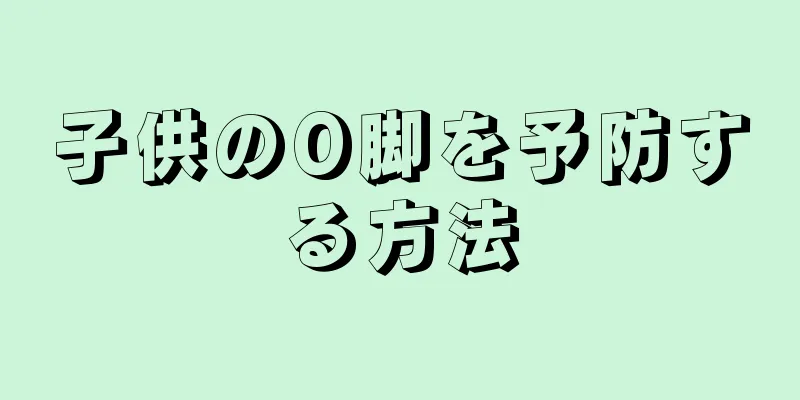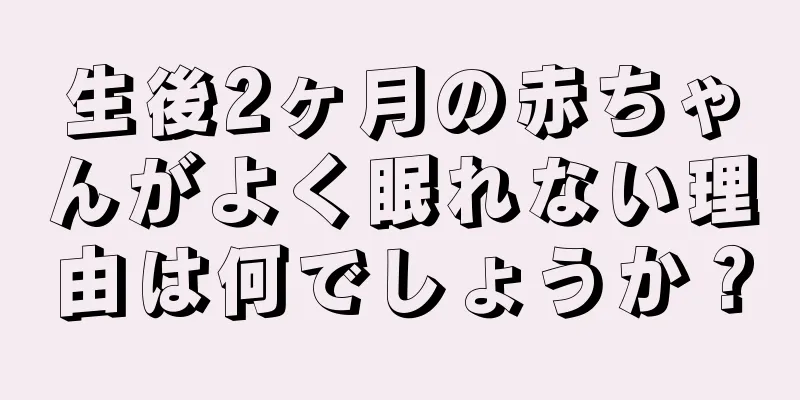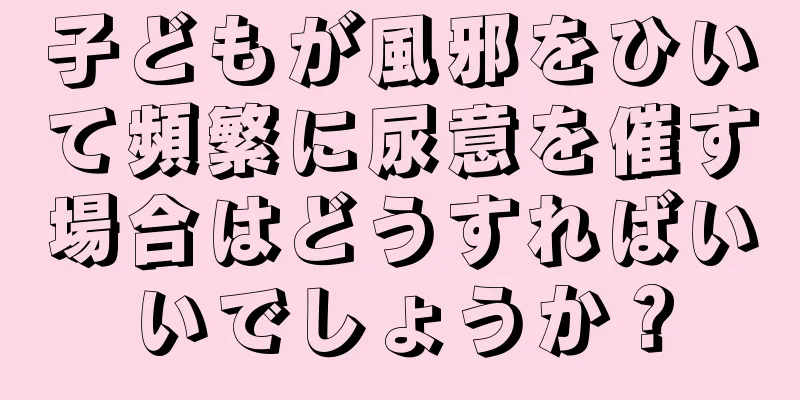赤ちゃんは何歳から卵の黄身を丸ごと食べられるのでしょうか?
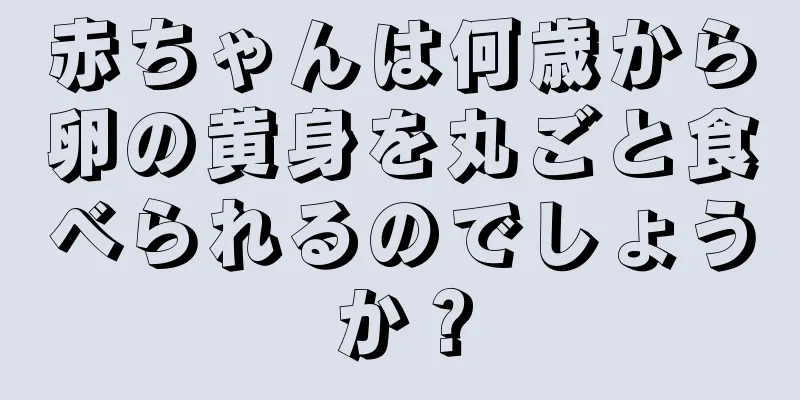
|
卵について言えば、卵白には水分が多く含まれ、最も栄養価が高いのは卵黄であることは誰もが知っています。含まれる栄養素は比較的包括的で、体に吸収されやすく、血液やカルシウムなどの補給に非常に有益です。では、このような栄養価の高い食品である卵黄は、赤ちゃんは何歳から食べられるのでしょうか。また、どのくらいの量が最も適切でしょうか。一緒に調べてみましょう。 卵黄は黄色い卵白と白い卵黄に分けられます。卵黄全体の約5%が白い卵黄で、残りは黄色いタンパク質です。 ①水。卵黄の約50%は水分で、残りは主にタンパク質と脂肪です。 ② タンパク質。卵黄に含まれるタンパク質のほとんどはリポタンパク質で、低密度リポタンパク質、高密度リポタンパク質、卵黄グロブリン、卵黄ホスファチジルコリンなどが含まれます。 ③脂質。卵黄には脂質が多く含まれており、その含有量は30~33%ほど。そのうちトリグリセリドが最も多く20%を占め、残りはリン脂質、ステロールなどです。 アドバイス:粉ミルクで育てている赤ちゃんは、今から卵黄を半分加えても大丈夫です。赤ちゃんは順応性が高く、6ヶ月で卵黄全体を加えることができます。8ヶ月まで延期することもできます。厳密な制限はなく、赤ちゃんに加える補助食品の量に応じて決めることができます。また、粉ミルクで育てている赤ちゃんは、卵黄に加えて、他の補助食品も加える必要があります。たとえば、野菜ジュース、またはどろどろの麺、どろどろのお粥、どろどろの野菜、レバーペーストなどです。このように、一定期間、卵黄を半分食べても大丈夫です。 実は、赤ちゃんが何歳になったら卵黄を丸ごと食べられるか、お母さんは心配する必要はありません。まず、赤ちゃんが食べる量や必要性はそれぞれ異なります。例えば、男の子と女の子の食欲には小さな違いがあるため、一般的に基準はありません。主に子供自身の吸収力に依存します。 |
>>: 赤ちゃんが牛乳アレルギーの場合はどうすればいいですか?
推薦する
子供の足の裏にニンニクを塗ると深刻な影響がありますか?
赤ちゃんが日常生活で咳をするのは普通のことですが、多くの赤ちゃんは親に甘やかされているため、親は非常...
10歳の子供はレモネードを飲めますか?
レモンには栄養素、特にビタミンCが豊富に含まれています。これらの栄養素は健康に非常に有益です。そうい...
赤ちゃんの目はなぜ紫色なのでしょうか?
赤ちゃんの体調は常に変化しており、何らかの病気や問題が起こりやすく、それが赤ちゃんの発育に大きな障害...
子供が夜に汗をかく理由
多くの場合、子供は夜寝るときにいつも汗をかくので、多くの親や友人を悩ませています。時間が経てば、子供...
子供の消化不良に対する食事療法
消化不良は多くの子供によく見られる病気です。症状は軽度の場合もあれば重度の場合もあります。適切なタイ...
活発な子供に欠けているものは何でしょうか?子育ての専門家が答えを教えます
多くの子供は活発で、これは正常な現象である可能性がありますが、一部の子供の活動は異常であり、体内の微...
混合授乳で母乳を飲むと吐いてしまう
赤ちゃんの胃腸の構造は異なるため、授乳中にさまざまな胃腸の問題が発生する可能性があり、その中でも嘔吐...
12歳の女の子の胸が未発達の場合の対処法
12歳の少女は思春期の初期段階にあり、乳房の発達は少女の成熟の始まりを示します。正常に発達した乳房は...
男の子が早発性発育障害を患った場合の対処法
男の子と女の子の最大の違いは、男の子は活発で、扱いにくく、身体の発達が早いことです。10歳になる前に...
未熟児の授乳に関する5つのヒント
一般的に言えば、未熟児の授乳は普通の赤ちゃんよりも注意が必要です。未熟児に授乳するときは、少量ずつ複...
子供が風邪をひいて熱が出たらどうするか
子供が風邪をひいて熱を出すのは、成長過程の避けられない現象です。成長過程でよく遭遇します。子供が風邪...
子供の先天性心疾患は治癒できますか?
昨今、妊娠に対する人々のこだわりはますます強くなっていますが、子供の先天異常は避けられません。遺伝だ...
子どもが食べ過ぎないようにすべき食品は?これらの7つの食品を控えましょう
親は赤ちゃんの食事に注意を払う必要があります。私たちが普段食べている食べ物、特に塩分を赤ちゃんに与え...
子供の脾臓と胃を強くするために何を食べると良いでしょうか?
脾胃が弱くなる原因は、一般的に不適切な食事、感情的要因、仕事と休息の不均衡、および脾胃の機能不全につ...
新生児の胎児毒素を除去する方法
生まれたばかりの赤ちゃんは、皮膚の発疹を起こしやすい傾向があり、これは一般に胎児毒素とも呼ばれていま...