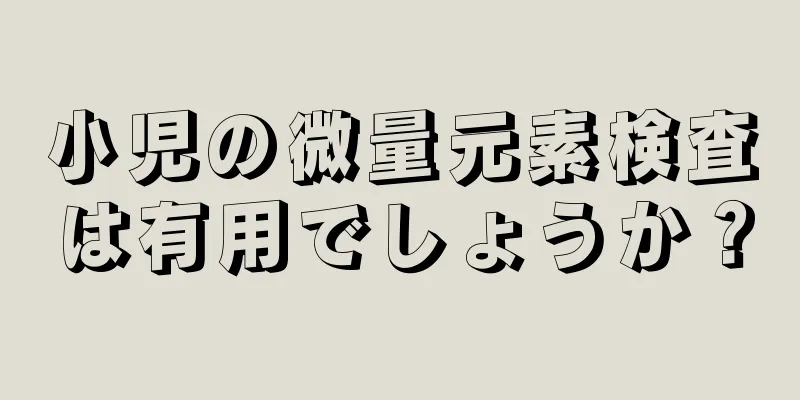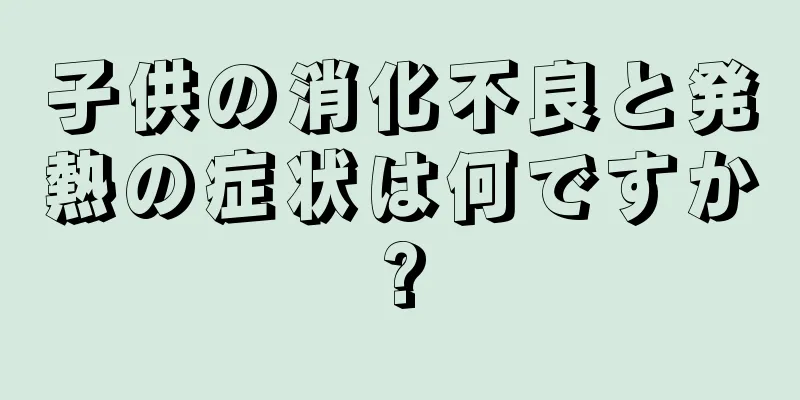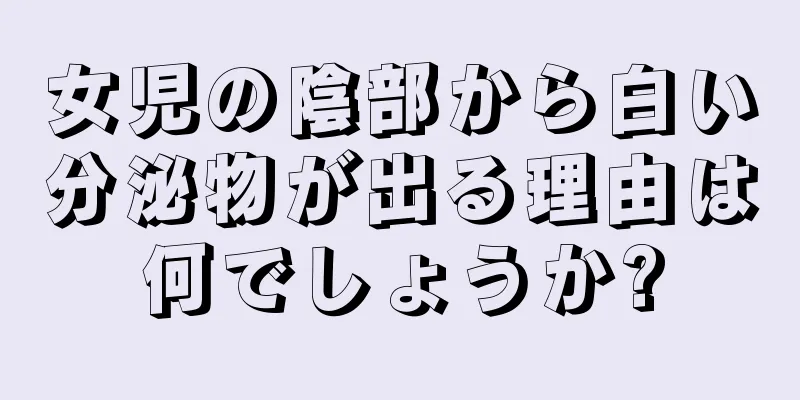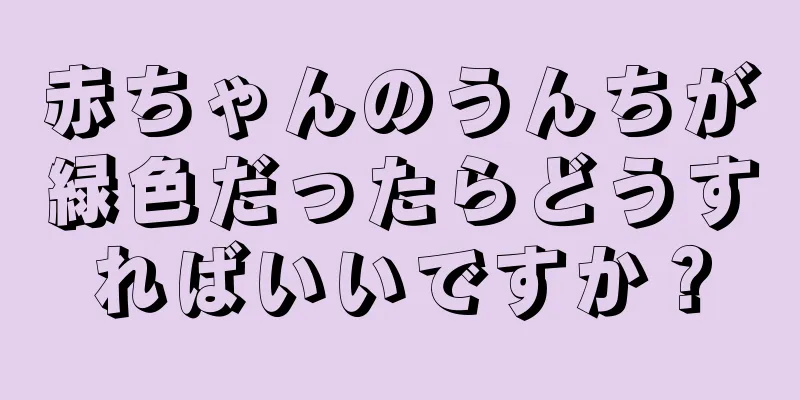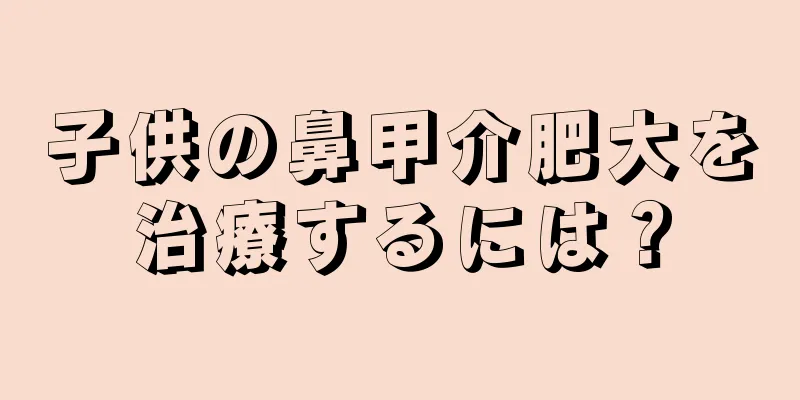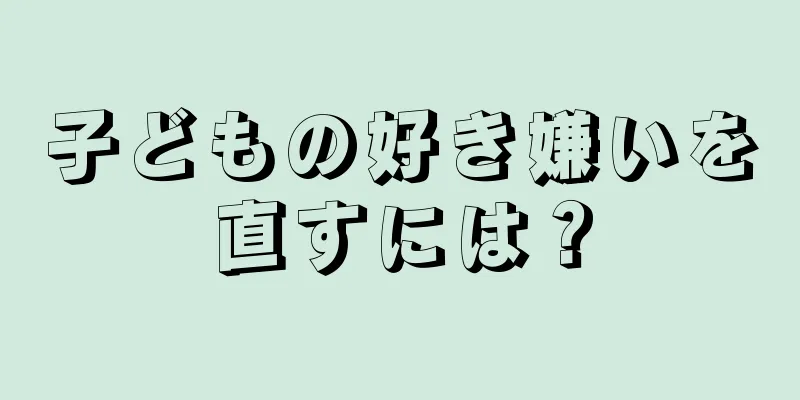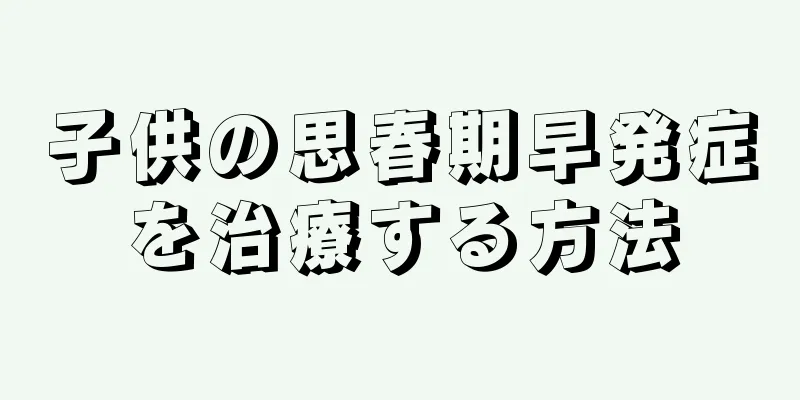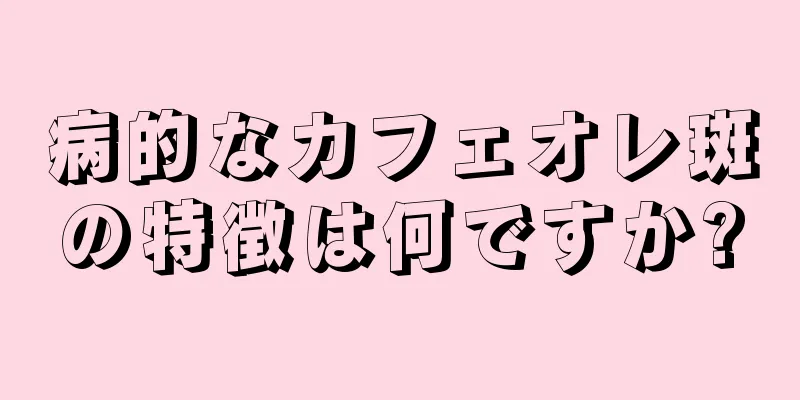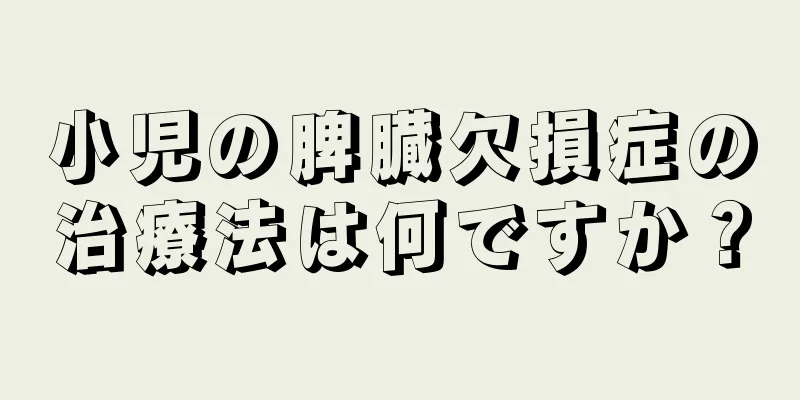新生児の発熱の症状

|
新生児の身体の健康は、すべての親にとって最も懸念される問題です。子供は比較的幼いため、体のさまざまな部分の臓器が完全に発達していないため、病気の症状が出やすい傾向があります。熱は新生児によく見られる病気ですが、熱の治療は比較的複雑です。子供が幼すぎるため、治療方法は子供自身の耐性に応じて決定する必要があります。新生児の発熱の症状は何ですか? 1. 高熱と脱水症状 新生児や乳児の体表面積は大人に比べて比較的大きいため、大人よりも熱を放散する速度が速いです。長時間包んだり、温めすぎたりすると、子どもの体の周りの温度が急激に上昇します。このとき、包みすぎると熱の放散に影響し、高熱状態に陥ります。このとき、人体の皮膚にある小さな血管が代償的に拡張し、皮膚の蒸発、つまり発汗と呼吸の増加による熱放散を促進するため、子供は大量の汗をかき、脱水症状に陥ることもあります。注意:また、熱が高いと体の新陳代謝が速くなり、酸素消費量が増加し、ベッド内の新鮮な空気が不足することで、子供に低酸素症を引き起こす可能性もあります。 2. 嘔吐 長時間保温された後、子供の体温は急激に上昇し、41℃~43℃に達します。大量に汗をかき、衣服はびしょ濡れになり、頭からは大量の熱い蒸気が出ています。顔は青白く、泣き声は弱々しく、食事も拒否します。 中枢神経系が影響を受けると、頻繁な嘔吐、叫び声、反応の鈍化、凝視、反復するけいれん、または昏睡が起こることがあります。 3. 昏睡または死亡 窒息し、発汗して水分を失うことで脳血流が減少し、脳組織が虚血・低酸素状態となり、昏睡に陥ることがあります。そして脳浮腫が起こることもあります。重症の場合、脳細胞の虚血性壊死により中枢神経系に永久的な損傷が生じ、てんかんや知的障害などの後遺症が残ることがあります。 過度の温暖化は多臓器不全や多系統不全を引き起こし、脳浮腫、不整脈、低血圧、呼吸不全、腎不全を引き起こし、また播種性血管内凝固症候群を引き起こす可能性もあります。すぐに治療しないと、短期間で赤ちゃんが突然死する可能性もあります。 新生児熱中症の原因は何ですか? この病気は主に、赤ちゃんを温めすぎたり、長時間覆いすぎたりすることで起こります。1歳未満の乳児、特に生後1か月未満の新生児によく見られます。通常、寒い季節に発生し、11月から翌年の4月までがピークとなります。 過度の温熱と蒸れは乳児熱中症の原因であり、乳児の神経系の発達が不完全、中枢神経系の調節が不十分、体表面の汗腺の機能が未熟、暑さから逃れられないことなどと関係があります。 赤ちゃんを暖かく保つと、体温が上昇し、40℃を超えることもあります。赤ちゃんは大量に汗をかき、最初は顔が赤くなり、その後、大量の水分が失われるため、イライラ、口渇、乏尿、大泉門と眼窩の陥没、皮膚の弾力性の低下などの脱水症状が現れます。この状態をコントロールしないと、深刻な合併症を伴う可能性があります。不適切な取り扱いや時期尚早な治療は、深刻な結果を招く可能性があります。 |
推薦する
消化不良の子供に良い食べ物は何ですか?
消化不良は大人にとっても不快ですが、子供にとってはさらに不快です。子供は無知で、痛みを表現する方法を...
赤ちゃんは4日間排便せず、おならだけしている
実際、赤ちゃんも便秘になることがあります。親が赤ちゃんの排便がないことに気付いたとしても、心配しない...
生後8ヶ月の赤ちゃんが熱を出しました
生後数ヶ月の赤ちゃんの世話をするときは、親がすべてを総合的に行う必要があります。これは赤ちゃんの健康...
赤ちゃんが熱を出したときの症状は何ですか?
赤ちゃんの体は非常に脆弱で、抵抗システムがまだ完全に確立されていないため、赤ちゃんの身体的健康は簡単...
子どもが猫背にならないようにするにはどうすればいいでしょうか?
調査によると、毎日重いランドセルを背負ったり、勉強中に正しい座り姿勢を保てなかったりして、多くの子供...
鍼治療は子供の近視に効果がありますか?
鍼治療は現在、伝統的な中国医学で使用されている治療法です。鍼治療は多くの病気の治療に使用できます。鍼...
赤ちゃんが過剰に発汗する理由は何でしょうか?
多くの母親は、赤ちゃんが汗をかきすぎることに気付くかもしれません。この問題は無視できません。なぜなら...
歯並びの悪さの原因
実際、多くの人の歯はあまりまっすぐではないことがわかりました。歯並びが悪くても噛むことには影響がない...
小児脳炎の治療方法
脳炎は非常に深刻な病気です。多くの子供が脳炎にかかっています。子供は抵抗力が低く、外部刺激にさらされ...
子どもは高熱を出しているのに、手足が冷たいです。なぜでしょうか?
子どもが熱を出すと大人はとても心配します。熱が出ると汗をかいても手足が冷たい子どももいます。この状況...
どのくらいの熱があると子供はけいれんを起こすのでしょうか?
子どもが熱を出したら、家族は特に熱が高いときは注意する必要があります。では、どのくらいの熱で子どもは...
新生児はクールマットの上で寝ても大丈夫ですか?
暑い夏には、赤ちゃんの新陳代謝が非常に速いです。家の温度が高すぎると、赤ちゃんがイライラしやすく、赤...
子供はエビを食べても大丈夫ですか?
子どもは成長期にあり、さまざまな栄養素を必要としています。では、干しエビは子どもに食べさせても大丈夫...
子供の身長を伸ばす方法
子どもの成長期、親は子どもの身体の健康と発育に非常に関心を持っています。痩せていて小さい子どももたく...
子どもの好き嫌いを直すにはどうすればいいでしょうか?
多くの子供は食事がうまくとれず、食べ物への興味も失っています。中には肉や甘いものしか食べない子供もい...