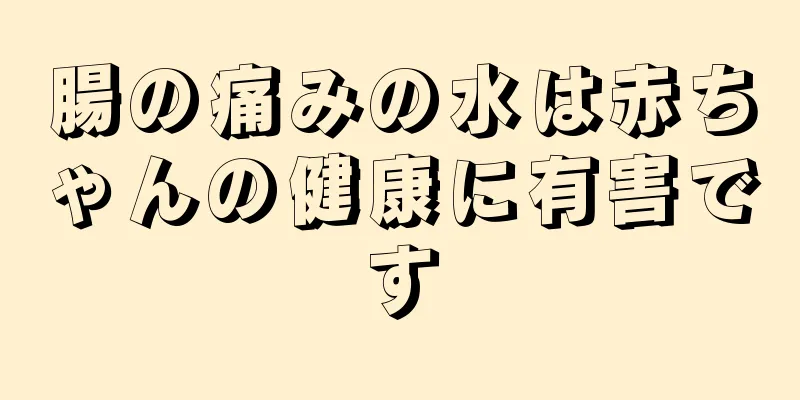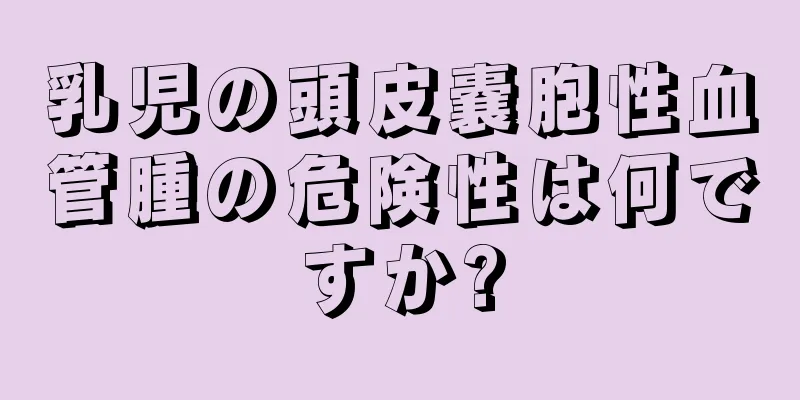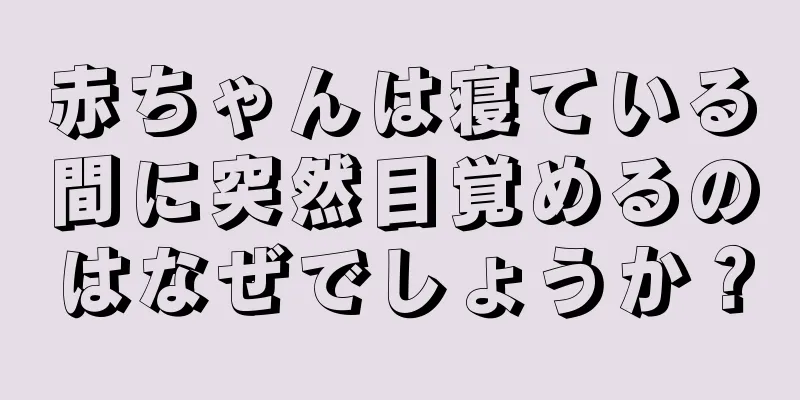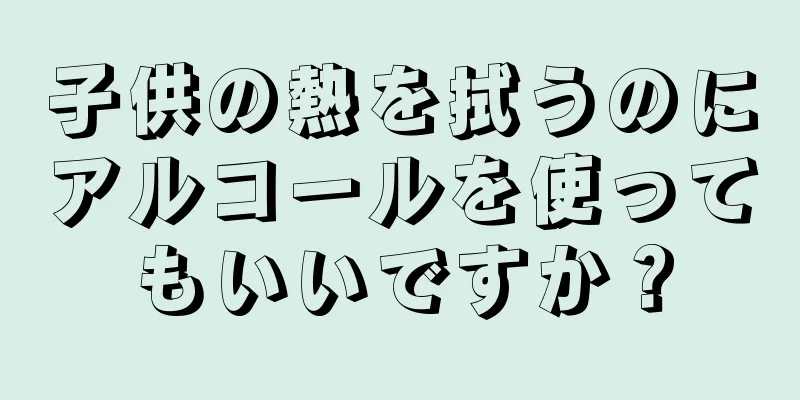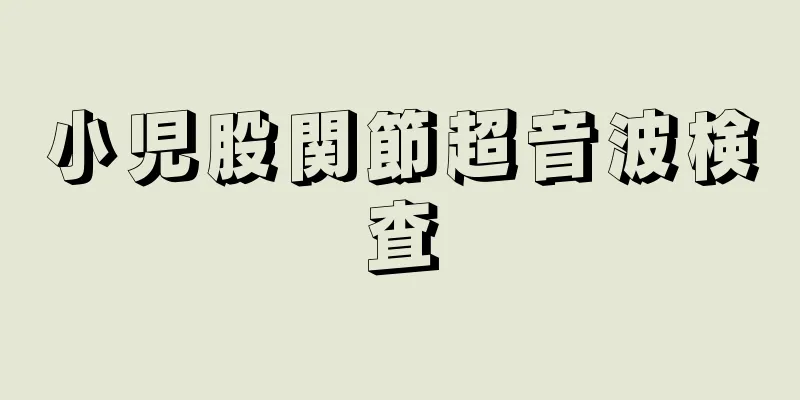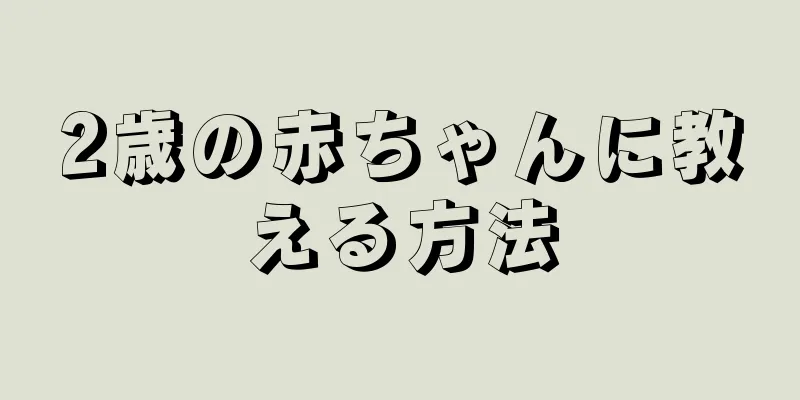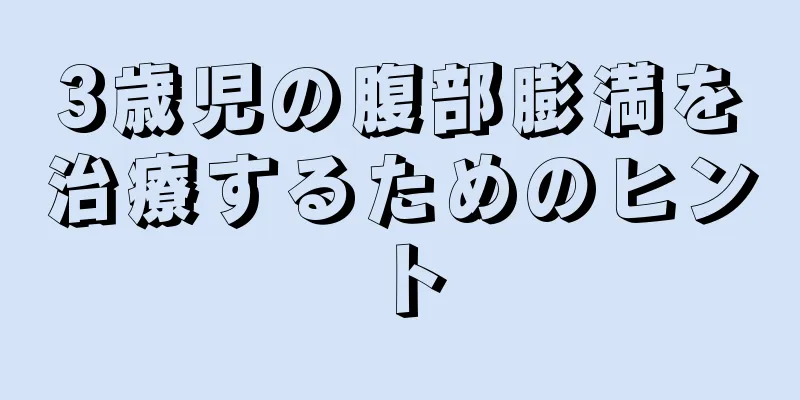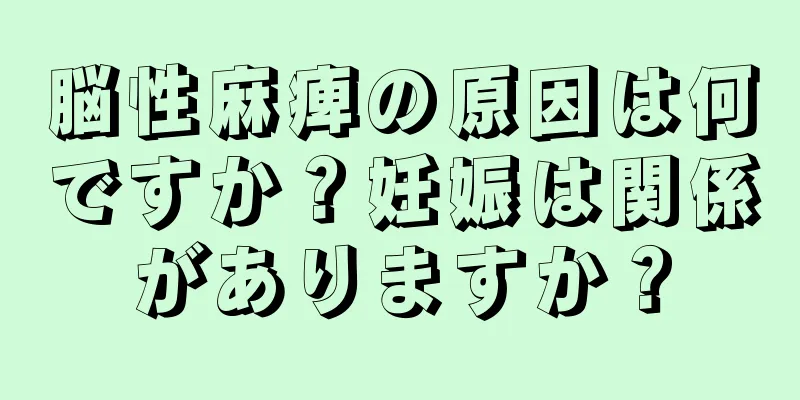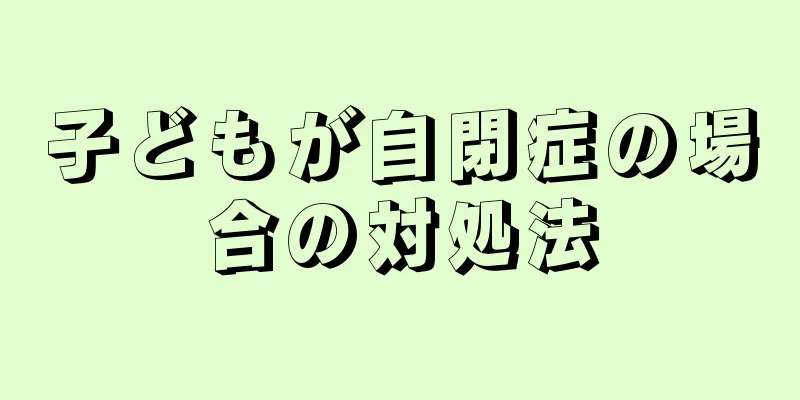小児麻痺
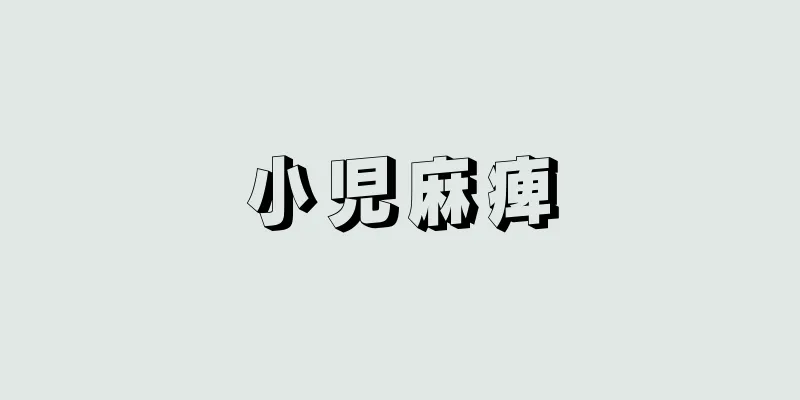
|
麻痺とは、単に体の一部における感覚や運動の喪失を指します。麻痺が起こると、患者の日常生活に影響を及ぼします。子どもの場合、麻痺は将来に影響するため、積極的な治療が必要です。小児麻痺の発生は主にポリオによるもので、ポリオは急性感染症を引き起こしやすく、麻痺を引き起こす可能性のある病気です。 ポリオは、ポリオウイルスによって引き起こされる急性感染症であり、子供の健康を深刻に危険にさらします。ポリオウイルスは神経向性ウイルスであり、主に中枢神経系の運動ニューロンに侵入し、主に脊髄前角の運動ニューロンに損傷を与えます。患者のほとんどは1~6歳の子供です。主な症状は発熱、全身の不快感、重症の場合は四肢の痛み、不規則に分布し程度の異なる弛緩性麻痺で、一般にポリオとして知られています。ポリオの臨床症状は、非常に軽度の非特異的病変から無菌性髄膜炎(非麻痺性ポリオ)やさまざまな筋肉群の弛緩性筋力低下(麻痺性ポリオ)まで、多岐にわたります。ポリオ患者は脊髄前角の運動ニューロンが損傷し、関連する筋肉が神経の調節を失い萎縮します。同時に皮下脂肪、腱、骨も萎縮し、体全体が痩せていきます。 現在、麻痺の発生と進行を抑制できる薬剤はなく、治療は主に対症療法と支持療法となります。 治療の原則は、恐怖を和らげ、骨の変形を軽減し、合併症を予防および管理し、リハビリテーション治療を提供することです。 1. 安静 患者は、熱が下がるまで1週間ベッドで過ごし、40日間隔離し、その後少なくとも2週間は身体活動を避ける必要があります。ベッドに横たわっているときは、フットレストを使用して足とふくらはぎを正しい角度に保ち、機能回復を促進します。 2. 対症療法 解熱剤、鎮痛剤、鎮静剤は、全身の筋肉のけいれん、不快感、痛みを和らげるために使用できます。2~4 時間ごとに 1 回につき 15~30 分間、温湿布を当ててください。温水浴も効果的で、特に幼児には効果的であり、鎮痛剤と併用すると相乗効果があります。条件が許せば、免疫グロブリン 400 mg/(kg·日) の静脈内注入を 2~3 日連続で使用して症状を緩和できます。インターフェロンは初期段階で使用することができ、1日100万単位を筋肉内に注射し、14日間の治療コースとし、軽い受動運動で変形を防ぐことができます。 3. 麻痺 (1)正しい姿勢:患者がベッドに横たわったとき、膝を軽く曲げ、板や土嚢を使って腰と背骨をまっすぐにし、足首の関節を90度にします。骨の変形を防ぐために、痛みが消えたらすぐに能動運動と受動運動を行ってください。 (2)適切な栄養:栄養価の高い食事と十分な水分を摂取してください。高温や温湿布により発汗した場合は、ナトリウム塩を補給してください。食欲不振の場合は、胃チューブを使用して食物と水分の摂取を確保することができます。 (3)薬物治療:ジバゾール、ガランタミン、ビタミンB12などの神経伝導機能を促進する薬剤。二次感染がある場合は適切な抗生物質で治療できる。 |
推薦する
6歳児、ワクチン接種後に腕に痛み
赤ちゃんに予防接種をすると、吐き気や嘔吐、発熱、局所の発赤や腫れなどの副作用が現れます。多くの赤ちゃ...
子どもの食習慣が悪い場合はどうすればいいでしょうか?
多くの子どもたちは、食事の前に手を洗う、食べ物の好き嫌いをするなど、悪い食習慣を持っていますが、多く...
6 歳の子供に適したカルシウムサプリメントは何ですか?
6 歳の子供はまだ重要な発達期にあります。カルシウムは、発達過程における子供の骨の成長に重要な役割...
湿疹がある場合、早く治すために子供に何を食べさせるべきでしょうか?
過剰な湿気は身体に大きな影響を与えます。大人も子供も除湿は重要です。除湿にはさまざまな方法があります...
子供がいつも風邪をひいたり咳をしたりする場合はどうすればいいでしょうか?
大人に比べて、子供は体が弱く、抵抗力も弱いため、特に風邪や咳にかかりやすいです。親はまず、子供を暖か...
なぜ子供は上半身が熱く、下半身が冷たいのでしょうか?
一般的に、人体の体温は比較的バランスが取れていますが、時には熱が出たり寒気を感じたりすることもありま...
赤ちゃんは何ヶ月で話し始めますか?
社会の発展に伴い、子供に才能を発揮させたいと考える親が増えています。子供が新しいスキルを早く習得でき...
子どもたちの安心感を育む方法にはどのようなものがあるでしょうか?
すべての子供が私たちが想像するほど良い子として生まれるわけではありませんし、すべての親が生まれながら...
赤ちゃんが熱を出した後に咳や鼻水が出たらどうすればいいですか?
多くの子どもが風邪をひき、咳をしたり、鼻水が出たりします。これは特に一部の子どもにとっては非常によく...
3歳の赤ちゃんに適した補助食品は何ですか?
赤ちゃんが3歳になると、一般的に離乳が成功します。この時点で、親は赤ちゃんのために補助食品をいくつか...
3歳の子供が機嫌が悪い場合の対処法
子どもがこの世に生まれたとき、彼は白紙のようなものであり、その性格の発達は周囲の人々の影響を受けます...
子供の猫背を直す方法
猫背は、脊椎の変形や胸椎後弯症によって起こることがあります。猫背は非常によくある現象です。外出すると...
子供の近視の分類、真偽を区別し適切な薬を処方する
子供の近視は大人の近視とは異なります。多くの親が意図的または無意識的に子供の目を守っていますが、多く...
赤ちゃんが食べたがらなかったらどうすればいいですか?赤ちゃんが食事中に避けるべき 9 つの間違い!
赤ちゃんがうまく食べてくれないと、多くの親が不安になると思います。そこで今日は、母親の私が赤ちゃ...
赤ちゃんが夜に咳をしたり嘔吐したりしたらどうすればいい?
現在、多くの親が、赤ちゃんの微熱や咳が一向に良くならず、症状が繰り返し再発し、非常に困惑していると報...