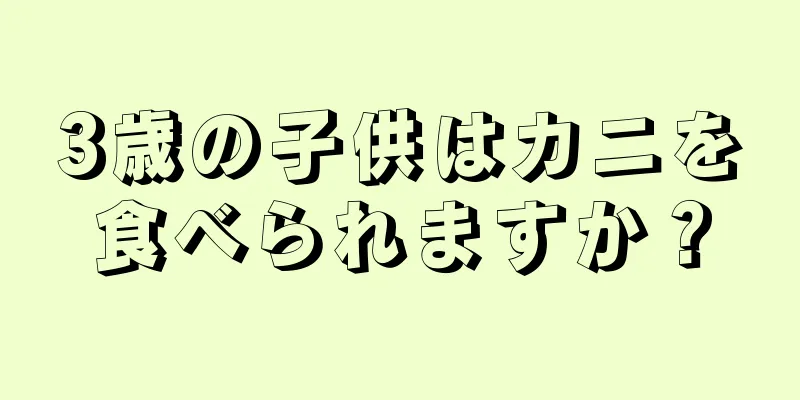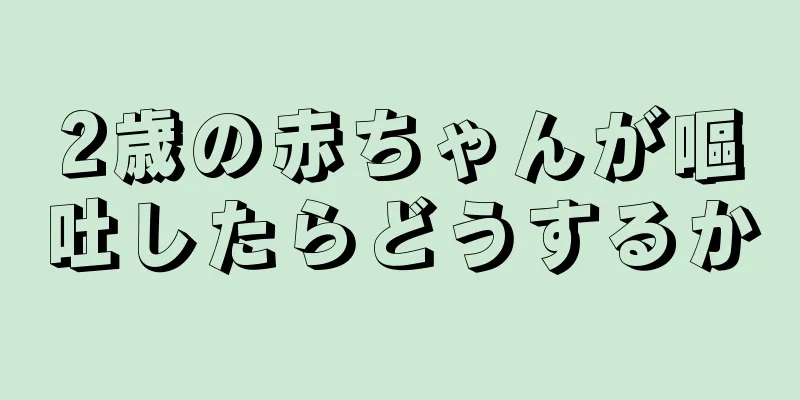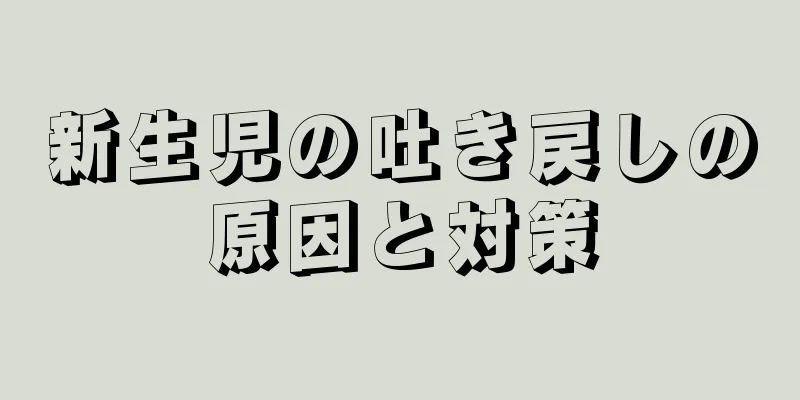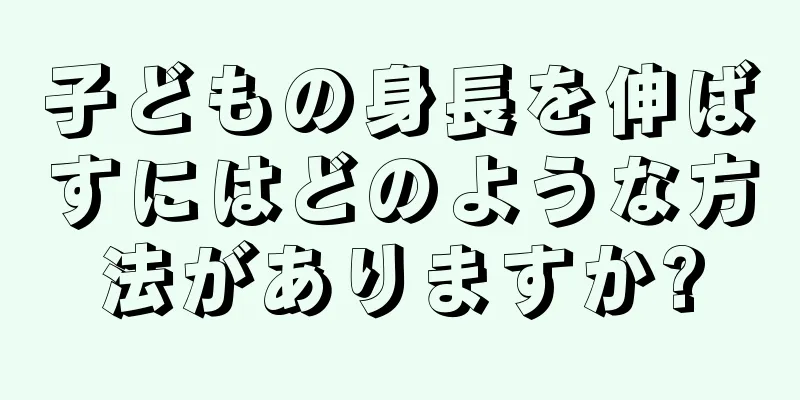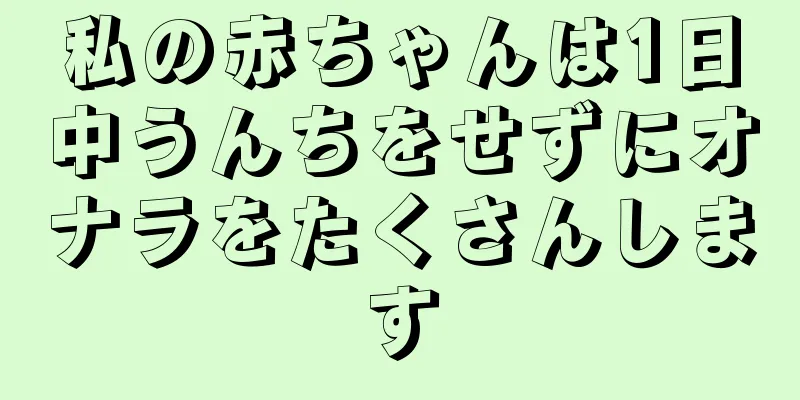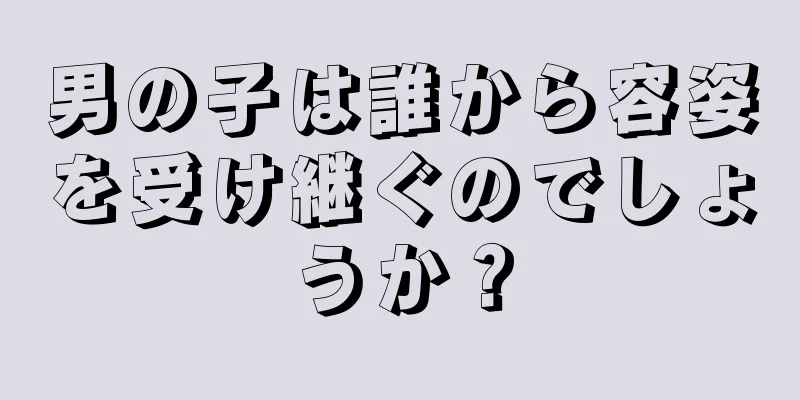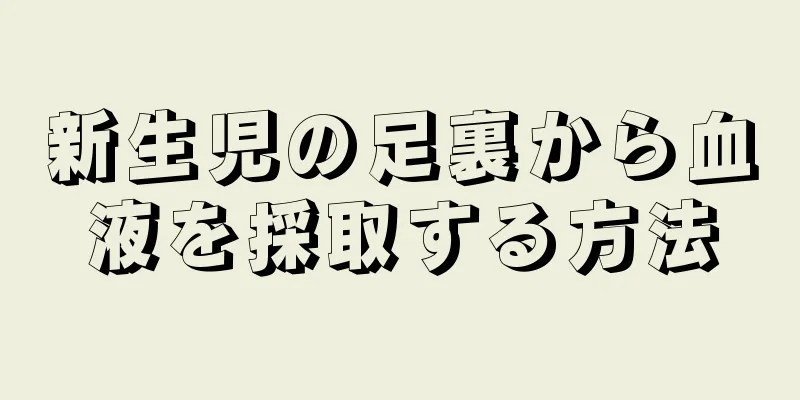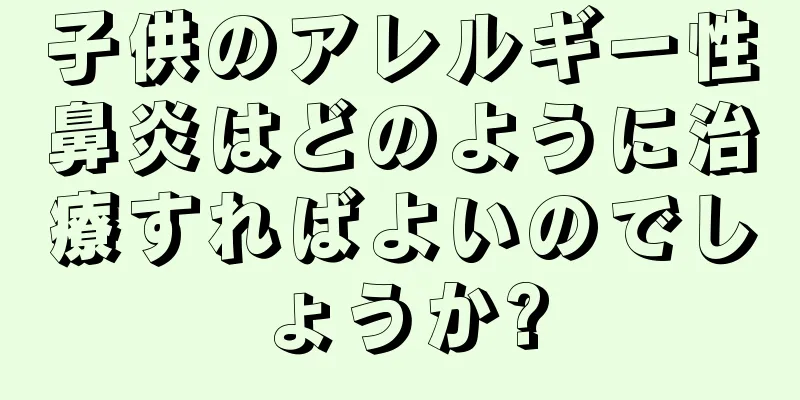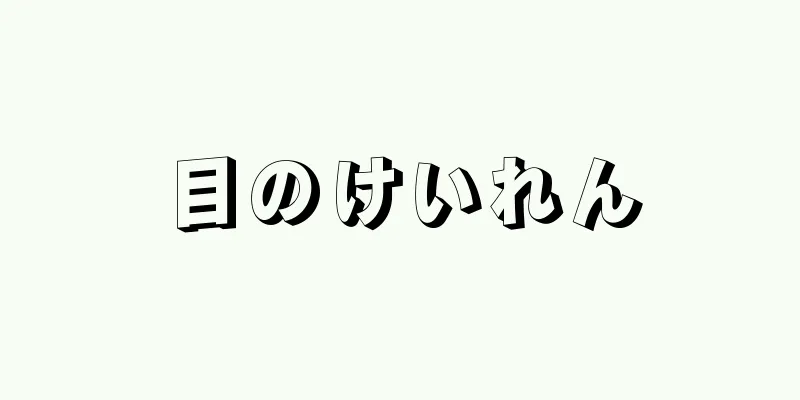生後2ヶ月の赤ちゃんのへそが突き出ている場合はどうすればいいですか?
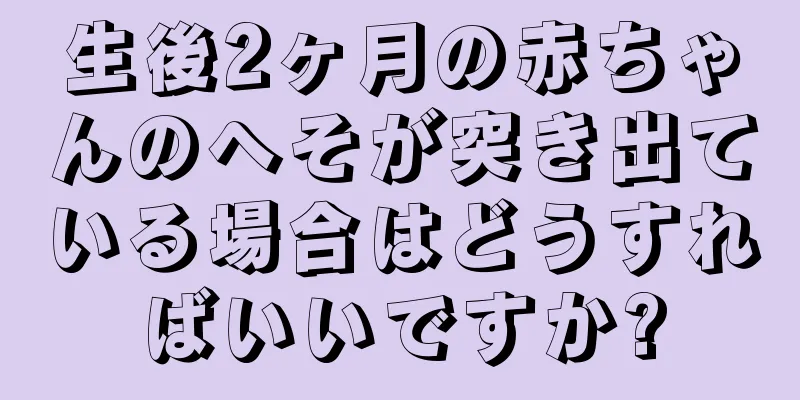
|
へそは、私たちが生まれたときにへその緒が残した傷跡だということは、誰もが知っています。へそはお腹の下にあります。いつもへそを触っていると、お腹が痛くなることがあります。自分を守ることに注意を払わなかったために、へそがひび割れた経験のある人はたくさんいます。そこで今日は、人体におけるおへその役割と日常生活でのおへその保護方法についてご紹介します。 へそは、一般的にはへそとして知られており、基本的には胎児が生まれた後にへその緒が落ちた後に残る傷跡です。臍は腹部の正中線上、上前腸骨棘の高さに位置し、直径は約 1.0 ~ 2.0 cm です。通常は小さな凹みや小さな突起になります。おへその下の腹筋がくぼんでいます。へその小ささは、構造上の弱さにつながり、臍ヘルニアになりやすい原因となることがよくあります。おへそはデリケートな部分なので、日常生活では冷気にさらされたり手で引っ掻かれたりしないよう注意して保護する必要があります。 ケア方法 1. へその衛生に注意してください。夏は汗の量が多く、体の汚れが簡単にへそに入り、汗と一緒に沈着する可能性があります。汚れを落とし、細菌の繁殖を防ぐために、毎日、温水と中性シャワージェルを使っておへそとおへその周りをこすってください。ただし、皮膚を傷つけたり感染症を引き起こしたりしないように、強くこすらないようにしてください。 2.「風」を防ぐことに注意する:おへその周りは胃腸の周りで冷えやすいので、おへそが風邪をひかないように注意しましょう。朝晩の涼しい時期や雨の日の気温が低いときは、お腹の出る服を着ない方がよいでしょう。扇風機やエアコンの冷風を直接おへそに当てないでください。お腹の出る服を着てバイクや自転車に乗るときは、スピードを出さないでください。寝るときは、薄い布でお腹を覆うか、へその緒プロテクターを使用してください。 3. へその偶発的な怪我を防ぐ: へその周りは露出しており、衣服による保護が不十分なため、火傷、擦り傷、引っかき傷などの偶発的な怪我を負いやすい傾向があります。したがって、日常生活や仕事では注意してください。 4. タトゥーを入れないようにしましょう: 見た目を気にする女性は、お腹が見える服は目立たないと考えることが多いため、お腹に模様や永久的なタトゥーを入れるのが好きです。しかし、そうすることで、特定の健康上のリスクが発生します。タトゥーは皮膚の排泄機能を妨げ、湿疹やあせもなどの皮膚疾患を引き起こす可能性があり、タトゥーの色素には身体に有害な化学成分が含まれていることが多い。また、タトゥーを営業所で施し、タトゥー針を共用すると感染症にかかる可能性がある。なので、飾るときには注意してください。 上記は専門家が紹介したおへそに関する常識です。おへそは胃腸管を保護する上で重要な役割を果たしているので、上記に基づいて、おへそのケアにもっと注意を払う必要があります。したがって、私たちは日常生活の中でこの知識にもっと注意を払うべきであり、それは私たちの体を守ることにも役立ちます。上記の内容がお役に立てれば幸いです。 |
推薦する
子供にとって最適な脂肪摂取量はどれくらいですか?
子供の脂肪摂取は脂肪と密接な関係があります。脂肪の摂取量は年齢層によって異なります。脂肪の摂取量が多...
1年生の夏休みのスケジュール
夏休みは、すべての学生が楽しみにしている、とても嬉しいものです。彼らはもう、勉強のプレッシャーや時間...
子供の呼吸困難の原因
子供はすべての親にとって大切な存在です。子供がちょっとした病気にかかったとき、親は子供に代わってその...
子供の一酸化炭素中毒の治療方法
一酸化炭素中毒は生活の中で非常によく見られる現象で、特に秋から冬にかけて寒くなると、多くの人が暖を取...
子供の足首の痛みの治療
多くの子供が足首の痛みを抱えていることは周知の事実です。これは子供にとって大きな悩みの種です。歩くと...
子供の体に小さな赤い発疹
赤ちゃんはどの家族にとっても中心であり、ほんの少しの不快感でも家族全員の気分に影響を与えます。人生に...
子供の身長を伸ばすのに最適な年齢はいつですか?
多くの親や友人たちは、子どもが健康でいてくれることを願うだけでなく、大きく成長してほしいという願いも...
歩くときに子供の猫背を矯正する方法
10代の若者の骨は最盛期です。この時期、骨は成長しています。悪い座り方や寝方、悪い歩き方など、あらゆ...
子供の声がかすれる原因は何ですか?
子どもの声がかすれる原因は、頻繁に大声を出すことによる喉の腫れや炎症が原因の場合があります。母親は子...
赤ちゃんの口の中の水疱性発疹の治療法
どの赤ちゃんも家族の中では大物です。赤ちゃんの皮膚は非常にデリケートで、抵抗力が比較的低いため、大人...
発育後、子供は背が伸びますか?
実際、背が高くなりたい人は多く、母親は皆、自分の子供が背が高くなることを願っている。結局のところ、男...
子どもが内気で臆病な場合の対処法
しかし、人生では、他人に会うと、家族の後ろに隠れて、話したり、他の人を見たり、音を立てたりすることを...
未熟児の心雑音
新生児が早産すると、子供の健康、特に心臓に悪影響を及ぼします。そのため、多くの新生児は早産後に心雑音...
子供の湿疹の治療方法
子供の湿疹を治療するには?子供の湿疹は非常に一般的であるため、すでに多くの治療法があり、薬は無数にあ...
顔色が黄色い子供にはどのように接したらよいでしょうか?
生活水準がかなり高いため、栄養失調は基本的に存在しません。そのため、親は子供の顔が黄色いことに気づい...